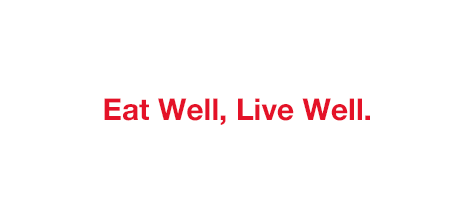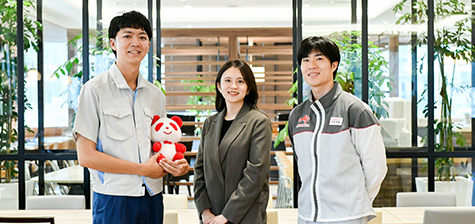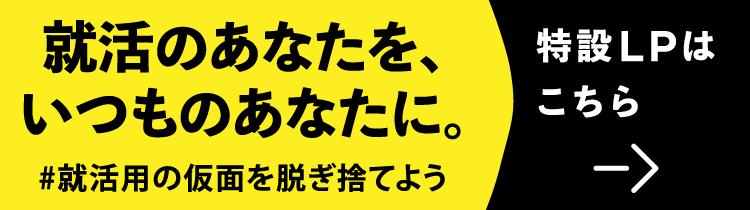社員
R&D
※入社時の職種:R&D

デジタルによる最適化で、
生産現場の
あるべき姿を実現する。
Toshiki
食品事業本部 食品生産統括センター
食品技術部デジタル技術グループ
2023年入社
工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻
※業務内容・所属部署は取材当時のものです
経歴
- 入社1~2年目:
- 食品事業本部 食品生産統括センター スマートファクトリーグループ(工場に関わるデータ分析、データ活用担当)
- 入社3年目:
- 食品事業本部 食品生産統括センター 食品技術部デジタル技術グループ(工場内外を含めた物流に関するデータ分析、データ活用担当)
01
食と技術。
その両面から、自分らしく。

入社動機を教えてください。
食べることが好きだったことに加え、学生時代にIoTデバイスを活用したビジネスコンテストに参加した経験から、食品工場のIoT化やデータ活用に興味を持つようになりました。食品業界のなかでも、味の素㈱は食品だけにとどまらない幅広い分野に挑戦し、さらに海外展開にも積極的。その姿勢に魅力を感じました。また、選考を通じて社員の温かさや、働く環境のよさを実感できたことも大きな決め手です。ほかには電力企業やIT系メーカーなどを検討しましたが、食と技術の両方に関われる味の素㈱なら、自分の経験を活かしながら成長できると感じて入社を決めました。
入社して感じたギャップはありますか?
入社前は、メディアやホームページの印象から「働き方改革が進んだ先進的な企業」というイメージを持っていました。けれど実際には、効率化が十分ではない部分も残っています。特に、企画や提案についての社内承認プロセス。年次や立場の異なる複数の関係者を説得する必要があり、その時間がかかる進め方に戸惑いました。ただ、ここ数年で現場の声を反映しながら改善が進んでいます。変革への意識が会社全体でますます高まっており、私自身も、その流れを推進する役割を担いたいと考えています。また、こうした経験を通じて、よりよい人間関係や働き方について考える機会にもなりました。
02
生産現場の課題を、
デジタルで解く。

現在の仕事内容を教えてください。
IT技術の活用や業務変革による「工場視点での生産最適化」と、事業利益と資産効率を最大化する「バリューチェーン視点でのスマートファクトリーの実現」に携わっています。「工場視点での生産最適化」においては、生産シミュレーションを活用したレイアウト設計や自動化の提案、デジタルツイン技術の活用検討に従事しています。また、「バリューチェーン視点でのスマートファクトリーの実現」では、需要を予測するAIモデルの構築を通じた在庫削減や、BI(ビジネスインテリジェンス)ツール、RPA、AI技術を用いたデータ活用支援業務を行っています。
その仕事のやりがいは何ですか?
現場の悩みをデジタルで解きほぐし、「役に立てた」と実感することに大きなやりがいを感じます。最近の例でいえば、3Dシミュレーションで工場内外の車両動線と積込計画を再現し、レイアウトと運用を見直すプロジェクト。画面上で複数の案を比較しながら関係部署と協議を重ね、構内渋滞やバース運用に関する課題を整理・改善へと導きました。動きの見えるモデルを共有したことで部門間の理解と連携も深まり、現場から「これなら試したい」と前向きな声が上がった瞬間、デジタルの力と自分の貢献が結びついた手応えを強く感じました。

学生時代の経験はどう役立っていますか?
コロナ禍で対面活動が制限された学生時代、私はオンラインゲームに没頭していました。限られた資源と時間で勝利するために、自然と身についたのは小さなPDCAを高速で回す習慣。現在の業務でも、生産シミュレーションや物流設計の課題をデータで可視化し、最短ルートでムダを削っていく過程にその習慣が活きています。さらに、チーム戦で学んだ役割分担と瞬時の情報共有は、社内外の関係者を巻き込んでプロジェクトを推進するうえで大きな武器となっています。
今の仕事を通じて、達成したいことを教えてください。
現在の目標は、生産現場および間接部門で日常的に発生する定型作業をRPAで自動化し、効率化を図ることです。データ入力や帳票作成などの人手に依存する業務をロボットに置き換え、作業時間を半減させつつヒューマンエラーを防止し、現場の付加価値向上に貢献したいと考えています。さらに、空いた時間を分析・改善活動に振り向けられる環境を整え、組織全体の生産性を底上げすることを目指します。
いつか、味の素㈱で成し遂げたいこと
将来的に実現したいのは、「人と地球の双方にやさしい持続可能な食品生産体制」の確立です。サプライチェーン全体を俯瞰し、資源ロスやCO₂排出を最小化する設計に加え、地域社会との共生や労働環境の改善といった社会課題にも応える「あるべき姿」をデザインします。そのために、工場・物流・販売をシームレスに結ぶデジタル基盤を整え、部門横断で知見を結集しながら、安定かつレジリエントな食の供給モデルを世界へ広げていきたいと考えています。