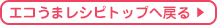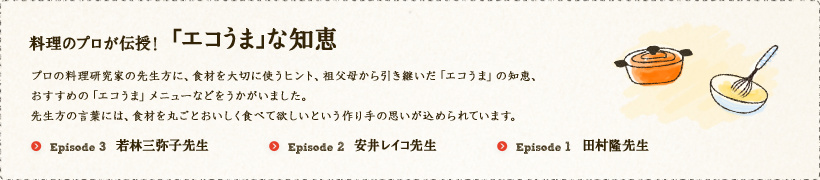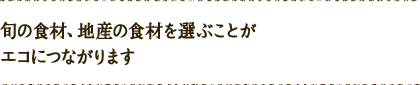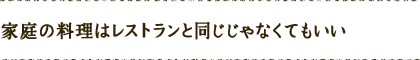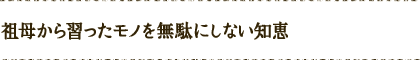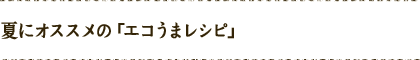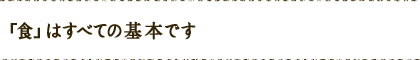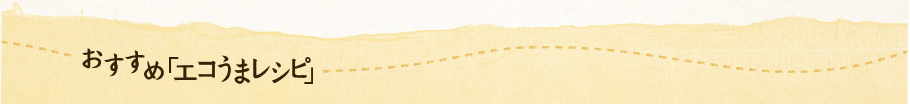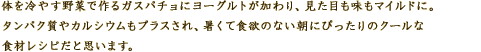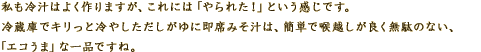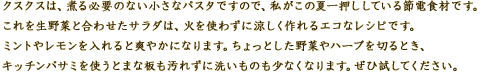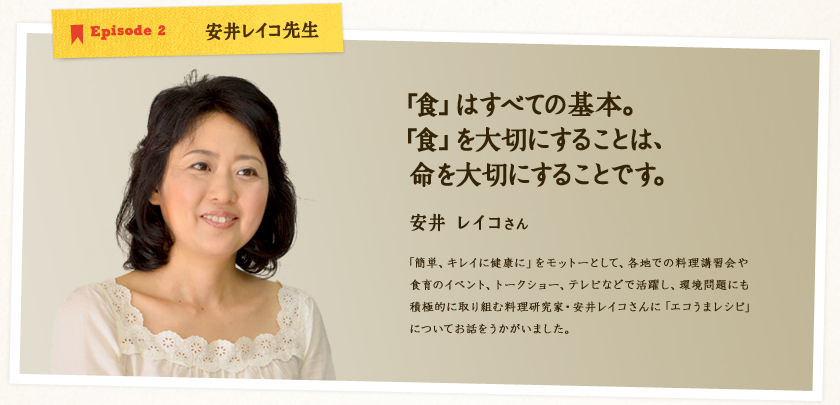
- ホーム>
- 社会・環境>
- 食卓から始めるエコライフ>
- エコうまレシピ>
- 安井先生の「エコうまレシピ」エピソード

私が食材を選ぶとき、できるだけ季節の旬の食材、その地方で獲れる食材を選ぶよう心がけています。
旬の食材というのは、ハウス栽培などと違って余計なエネルギーは使っていません。自然の力だけで育ち、栄養も高くておいしい。また、地産の食材は輸送に余計なエネルギーを使いませんし、それを選ぶことで獲れてすぐのおいしさが味わえます。
また、旬のものは食卓がカラフルで彩りがよく、見た目に楽しくなりますよね。そうすることで食欲もわき、自然と必要な栄養素も取れます。栄養素がどうのこうのと考えて選ぶより楽しいですよね。
エコ、エコと、考え過ぎても楽しくない。電気を使わなくてもガスを使い過ぎるとCO2が出るからどうなんだろう…とか。私は「トータルでエネルギーにかかる費用が安くなればOK」という考えです。それだと分かりやすいでしょ。
例えば料理するとき、暑い台所に立つ時間を短くすることを目指す。そうすると自分も楽ですよね。楽するには段取りを考えて料理することが必要。冷蔵庫も開けてから何があるかな~と探すのではなく、目的を持って開ける。小さいことの積み重ねが大切ですよね。
それに、楽しみながら工夫することも大切。例えばパスタを茹でるとき、私はパスタがひたひたに浸るぐらいのお湯しか使わない。多少パスタ同士がくっついても別にレストランじゃないからいいんですよ。水道代もガス代も節約になります。
「これってなくてもいいんじゃない?やらなくてもいいんじゃない?」といろいろ試してみると楽しいですよ。


私は祖母から家庭料理を教わったんですが、野菜の皮は「むかなくていいよ」と教わりました。確かに、キンピラゴボウやカレーのニンジンの皮なんて気にしませんよね。皮の部分は栄養もあります。手間が省けて、ゴミも減らせ、栄養も高い、と一石三鳥です。もちろん、じゃがいもの皮も新じゃがならむかない、冬場の固いものならむく、お客さんに出すときはむくとか、その時々で考えながらですよ。
祖母は、何ごとも無駄なくやる人でした。
冬場のお野菜を大切に使ったり、お漬物にしたり、と保存方法もいろいろと習いました。特にぬか漬けは、旬のうま味を保存するだけでなく、お野菜のはしっこもいろいろ入れて工夫しながらおいしくしていくんです。うちでは主人のビールも少し入れたりします。
あと、我が家で受け継がれているのが、チラシを折って作る箱。夏場はスイカや枝豆、冬場はみかんをこの上で食べます。ティッシュやお皿を使わないからエコですよね。調理するときも生ゴミをそこに捨てると水分が蒸発するからゴミの量も減り、燃やすエネルギーも少なくてすみます。
夏の時期にオススメの「エコうまレシピ」は、できるだけ火を使わず生の野菜のおいしさを味わえる料理。例えば、「ガスパチョ」や「冷や汁」、「クスクス」。
「ガスパチョ」はアラビア語で「濡れたパン」という意味。もともとは浸して食べていた固くなったパンを料理に混ぜるようになった。世界には、他にも固くなったパンをおいしく食べる知恵がたくさんあります。ハンガリーでは固くなったパンを牛乳に浸して丸めて茹でる「ジェムレゴムボーツ」という料理があります。
「クスクス」は、クスクスと同量のお湯を入れて蒸らすだけで簡単に作れます。まだ馴染みがないですが、野菜と混ぜてサラダにするとおいしい。ミントやお酢、レモンなどの「涼味」を使うことで口の中から爽やかに涼しくなります。


「食」というのは、すべての生きとし生けるものの基本です。体を養って命を次の世代に伝えるために必要なもの。そして「食」を文化にまで発展させたのが人間です。
食べ物を大切にするというのは、命を大切にすること。お米一粒も大切にしましょう、というのは、一粒の命でも大切にしましょう、ということ。それを子供たちに伝えることで、他人のことを思いやれる大人になってくれたら、と思っています。
主婦であり、3人の男の子のお母さんでもある安井レイコさん。
簡単で、地球にもやさしく、楽しいエコのアイディアを提案していただきました。
そして最後に「エコうまレシピ」に挑戦する方々へのメッセージをいただきました。