- 中華だしシリーズサイトTOP
- 中華のまめ知識
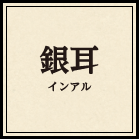

銀耳(インアル)
ふるふるした食感が特徴の白きくらげ。黒いきくらげと比べ、見た目も味わいも繊細です。コラーゲンと食物繊維が豊富で、カロリーはゼロ。美容食として女性を中心に人気があります。食べ方としては、サラダやスープに入れるほか、シロップ煮にしてデザートにも使います。

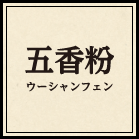

五香粉(ウーシャンフェン)
山椒、八角、桂皮(シナモン)、丁字(グローブ)、陳皮(みかんの皮)、ウイキョウ(フェンネル)など、数種類の香り高い香辛料をあわせて作るブレンドスパイス。料理に少し振り入れるだけで、いかにも本格中華らしい香りがただよってきますが、それだけに使いすぎは禁物。隠し味程度の少量から使い始めるのがおすすめです。使用するスパイスは必ず5つと決まっているわけではなく、種類や混合比率は、地方によって多少の違いがあります。

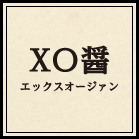

XO醤(エックスオージァン)
香港・ペニンシュラホテル「嘉麟楼」のシェフが1980年代に考案した、新しい調味料。ホタテ貝柱や干しエビ、金華ハムなどの高級食材をふんだんに使って、唐辛子、にんにくなどとともに炒めて作ります。XOは最高級という意味で、最高級ブランデーにも負けない味わい、ということから名前がつけられたといわれています。

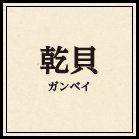

乾貝(ガンベイ)
帆立貝などの貝柱を塩ゆでして、カラカラに乾燥させたもの。干貝ともいいます。酒蒸しなどで食べるほか、戻し汁にはとても上品な味のスープが出るので、上等な料理の味付けに使われています。選ぶときは、あめ色でツヤがあり、粒がしっかりしたものを。

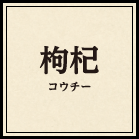

枸杞(コウチー)
クコ。滋養強壮や代謝促進、高血圧予防などに良いという薬膳食材です。古くから人々に親しまれていて「遠くへ行く人にはクコを食べさせてはいけない(=元気になって浮気をしてしまうかもしれないから)」ということわざもあるほど。日本でも健康食品として人気があります。枸杞子(実)は、あざやかな赤色で、干したものはほのかな甘みがあり、そのまま(あるいは水につけて戻して)料理や点心の彩りに使われています。

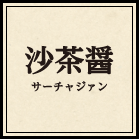

沙茶醤(サーチャジァン)
インドネシア、マレー半島の串焼き「サテ」のソースが元になった調味料。バーベキューソースとも呼ばれています。辛味と香ばしさが複雑にいりまじった味わいで、肉料理との相性はバツグン。炒め物のほか、ステーキやローストビーフにもよくあいます。

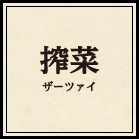

搾菜(ザーツァイ)
日本でもおなじみのザーサイは、四川省の特産品。大頭菜(カラシ菜の一種)の根元にあるコブ状の部分を、塩や粉唐辛子などで漬けこんだもので、重石をして水分を搾って作ることから、搾菜の名前がつきました。独特の辛味と歯ごたえを楽しむため、うすく切ってそのまま食べるほか、細切りにして肉と炒めたり、スープの実にも使います。塩味が強すぎるときは、水につけて塩抜きをしてから使いましょう。

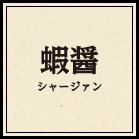

蝦醤(シャージァン)
ペースト状の調味料で「えびみそ」とも言われます。アミ(小魚)や小エビに塩を加えて、毎日かきまぜながら発酵させて作るもので、しょっつるやナムプラーなど魚醤の仲間。炒め物などの隠し味に少量加えると風味が増します。

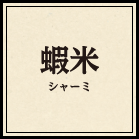

蝦米(シャーミ)
芝エビ、手長エビ、桜エビなど、小ぶりのエビをゆでて乾燥したもので、エビらしいコクとうまみがあります。選ぶときは、大きさがそろっていて、香りのよいものを。戻さずに水洗いしてそのまま使うこともできます。戻して使う場合には、水につけるだけでよく、戻したあとの汁は、だしとしても利用できます。

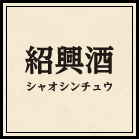

紹興酒(シャオシンチュウ)
もち米と小麦が主原料の醸造酒。おだやかな酸味と少々の渋みが特徴です。アルコール度数は16度程度。正式に「紹興酒」と名乗れるのは、浙江省、紹興市で作られたものだけ。年代物は老酒(ラオチュウ)として珍重されています。温めて氷砂糖やザラメを入れる飲みかたは日本特有のもの。中国では常温ストレートが一般的です。料理酒として使う場合は、うまみを増すために、煮込み料理や炒め物に少量入れることが多いようです。

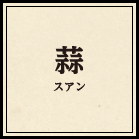

蒜(スアン)
日本でもおなじみニンニクのこと。ユリ科のネギ属の植物で、臭いは強烈ですが、強壮や食欲増進に効果があり、中華料理でもいため物には欠かせない野菜のひとつです。日本で普通に食べられているのは根の鱗形(りんけい)と呼ばれる球の部分。緑色が鮮やかなニンニクの芽(茎にんにく)は、花が開く前のにんにくの花茎。最近では、葉ニンニクが野菜として出回るようになりました。いずれも油で炒める料理によくあいます。

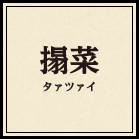

搨菜(タァツァイ)
日本ではターサイまたはタァサイと呼ばれる中国野菜。きさらぎ菜、ちぢみ菜、ひさご菜などの別名があります。「搨」は「くぼんだ」「押しつぶされたような」という意味。葉の表面に縮れたようなしわがあるのが特徴です。選ぶときは緑色の濃いものを。暑さや寒さに強く、日本では一年中栽培されています。油との相性が良いので、炒め物、炒め煮などに向いています。

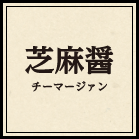

芝麻醤(チーマージァン)
白ごまのペースト。炒った白ごまをすりつぶし、植物油を加えて練ったものです。ごまの香りが香ばしく、コクがあるのが特徴です。バンバンジーのソースに加えるほか、なべの薬味や、冷たい麺のタレなどにも使われます。練りごまとして、ごま和えなどの和食にも応用可能です。

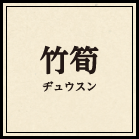

竹筍(ヂュウスン)
タケノコ。淡白でくせがないので、中華料理では主材料、副材料どちらにも幅広く使われています。冬にとれるものを冬筍(ドンスン)、春のものを春筍(チュンスン)と呼び、最高級品は柔らかい冬筍。日本でもおなじみの孟宗(もうそう)竹は、孟宗という人が病気の母親のために、必死で掘りあてたことから名前がついた、という伝説があります。

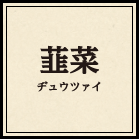

韮菜(ヂュウツァイ)
ニラのこと。ユリ科の多年草。緑色のものは、昔から日本の食卓でもおなじみですが、最近では、遮光栽培した韮黄菜(ヂュウホワンツァイ・黄ニラ、にらもやし)や、ニラのつぼみを食べる韮花菜(ヂュウホウツァイ・花ニラ)なども出回っています。

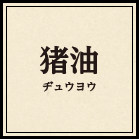

猪油(ヂュウヨウ)
ラード。豚の脂を精製したもの。コクがあり、しっかりとした味わいになります。最近では、炒め物などは植物油で代用することもあります。点心では中華まんなどの生地になめらかさをプラスするために使います。

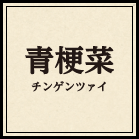

青梗菜(チンゲンツァイ)
身近な中国野菜として日本でもすっかり定着したチンゲンサイ。煮崩れにくく、アクやクセがないので、調理しやすいのが特徴です。原産は中国華南地方。日中の国交が正常化された1970年代以降になって、日本でも栽培されるようになりました。白菜の一種で、旬は冬。ビタミン類を多く含み、冬の風邪予防のためにも、積極的にとりたい野菜のひとつです。

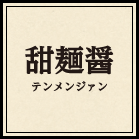

甜麺醤(テンメンジァン)
ねっとりとしたまろやかな味が特徴の中国の甘みそ。日本の八丁みそにも似ています。回鍋肉などの炒め物や、煮物の味付けに使われているほか、そのまま北京ダックのつけみそにしたり、生野菜につけてもおいしく食べられます。

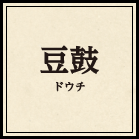

豆鼓(ドウチ)
味噌なっとう。日本の浜納豆や大徳寺納豆などの糸を引かない乾燥納豆とほぼ同じものです。大豆を蒸して、発酵させ、塩漬けして作ります。食感はやわらかく、味噌と醤油をあわせたような味。独特のうま味があります。刻んでいため物、煮物などに使います。

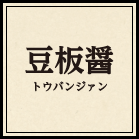

豆板醤(トウバンジァン)
ピリッと辛い唐辛子みそ。蒸したソラマメと小麦粉を発酵させ、唐辛子、塩を加え、長時間寝かせて作ります。麻婆豆腐をはじめ、炒め物、煮物、あんかけなど、辛味が特徴の四川料理を中心に、料理用、食卓調味料の両方に使われています。辛い味が好きなら、ラーメンや餃子などに入れてみるのもおすすめ。

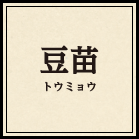

豆苗(トウミョウ)
えんどう豆の苗。発酵して間もない茎と柔らかい葉を摘みとって食べます。収穫期間が短いため、もともと高価な野菜ですが、豆ではなく苗をとるために改良された品種や、水耕栽培のものもあり、身近になってきています。えんどうの苗だけに、えんどう豆と同じような香りがありますが、味はほうれん草に似ています。使い方もほうれん草とほぼ同じで、炒め物やスープの具などに使います。

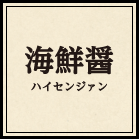

海鮮醤(ハイセンジァン)
大豆で作ったみそに、ゴマ、にんにく、香辛料で香りをつけ、酢などで味を調えたもの。甜麺醤と同じく甘みそですが、大豆が多いため、甜麺醤よりも濃厚な味わいになっています。焼肉や生野菜、北京ダックにつけて食べるのが一般的。調味料として、炒め物の風味づけなどにも使うこともあります。

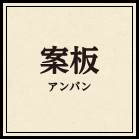

案板(アンバン)
めん台。生地をこねたり伸ばしたりするための台です。大きめのものが作業をしやすいようです。ラワン材や大理石など、さまざまな素材のものがありますが、家庭では清潔にしたダイニングテーブルなどでも代用可能です。

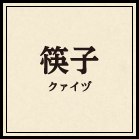

筷子(クァイヅ)
食卓で各自が使う箸のこと。中国の箸は太さがほぼ均一で、木製、プラスチックなどのほか、ひすいや象牙も使われています。中国料理のテーブルセッティングでは、箸は箸置きに乗せ、取り皿の右横に縦長に置くきまり。箸置きを使うのは、日本の影響だといわれています。ちなみに、日本の箸は中国から伝来したもので、魚の骨を除きやすくするため先が細く変わったといわれています。

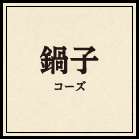

鍋子(コーズ)
中国鍋のなかでも、両手のついた鍋のこと。炒める、煮る、蒸す、焼く、揚げるなどほとんどの調理が可能な万能選手です。底がやや浅いのが広東鍋、やや深いのが四川鍋。素材は、鉄、アルミニウム、ステンレス、チタンなど、さまざまなものがあります。ちなみに、中華鍋の底が丸いのは、火にあたる面積を大きくして、熱が平均してまわるようにするためです。

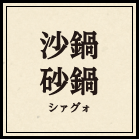

沙鍋・砂鍋(シァグォ)
土鍋のこと。中の食材が冷めにくいので、弱火でゆっくり煮込む料理に適しています。中華おこわやおかゆを炊いたり、スープを作るときなど、家庭にひとつあると便利。和風の鍋料理につかう土鍋で兼用できます。

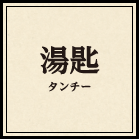

湯匙(タンチー)
「れんげ」「ちりれんげ」とよばれるスプーン。汁の垂れそうなものを食べるときに、これを左手にもち、右手の箸と同時に使うとスマート。日本で「ちりれんげ」と呼ばれるようになったのは、この湯匙の形が、散ったレンゲの花びらに似ていることに由来しているといわれています。

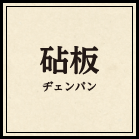

砧板(ヂェンパン)
中華料理に特有の円形のまな板。直径30~80センチ、高さ20~30センチ。重い中華包丁をほどよい弾力と強度で受け止めるため、大きく厚みがあるのが特徴。ケヤキ、サクラ、イチョウなどの木材を輪切りにして作ります。年輪がきめ細かく均等なもの、木の香りがしないものを選びましょう。最近では、プラスチック性のものが主流になっています。

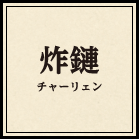

炸鏈(チャーリェン)
たくさんの穴があいた片手の中華鍋。ジャーレン。中華鍋の中に入れて、食材を湯や油の中から一度にすくいあげるのに使います。湯切り、油切りがカンタンにでき、ゆでむら、揚げむらが防げるという利点があります。中華鍋より一回り小さいサイズの物が使いやすいようです。

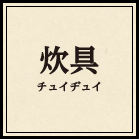

炊具(チュイヂュイ)
調理器具全体のことをいいます。ひとつの中華鍋で、多彩な料理ができることからもわかるように、中華料理の調理器具や道具類はとてもシンプルで、種類もそれほど多くないのが特徴。長い歴史の中で、必要なものだけが残り、不必要なものはそぎ落とされた、といえるのです。

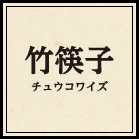

竹筷子(チュウコワイズ)
竹製のさいばし。中華料理のゆで箸や麺箸は、日本のさいばしと違い、太さが均一です。もしも、中華料理を意識してさいばしを新調するなら、やや太めのものが麺をほぐしやすいのでおすすめです。

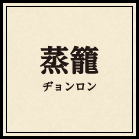

蒸籠(ヂョンロン)
中華饅頭、シュウマイ、チマキ、茶碗蒸しなどを作る際に使う中華せいろ。竹製や木製で、余分な蒸気がぬけるので、ふっくらおいしく蒸し上がります。使い方は、お湯をわかした中華鍋の上に乗せるだけ。お湯が足りなくなったら鍋に熱湯を足します(水では温度が下がってしまうため必ず熱湯を)。使うたびに高温の蒸気で殺菌されるので、お手入れは汚れをざっと落とす程度でOK。使わないときは、通気性の良い場所に保管します。直径30センチくらいのものを中籠(チョンロン)、10~15センチほどのものは小籠(シャオロン)といいます。

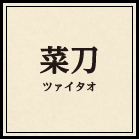

菜刀(ツァイタオ)
包丁のこと。いわゆる中華包丁は両刃で重みがあるため、硬いものでもあまり力を入れず切れるのが特徴。広い側面で材料を押しつぶすこともできます。長方形の方頭刀(ファントウダオ)は四川、広東料理用のもの。ほかに上海包丁とも呼ばれる圓頭刀(ユエントウダオ)、北京料理でよく使われる馬頭刀(マートゥダオ)があります。素材の切り方は刀工(ダオゴォン)、包丁さばきは刀法(ダオファ)と呼んでいます。

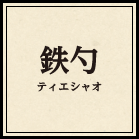

鉄勺(ティエシャオ)
鉄製の中華「おたま」。日本のおたまと同じように、汁ものを移すのに使うほか、素材を炒めるのにも使います。高い火力で調理しても、やけどをしにくいように、柄が長くなっているのが特徴です。半円形の部分にどれだけ入るか、だいたいの容量を把握しておくと、調味料やスープを入れるときに計量カップ代わりになって便利です。

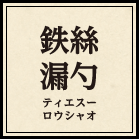

鉄絲漏勺(ティエスーロウシャオ)
金網のしゃくし。ストレーナー。中華なべで揚げた食材や、ゆでた麺類をすくいあげるのに使います。目の粗いもののほうが湯切れ、油切れが良いようです。熱を伝えないように、柄は竹でできています。

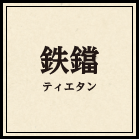

鉄鐺(ティエタン)
「鐺」は底の平らな鍋のこと。鉄鐺はフライパンのような平底鍋で、日本では「餃子鍋」と呼ばれていることもあります。その名の通り、焼餃子をはじめ、焼肉、焼餅など、焼きものを作る際に使います。家庭ではフライパンやホットプレートで代用してもいいでしょう。

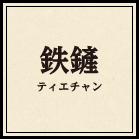

鉄鏟(ティエチャン)
炒めている食材を混ぜたり、焼いたものを裏返したり、食材の形を整えたりするのに使う鉄製のへら。強い火力でやけどしないよう、柄が長いのが特徴です。鉄やチタンの中華鍋ではなく、テフロン加工の炒め鍋を使う場合は、ナイロン製など、鍋の加工を痛めにくい素材のへらを使います。

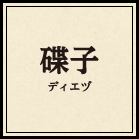

碟子(ディエヅ)
食卓で各自が使う取り皿のこと。平たい皿と深めの皿の2種(いずれも直径18~15センチ)があり、平皿にはソースがかかっていない揚げ物などを、深めの皿には汁物を使います。料理の味が混ざらないよう、こまめに取り替えるのがマナー。家庭でお客様をおもてなしする際には、数は多めに用意しておきましょう。

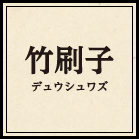

竹刷子(デュウシュワズ)
ササラ(簓)。細く切った竹を束ねたブラシ状のもので、中華鍋を洗うのに使います(亀の子タワシでも代用可能)。鉄製の中華鍋は表面の油膜が落ちるとさびやすいため、洗う際に洗剤は使わず、湯を沸かしてササラで汚れをこすり落とします。

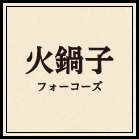

火鍋子(フォーコーズ)
中国版「しゃぶしゃぶ」ともいえる火鍋(フォーコー)のための鍋。ドーナツ型になっているのは、スープを対流させて温度を一定に保つためです。食卓で煮ながら食べるのは日本の鍋料理と同じ。伝統的なものは熱伝導のよい銅製で、中央に木炭を置いて加熱していました。

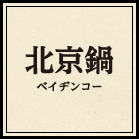

北京鍋(ベイヂンコー)
中華鍋のなかでも、片手鍋のこと。北京など、北方で使われることが多い鍋です。どんな料理にも使えますが、チャーハンや野菜炒めなど、特に炒めものを作るのに向いています。炒めながら鍋を振って、食材を宙に舞わせることを「あおる」といいます。かっこよく鍋をあおるには少し練習が必要です。

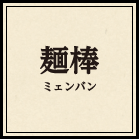

麺棒(ミェンバン)
めん棒のこと。中華料理では麺類の生地や餃子の皮などを薄く伸ばすのに使います。シンプルな棒状のもの、両端が細くなったもの、中に細い棒を通したものなど、太さ、長さ、形はさまざまで、用途に応じて使い分けます。餃子や肉まんの皮などを作るには、長さ20~30センチ、直径2~3センチくらいの麺棒が向いています。

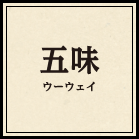

五味(ウーウェイ)
「うま味・甘み・塩味・酸味・苦味」の5種類の味のこと。これら5つの味のバランスによって、料理の味が決まります。おいしい中華料理を作るには、五味の調和がとても大切。やっぱり、中華もおだしが基本なのです。

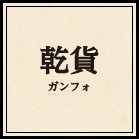

乾貨(ガンフォ)
中華料理に欠かせない乾物のこと。陸産物の山珍、海産物の海味とにわけられます。日本は庶民的な保存食料というイメージが強い乾物ですが、中華料理の乾貨はフカヒレ、ウミツバメの巣、干しなまこなど高級食材も多いのが特徴です。中国で乾物が発達したのは、広大な土地で食物を運搬するために保存性を高める必要があったため。貝柱やシイタケのように、乾燥させることで味や栄養価がアップするものと、素材そのものには味がなくゼラチン質の感触を楽しむもの(フカヒレなど)があります。

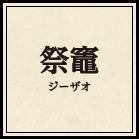

祭竈(ジーザオ)
旧暦12月23日(または24日)。かまどの神様をまつる日。かまどの神様が、この日天に昇り、その家の人のようすを天の玉皇大帝に報告をするといいます。よい報告をして幸せがもたらされるように、かまどにお供えをし、また、まずいことを話されて災いを受けないように、絵に描いた竈神の口に水飴を塗るという風習があります。

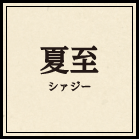

夏至(シァジー)
一年で一番昼が長く夜が短い日。6月21日ごろ。地方によっては「冬至餛飩(餃子)、夏至麺」といって、夏至には麺条(麺料理)を食べる習慣があります。

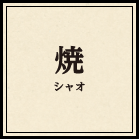

焼(シャオ)
焼き物ではなく、煮込み料理のこと。多くの中華料理では、食材をあらかじめ炒めたり揚げたりしてから煮込みます。これは肉のうまみを逃がさないためと、野菜の型崩れを防ぐため。弱火か中火でじっくり煮込んで、おいしさを引き出します。

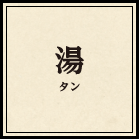

湯(タン)
中華料理のスープのこと。日本料理のだし、西洋料理のブイヨンにあたり、湯菜(タンツァイ)としてスープ料理で出されるほか、煮込み料理や炒め料理など、ほとんどすべての料理で味のベースになるものです。動物性の鶏肉や干し貝柱、中国ハムなどから作る葷湯(ホンタン)、シイタケなど植物性の素材から作る素湯(スータン)にわけられます。また、透明感のあるスープを清湯(チンタン)、片栗粉などでとろみをつけたスープを濃湯(ノンタン)といいます。

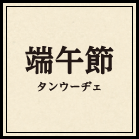

端午節(タンウーヂェ)
旧暦の5月5日。「端午」は月の始めの午の日のことで、「午」は「五」に通じることから毎月5日になり、数字が重なる5月5日を「端午の節句」と呼ぶようになりました。元々はしょうぶ酒などの薬酒を飲み、健康を祈る日でした。日本でも端午の節句にチマキを食べますが、これは中国から伝わったもの。約2300年前頃、湖に身を投げた屈原(くつげん、政治家・詩人)が、あの世で空腹にならないように(魚が屈原の体を食べないようにという説もあります)、民衆が竹筒に米を入れて投げ入れたのがチマキのはじまりといわれています。ちなみに日本で男の子の節句になったのは「菖蒲」を「尚武」として、武士が盛んに祝ったのがきっかけです。

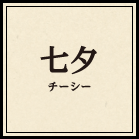

七夕(チーシー)
旧暦の7月7日。日本で「七夕の起源」として知られている織姫と牽牛の伝説は、中国から伝わったものです。中国ではかつてこの日を「乞巧節」といい、織姫が機織り上手だったことにあやかって、手芸や針仕事の上達を祈る習慣がありました。現在では「七夕情人節」といえばバレンタインデー(西洋情人節)と並ぶ恋人たちの日。仲の良いカップルを多く見かけます。

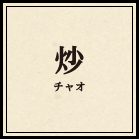

炒(チャオ)
強火、高温の油で手早く炒めること。生炒(下味をつけずにいためる)、清炒(衣をつけずにいためる)、乾炒(粉をつけていためる)、京炒(卵入りの衣をつけていためる)があります。強火でスピーディに炒めるためには、あらかじめ食材は切りそろえ、調味料も事前に計量、手にとりやすい場所にそろえておくことが必要です。

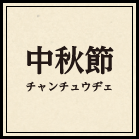

中秋節(チャンチュウヂェ)
旧暦8月15日。団圓節(トアンユエンヂェ)ともいいます。日本でいう「中秋の名月」。この夜の満月が、もっとも明るく丸いといわれ、家族で月餅(ユエピン)を食べながらお月見をする習慣があります。月餅は甘いものばかりではなく、チャーシュー入りのものや、植物性の材料だけを使ったものなど、地方や好みによって、味も色どりも千差万別。遠くに住む家族や友人には月餅を贈って親愛の情を示します。

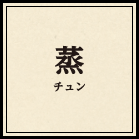

蒸(チュン)
蒸しもの、蒸し料理。中華鍋にお湯を大目に入れ、蒸籠を乗せて作ります。蒸籠を乗せるのは湯気があがってから、さらに調理中はなるべくフタを取らないのがコツ。皿に盛りつけた調味済みの食材を蒸して仕上げるときは蒸し時間を短めに、肉を柔らかくしたいときなどは長めにします。

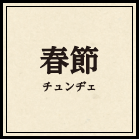

春節(チュンヂェ)
旧暦の1月1日。一年で一番大切な行事と考えられています。大晦日の夜には家族が集まり、縁起のよい話をしながら年夜飯(ニェンイエファン)、団年飯(トアンニエンファン)というごちそうを食べます。元日、北京など北方地方では、縁起物として餃子を食べる習慣があります。

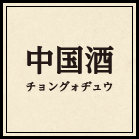

中国酒(チョングォヂュウ)
お酒と人間のつきあいは古く、中国では6~7千年前の新石器時代の啤酒器が発掘されています。現在の中国では醸造酒、蒸留酒、混成酒、ビールなどがよく飲まれています。醸造酒は中国に古くからある穀物が原料の黄酒(ホワンチュウ、紹興酒も黄酒の一種です)、葡萄酒(ブイタオチュウ)など果実酒があります。蒸留酒としては、ブランデー、ウイスキーと並ぶ世界三大蒸留酒の白酒(パイチュウ)が有名です。混成酒は、醸造酒や蒸留酒に果実や花などを入れたもので、薬効のあるものが多いようです。

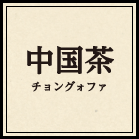

中国茶(チョングォファ)
日本でも最近人気の中国茶。約4700年前から飲まれていた、というほど歴史は古く、日本茶や紅茶のルーツも中国にあります。種類は千種以上と驚くほど多彩。緑茶(不発酵茶)、白茶(微発酵茶)、青茶(半発酵茶、ウーロン茶)、紅茶(発酵茶)、黄茶、黒茶(いずれも発酵を止めたあとに別の菌類で発酵させる後発酵茶)の6つに大きく分けられ、ほかに茶葉を固めた緊圧茶、花の香りのついた花茶なども飲まれています。

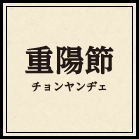

重陽節(チョンヤンヂェ)
旧暦9月9日、陽数の9が重なるので「重陽」といいます。「九九」は長久平安をしめす「久久」につながり、縁起がよいとされています。重陽が祭日になったのは、およそ2000年前の東漢の時代のこと、ある人が「九月九日に災いにあう、免れるためには、家族全員で高い所に登って菊花酒を飲め」という予言を受けたことから、同日に山の上などから景色を眺めつつ菊花酒を飲み、災いを避ける風習が流行りだしたといわれています。

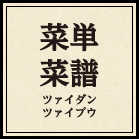

菜単、菜譜(ツァイダン・ツァイプウ)
メニューのこと。中華料理の一般的なコースは、冷盤・拌盤(冷たい前菜)→熱炒(温かい前菜)→大菜(主菜)→湯菜(スープ)、点心(デザート)、果物→お茶、の順です。宴席などではこの順番でサーブされますが、日本の家庭料理と同じように、中国でも普通の家庭料理では、ほとんど気にしていないようです。

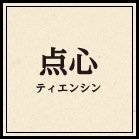

点心(ティエンシン)
食事ではなく、軽食や間食などで食べるもののこと。食べる時間帯によって早点(朝食を点心ですませることも多いようです)、午点(おやつ)、晩点(夜食)と呼ばれています。種類は豊富で、大きく分けると、甘くない鹹点心(餃子、シュウマイ、春巻きなど)と甘い甜点心(ごまだんご、杏仁豆腐、月餅など)があり、いずれも見た目が華やかで凝ったものが多いのが特徴です。点心というと思い浮かべる「飲茶(ヤムチャ)」は、お茶を飲みながら、点心をつまむこと。これは広東や香港の呼び方で、ほかの地方では吃点心(チディエンシン)といいます。

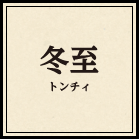

冬至(トンチィ)
一年でもっとも昼が短い日。中国の北方地方では、寒さを乗り切るため、冬至にワンタンを食べる習慣があります。その起源は漢時代。張仲景という名医が、貧しい人々の耳に痛そうな凍傷ができてしまっているのを見かねて、羊の肉や薬味を小麦粉の皮に包んだ食べ物を与えて治療したことからきている、といわれています。

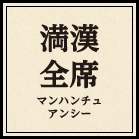

満漢全席(マンハンチュアンシー)
中国料理のなかでも最大にして最高の宴席。もとは清時代の宮廷料理で、満漢全席の「満」は満州族、「漢」は漢族のこと。満州族と漢族、両方の料理のなかから、おいしいもの、すばらしいものを持ち寄って集大成したものです。料理の数は少なくとも70品目以上、200品を越えることもあります。宴席は短くても1回3時間、長いものだと3晩にもわたって繰り広げられます。

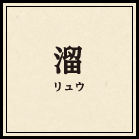

溜(リュウ)
いわゆる「あんかけ」。料理の最後に水溶き片栗粉などでとろみをつける調理法をいいます。上手に作るコツは、もとの味付けは薄味にしておき、最後のあんで味を調整すること。調理に入る前に、片栗粉を水に溶いておくなど、あらかじめ用意しておくと、手順がスムーズです。



