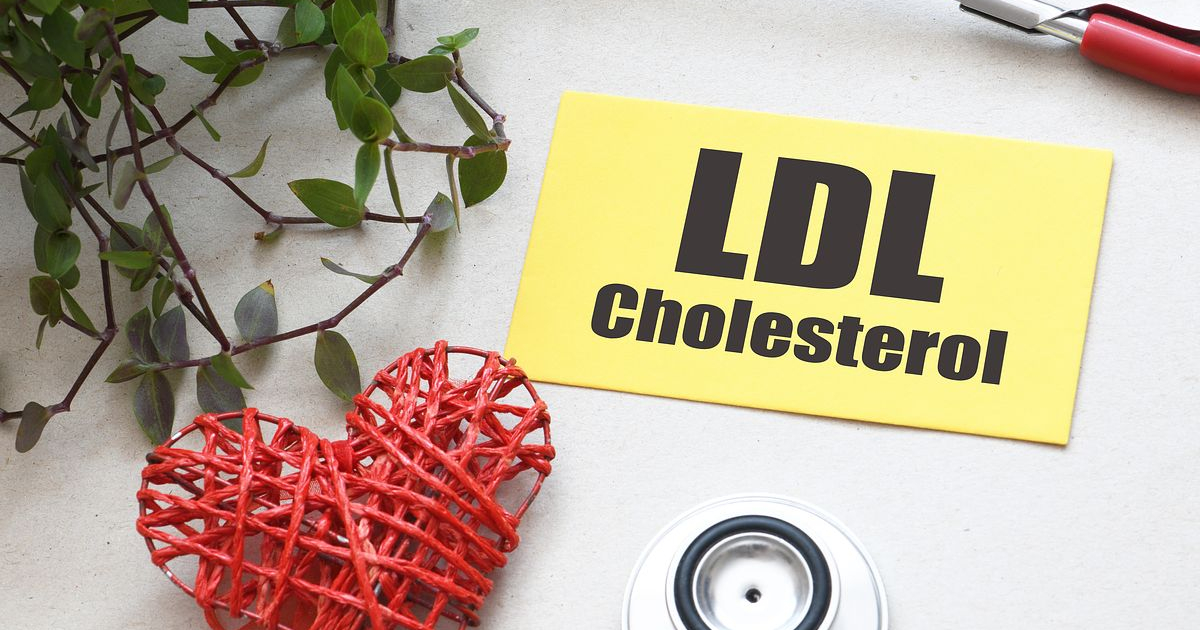野菜は冷凍保存が便利!保存のコツや野菜別の冷凍方法・使い方を紹介

野菜は常温や冷蔵で保存されることが多いですが、使い切れずに傷んでしまうケースもあります。すぐに使わない野菜は、冷凍保存しておけばより長持ちして最後までおいしく食べられます。
この記事では、野菜を冷凍保存するコツや具体的な方法を野菜別に紹介します。野菜に適した保存方法をマスターして、毎日の食事づくりに活用しましょう。
また、冷凍保存した野菜を使って栄養バランスの整った食事をつくりたいと考えている方には、「未来献立®」がおすすめです。「未来献立®」は、栄養バランスの整った献立を最大8日間分まとめて提案する、無料で使える献立提案サービスです。気になる方は、以下から詳細をご確認ください。
野菜を冷凍保存するメリット・デメリット
野菜を冷凍すると、常温や冷蔵で保存する場合に比べて保存期間が延びます。そのため、食材を無駄にせずに済み、食費の節約にも役立ちます。様々な野菜をストックしておけば、レシピの幅も広がるでしょう。
また、時短調理が可能になる点も大きなメリットです。冷凍する前に、「洗う」「切る」などの下ごしらえをまとめて済ませるため、調理するたびの手間が無くなります。
さらに、野菜は冷凍すると細胞が破壊されるため、解凍時に柔らかくなり調理の際に味がしみやすくなります。野菜から出る水分の浸透圧によって、調味料がしみておいしくなる仕組みです。元々硬めの野菜も冷凍保存することで柔らかくなるため、スープや煮物などの煮込み料理も短時間で簡単につくれます。
ただし、冷凍・解凍によって野菜が柔らかくなる点はメリットである反面、デメリットになる場合もあります。食感が変わりおいしさが損なわれる野菜もあるため、冷凍保存の向き不向きを正確に知っておきましょう。
冷凍保存に向く野菜・不向きな野菜とは
野菜の中には冷凍保存に向かないものもあります。以下では、冷凍保存できる野菜と冷凍保存に不向きな野菜の種類・特徴を紹介します。
冷凍できる野菜の特徴
葉物野菜(ほうれん草、小松菜、白菜など)、ブロッコリー、きのこ類などは、冷凍しても色や食感の変化が少ないため、冷凍保存に適しています。きのこ類は、冷凍によって旨味が増すというメリットもあります。
また、根菜類(大根、人参など)や玉ねぎなど、主に煮込みを中心とした加熱調理に用いる野菜は、冷凍保存することで味が染み込みやすくなり時短調理に役立ちます。
ただし、根菜類は冷凍により食感が変わりやすい野菜でもあるため、注意が必要です。冷凍保存に適しているものの食感が変わりやすい野菜は、下処理(切り方)や調理方法を工夫し食感の変化をカバーすると良いでしょう。
冷凍に不向きな野菜の特徴
サラダなど生野菜として食べる、水分の多い野菜は冷凍保存には向きません。解凍時に水分が多く出てしまうため、食感や味の変化が大きく、おいしく食べられない状態になってしまいます。水分量の多い野菜には、レタス、きゅうり、トマトなどが該当します。
ただし、解凍後の調理方法によっては冷凍可能な野菜もあります。その一例がトマトです。冷凍したトマトは生食には不向きですが、加熱調理には適しています。解凍後にソースや煮込み料理をつくる場合は冷凍保存しても良いでしょう。
また、芋類(じゃがいも、さつまいもなど)は、冷凍するとボソボソとした乾燥感のある食感になってしまうため、冷凍には不向きです。ただし、こちらも煮込み料理に使う場合や、加熱してマッシュポテトの状態で保存する場合は冷凍可能です。
このように、冷凍に不向きな野菜でも冷凍前の下処理や解凍後の調理法によって、おいしく保存できる場合もあります。
野菜をおいしく冷凍保存する方法とコツ

野菜によって適切な冷凍保存方法は異なりますが、基本の手順は共通です。
野菜を冷凍保存する際は、基本的に以下の手順で保存します。
- 野菜にあわせた下処理を行い(洗う・切る・加熱するなど)水分をキッチンペーパーなどで取る
- 保存容器に入れて、できるだけ平らにしてから空気を抜き密閉する
- 冷凍庫に入れる(アルミやステンレスバットに載せて冷凍すると尚良い)
下処理の方法は野菜によって異なるものの、基本的には用途にあわせて行う方法がおすすめです。みじん切りやいちょう切りなど、様々な切り方でカットしてストックしておけば、料理にあわせてすぐに調理できます。
また、小分けにして冷凍する方法もおすすめです。一度にたくさん使わない野菜は、1回分ずつの量に小分けして保存袋に入れておくと良いでしょう。
なお、冷凍保存の際は、できるだけ早く凍らせることが品質維持のポイントです。急速冷凍室を使用したりアルミトレイに乗せて冷凍したりすると、熱伝導が早く冷凍時間が短縮できるため、よりおいしい状態で冷凍保存できます。
冷凍保存に使う容器は?
野菜の冷凍保存には、冷凍用保存袋(フリーザーバッグ)、冷凍保存対応の蓋付き容器などが使えますが、必ず冷凍対応のものを選びましょう。
保存袋を使う場合は、野菜を入れて空気を抜き、なるべく平らにするとコンパクトに保存できます。薄型で保存できるため、冷凍時間の短縮にもつながります。
蓋付き容器の場合は、食材が潰れにくく、製品によってはそのまま調理・食器として使えます。
冷凍しやすい点では保存袋がおすすめですが、それぞれメリットが異なるため、それぞれ好みや使いやすさで選びましょう。
冷凍保存期間の目安は?
冷凍した野菜の保存期間は、3週間程度が目安です。
ただし、一般家庭の冷凍庫は業務用と比べて庫内温度が高く設定されているため、できるだけ早く使い切ることを意識できると良いでしょう。
【野菜別】適切な冷凍方法とおすすめの使い方
野菜を上手に冷凍保存するには、野菜にあわせて適切な方法を選ぶのがポイントです。使いやすさや調理のしやすさを考慮した上で冷凍保存すれば、様々な料理に活用できます。
以下では、代表的な野菜の冷凍方法をおすすめの使い方とともに紹介します。
なお、「未来献立®」では、プロ監修の栄養バランスが整った献立を楽しみながらつくることができます。野菜をたっぷり使ったサラダやおかずレシピをはじめ、簡単に調理できるメニューを多数揃えているため、冷凍した野菜を調理する際は、ぜひ活用してみてください。
玉ねぎ
玉ねぎは、メニューにあわせて薄切りやみじん切りにして冷凍するとすぐに使えて便利です。薄切りはスープや炒め物に、みじん切りは肉団子の具などに使えます。切ったものは1回分ずつラップなどで小分けにし、冷凍用保存袋で冷凍しましょう。
また、生のまま冷凍する以外に、みじん切りしたものを炒めて冷凍しておくのもおすすめです。ハンバーグやカレーなどにそのまま使えるため、時短調理に役立ちます。
小松菜・ほうれん草などの葉物野菜
小松菜やほうれん草などの葉物野菜は、生のまま、または下茹でしてから冷凍しましょう。ほうれん草などアクが気になる野菜は下茹でしておくと、解凍後そのまま調理できます。茹でた場合は粗熱を取り、水気を絞ってから冷凍するのがポイントです。
いずれの場合も、根の部分を切り落とし、ざく切りにしたものを小分けにして冷凍しておくのがおすすめです。生ものは炒め物やスープなどの加熱調理に、下茹でしたものはお浸しやナムルに使えます。
キャベツ
キャベツは、生のままざく切りや細切りにして、保存袋に入れて冷凍しておくのが良いでしょう。水分が抜け塩もみしたような状態になり、和え物などに使いやすくなります。また、焼きそばの具やスープ、炒め物などの加熱調理では、凍ったまま調理できます。
なお、軽く茹でてから冷凍すると、ボリュームが減りコンパクトに保存できます。下茹でした場合の冷凍キャベツは炒め物に不向きですが、和え物や餃子の具などに使うと良いでしょう。
ブロッコリー
ブロッコリーは、小房に分けて、生のままか硬めに茹でてから冷凍しましょう。茹でた場合は粗熱を取り、水気をよく切ってから保存袋に入れて冷凍します。
冷凍したブロッコリーは花蕾の部分が崩れやすいため、ラップで小分けにして容器に入れるのがおすすめです。
なお、凍ったままでソテーや蒸し物、煮込み料理に使えます。
人参
人参は、メニューにあわせて薄切り、いちょう切り、細切りなど様々な切り方で生のまま冷凍しておくのがおすすめです。切って保存することで厚みが減り、食感の変化(筋っぽさ)も気になりづらくなります。
そのまま保存袋に入れて平らな状態で冷凍し、調理する際は、使う分だけ折って取り出すと便利です。または、小分けにしたものをラップで包んでから保存袋に入れても良いでしょう。きんぴらなどの炒め物、スープなどの煮込み料理には凍ったまま使えます。
大根
大根は、根の部分をいちょう切りや短冊切りなどに切ってから、生のまま保存袋に入れて冷凍するのがおすすめです。炒め物、汁物、煮込み料理など多様なメニューに使えます。また、大根は味がしみやすいため、厚めの輪切り状態で冷凍し、そのまま煮物に使うのも良いでしょう。
なお、すりおろしてラップで小分けにし、袋や容器に入れて冷凍保存すれば、自然解凍後大根おろしとして生食もでき、みぞれ和えなどの加熱調理にも使用できます。
大根の葉は刻んで塩もみし、水気を絞った状態での冷凍保存がおすすめです。
ピーマン
ピーマンは、ヘタ・種・ワタを取り除き、使いやすい大きさにカットして保存袋に入れて冷凍します。種やワタにも栄養が含まれますが、時間が経つと酸化してしまい長期保存には不向きなため、あらかじめ取り除いておきましょう。
ピーマンは凍ったまま加熱調理に使用できます。火がとおりやすいため、炒め物はサッと加熱する程度にしましょう。
冷凍時は生のまま冷凍するのが基本ですが、サッと火を通してから冷凍すれば、解凍後サラダや付け合わせの野菜として、そのまま食べることもできます。
トマト・ミニトマト
トマトは、ヘタを取り除いてざく切り、または丸ごとそのままで保存袋に入れて冷凍しましょう。丸ごとの状態で冷凍すると、凍ったトマトを水に浸けるだけでツルンと皮が剝がれ、簡単に剥けるようになります。
調理する際は、凍ったまま加熱しスープや煮込み料理にすると良いでしょう。すりおろして加熱すると、トマトソースも簡単につくれます。
もやし
もやしは、洗ってざるなどで水気をよく切ってから保存袋に入れ、生のまま平らな形で冷凍しましょう。冷凍したもやしは、あんかけの具材やスープなどに使うのがおすすめです。
もやしは傷みやすい野菜のため、使い切れない場合は早めに冷凍保存すると良いでしょう。
きのこ
きのこは、石突きを切り落とし、ほぐす・切るなど使いやすい大きさにしてから保存袋に入れて冷凍します。しめじ・舞茸・えのき・株なめこは、ほぐして1本ずつか小房に分けておくようにしましょう。脱気パック入りなめこ(加工品)は、パックのまま冷凍できます。エリンギ・マッシュルーム・しいたけは、使いやすい厚さや長さにカットしてください。
様々なきのこをミックスした状態で冷凍保存するのも便利です。いずれも、炒め物やスープ、煮物、蒸し物など、加熱調理して食べるようにしましょう。
じゃがいも・さつまいも
じゃがいもやさつまいもなどの芋類は、冷凍すると食感が悪くなってしまうため、本来は冷凍に不向きな野菜ですが工夫すれば冷凍保存も可能です。冷凍する際は、食感の変化を抑えるために加熱してから冷凍しましょう。
食べやすい大きさにカットして、茹でるか電子レンジで加熱し、粗熱を取り保存袋で冷凍します。マッシュポテトの状態にしてから冷凍保存する方法もおすすめです。
冷凍保存した野菜をおいしく解凍するコツ
冷凍保存した野菜は、凍ったまま加熱調理するのが基本です。そのまま炒めれば、余分な水分を飛ばしながら解凍できます。また、火がとおりやすい状態になっているため、煮込み料理にも適しています。
加熱処理後に冷凍した場合は、流水解凍すると良いでしょう。ボウルやバットに水を張り、保存容器(袋)ごと野菜を入れて水道水にさらしてください。自然解凍より解凍時間が短縮され、水分の流出も防げます。
冷凍保存した野菜のレシピや調理方法に迷ったら「未来献立®」を活用しよう
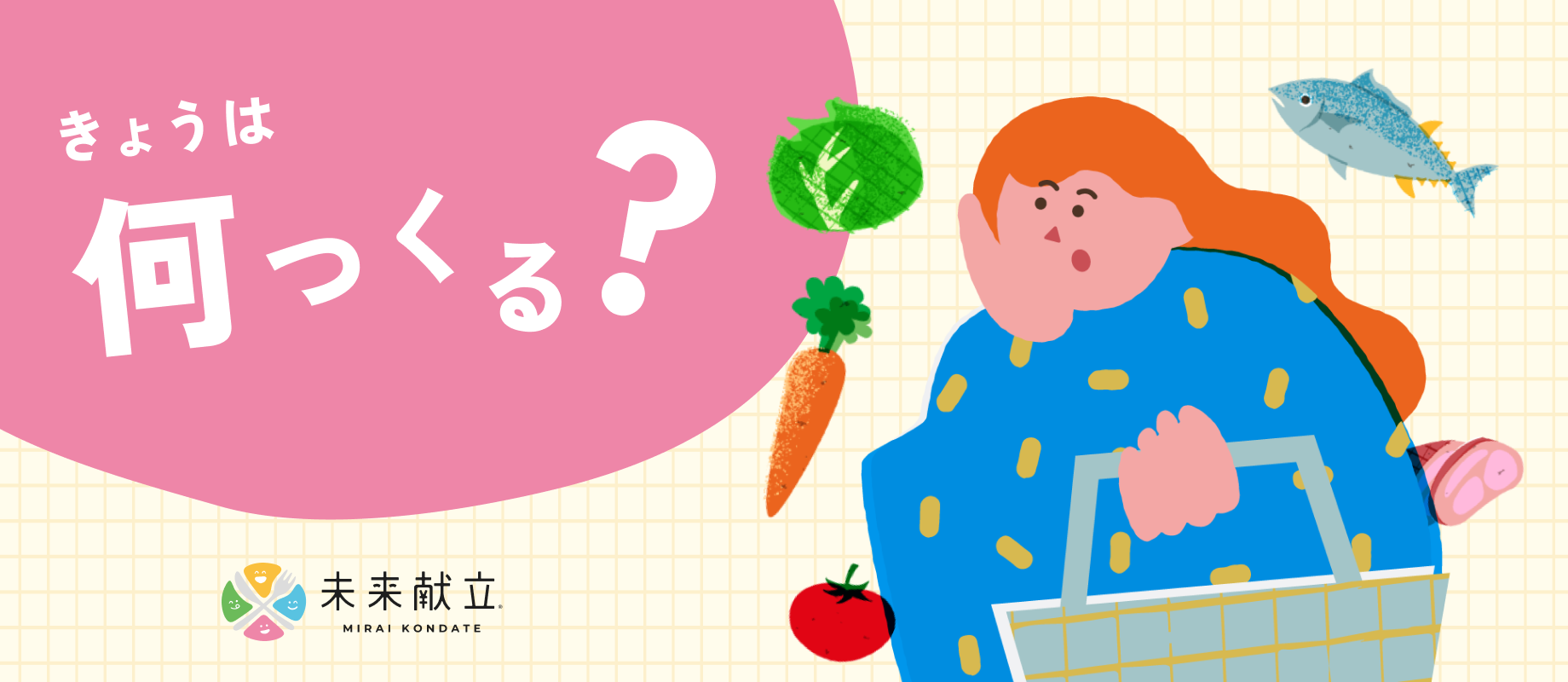
冷凍野菜のストックができれば、料理のバリエーションも広がります。しかし、毎日献立を考えるのは難しく感じる方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、具体的にどんな食事にすればいいの?」と悩む方は、献立提案サービス「未来献立®」を試してみてください。特徴は以下のとおりです。
「未来献立®」の特徴
- 自分の食生活に合わせて栄養バランスが整った「ゴールデン献立」ができる
- 簡単な操作で最大8日間分まとめて登録でき、登録・利用ともに無料
- 昨日偏った栄養バランスを整える、便利な「ツジツマ献立」機能あり
- 一部のメニューを差し替えて自分好みの献立にカスタマイズできる
- お気に入りの献立・苦手な食材を登録できる
- レシピのアレンジ・分量などもメモできる
「未来献立®」を使えば、プロ監修の栄養バランスが整った「ゴールデン献立」を楽しみながらつくることができます。まとめて30分前後で完成する献立は、簡単につくれるメニューが多く、時間がない日の食事づくりに役立ちます。
また、外食などで偏った栄養バランスとツジツマを合わせて次の献立をご提案する「ツジツマ献立」機能で、誰でも簡単に栄養バランスを整えることが可能です。
冷凍保存した野菜を活用しながら、おいしく栄養バランスの良い献立をもっと気軽に実現したい方は、ぜひ「未来献立®」を活用してみてください。
最適な方法で野菜を冷凍保存して毎日の食事づくりに役立てよう
野菜を冷凍保存すると、長持ちさせられるだけでなく毎日の食事づくりが楽になります。冷凍した野菜は3週間程度を目安に保存できますが、鮮度が落ちないうちに早めに使い切りましょう。
また、野菜は冷凍保存に向くものと不向きなものに分けられますが、工夫すれば不向きでも冷凍できる野菜もあります。それぞれの野菜の特徴や用途に合わせた方法で冷凍することが大切です。
様々な野菜をストックしておくと、献立のバリエーションも広がりやすくなります。なお、冷凍保存した野菜を使ってバランスの良い食生活を送りたいと考えているものの、毎日献立を考えるのは大変という場合は、「未来献立®」の利用を検討してみてください。栄養バランスのとれた献立を無料でご提案します。

監修者
金丸 利恵(かなまる りえ)
おうちごはん研究家、管理栄養士、分子栄養学カウンセラー
大手企業での栄養士業務、レシピ開発を担当。保健指導では2000名以上の食事指導を行う。その後独立し、料理教室を主宰し、食育やダイエットサポートなどあらゆる世代の食と健康に関わる。「食べることは、生きること」をモットーに、栄養指導やセミナーを通じて、食と栄養の大切さを伝えている。スーパーで買える身近な食材で、健康的に美味しく簡単に作れるレシピに定評がある。
 献立提案サービス
献立提案サービス