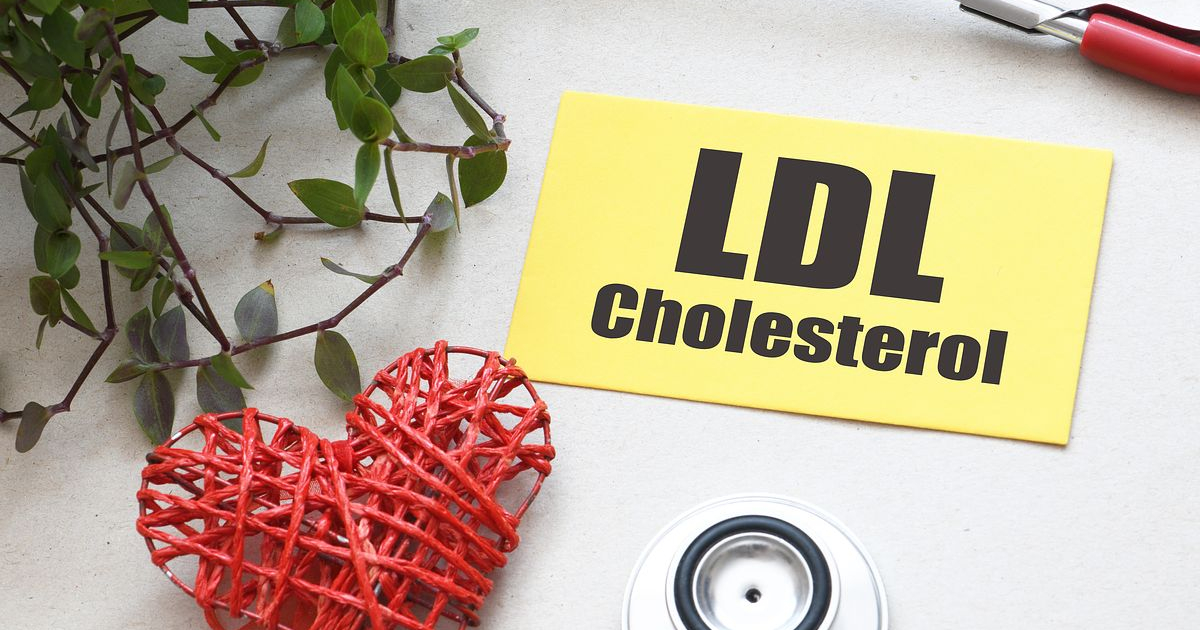BMIとは?定義や計算方法、数値を下げる食事のポイントをわかりやすく解説

BMIという言葉は聞いたことがあるものの、定義や具体的な活用方法がわからない方もいるのではないでしょうか。
BMIは肥満度を判定するもので、健康状態を判断する上での指標になります。BMIの数値が基準値を大きく外れた場合には、生活習慣の見直しが必要です。
この記事では、BMIの定義と判定方法や、BMIの数値が基準値を大きく外れた時の対処法を解説します。
また、BMIをきちんと管理するために栄養バランスの整った食事をしたいと考えている方には、「未来献立®」がおすすめです。「未来献立®」は、栄養バランスの整った献立を最大8日間分まとめて提案する、無料で使える献立提案サービスです。気になる方は、以下から詳細をご確認ください。
BMIとは
BMIとは、肥満や低体重(痩せ型)の判定などに用いられる国際的な指標です。ボディ・マス指数とも呼ばれ、「体重(kg)÷身長(m)の2乗」で算出されます。BMIでは筋肉や脂肪の量を考慮していないため、体脂肪率とは異なります。
体脂肪率は、体重に占める体脂肪の比率を示すもので、「脂肪の重量(kg)÷体重(kg)×100(%)」で算出されます。
BMIは、体脂肪率が低く筋肉量が多い筋肉質の方の場合でも、数値が高くなる点が特徴です。
体重と身長を用いたBMIの計算方法
前述のとおり、BMIは体重と身長の数値から計算できます。計算式は以下のとおりです。
体重(kg)÷身長(m)の2乗
例えば、身長170cm、体重60kgの場合、BMIは以下のように計算されます。
60(kg)÷(1.70(m)×1.70(m))=BMI値20.8(小数点以下四捨五入)
身長の単位をcmのまま計算すると正しい値にならないため、必ずmに換算してから計算しましょう。
世界・日本での肥満の判定基準
BMIの数値を元に肥満や痩せ型が判定されますが、BMIの判定基準は国によって異なります。
WHOの基準ではBMI30以上が肥満とされています。他方、日本人は欧米人に比べてBMIが平均的に低く、日本肥満学会の基準ではBMI25以上を肥満と判定します。
日本における詳細な判定基準は以下のとおりです。
| BMI値 | 体型分類(日本基準) |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5以上〜25未満 | 普通体重 |
| 25以上〜30未満 | 肥満(1度) |
| 30以上〜35未満 | 肥満(2度) |
| 35以上〜40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
BMI上の肥満と肥満症は異なる
BMI上の「肥満」とは、単に太った状態をさす言葉であり、病気ではありません。ただし、肥満に伴う合併症を患っている場合や、病気になるリスクが高い場合は「肥満症」と診断されます。
肥満症の基準は、BMI25以上に加えて、以下のどちらかに当てはまることです。
- 腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上であること
-
以下の11種の病気の中からひとつ以上当てはまる
- 耐糖能障害
- 脂質異常症
- 高血圧
- 高尿酸血症・痛風
- 冠動脈疾患(心筋梗塞・狭心症)
- 脳梗塞(脳血栓症・一過性脳虚血発作(TIA))
- 脂肪肝(非アルコール性脂肪性肝疾患/NAFLD)
- 月経異常・不妊
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)・肥満低換気症候群
- 運動器疾患(変形性関節症(膝・股関節)・変形性脊椎症・手指の変形性関節症)
- 肥満関連腎臓病
また、肥満症と似た病態としてメタボリックシンドロームがありますが、その判定基準にはBMIを用いません。
腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上あり、「血圧・空腹時血糖値・中性脂肪」の数値が2つ以上基準値を外れた場合にメタボリックシンドロームと診断されます。予備軍を拾い上げる観点から、特定健診・特定保健指導の基準のひとつとしてBMIが用いられることはあります。
太りすぎや痩せすぎによる健康上のリスク

太りすぎや痩せすぎの場合、どちらも健康上のリスクがあります。BMI数値では22程度が標準体型であり、目指したい数値です。
以下では、BMI25以上(太りすぎ)や、BMI18.5未満(痩せすぎ)による健康上のリスクを紹介します。
太りすぎによるリスク
太りすぎている場合、例えば以下の病気の発症リスクが高まるとされています。
- 糖尿病
- 高血圧
- 脂質異常症 など
また、女性特有のリスクとして排卵障害や卵巣機能の低下、乳がんリスクの上昇も挙げられます。
痩せすぎによるリスク
痩せすぎている場合、例えば以下のリスクが上がるとされています。
- 栄養不良
- 骨密度の低下
- 貧血
- 体の冷え など
また、太りすぎている場合と同様に、女性特有のリスクがあることも懸念点です。具体的には、子宮内膜症や不妊症、卵巣機能の低下、低出生体重児の出産などが挙げられます。
BMIが痩せの判定でも隠れ肥満に注意
BMIの数字が低く、痩せ型と判定されても「隠れ肥満」の状態になっている場合があります。特に筋肉量が少ない場合は、痩せ体型でも生活習慣病のリスクが上がります。
実際に、痩せ体型の方の糖尿病発症リスクは普通体重の2倍という報告もあります。若い女性のうち、3〜4割が隠れ肥満と報告された研究もあり、注意が必要です。
隠れ肥満は生活習慣病だけでなく、身体機能の低下を引き起こすこともあります。
隠れ肥満は間違ったダイエットが原因の可能性がある
隠れ肥満の原因のひとつと考えられているのは、間違ったダイエットです。食事が少なすぎたり、間食が多すぎたりなどの、食事内容の影響が大きいといわれています。
不規則な時間の食事も隠れ肥満のリスクを高めるため、避けたほうが良いでしょう。これら食事面の要因に加えて、隠れ肥満の方は運動量が少ないという傾向もあります。
痩せていても筋肉量が少ない自覚がある場合は、食生活の見直しや運動など、生活習慣を見直す必要があります。
なお、食生活を見直して栄養バランスが整った食事を心がけたい場合は、無料の献立提案サービス「未来献立®」をぜひご活用ください。
肥満や隠れ肥満を抜け出す運動のポイント

BMIは22が適正値とされます。もしBMIが高すぎる場合、カロリーをコントロールして体重を落としていくことが大切です。
体重を落とすには、摂取カロリーよりも消費カロリーが大きい状態を目指す必要があります。消費カロリーを増やすには、体を動かす機会を増やしましょう。
体重を減らす運動は、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を中心に取り組むのがおすすめです。運動習慣がない方は、階段を使ったりいつもより多く歩いたりする方法からはじめると、継続しやすいでしょう。
有酸素運動の前には怪我防止のためにストレッチを行い、急な運動は避けましょう。また、必要に応じて筋トレやヨガを取り入れるのも効果的です。
なお、BMIが高いからといって、急激に体重を落とすのはおすすめしません。リバウンドのリスクを避けるため、1ヶ月あたり現体重の3~10%のペースで体重を落とせるように調整しましょう。
ダイエットのポイントについては以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
肥満や隠れ肥満を抜け出す食生活のポイント
摂取カロリーよりも消費カロリーが多い状態を目指すには、運動に加えて食生活の見直しも重要です。摂取カロリーを調整すると、体重の減少につながります。
肥満や隠れ肥満の可能性がある方に向けて、食生活で意識したいポイントを解説します。
- 1日3食を規則正しい時間に食べる
- バランスよく栄養を摂取する
- ゆっくり食べる
- 間食を減らす
なお、栄養バランスが整った食事のためには、自分の食生活に合わせた献立がつくれる「未来献立®」をぜひご活用ください。プロ監修の献立を、最大8日間分まとめてご提案します。
ダイエット中の食事のポイントについては以下の記事でも詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
1日3食を規則正しい時間に食べる
毎日同じ時間に食事を摂ると血糖値の急上昇を抑えられるため、可能な限り決めた時間を意識してみましょう。
加えて、1日3食しっかり食べることも大切です。朝食を食べないとリズムが崩れる他、空腹の時間が長くなると脂肪が蓄積されやすくなってしまいます。
バランス良く栄養を摂取する
主食だけを食べる単品の食事は炭水化物の割合が多くなり、たんぱく質やビタミンの不足につながります。一食で主食、副菜、野菜を摂取できると、栄養バランスが整いやすくなります。
特に野菜や海藻類は不足しやすいため、1日トータルで350gの摂取になるよう、毎食取り入れることをおすすめします。また、油の取りすぎにも注意しましょう。
栄養バランスについては以下の記事でも詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
ゆっくり食べる
ゆっくり食べるように意識することも、カロリーコントロールに有効です。
食事の開始から満腹だと感じるまでには、15~20分程度かかるとされています。早食いは満腹を感じにくく、食べすぎて太る原因になるため、ゆっくり食事することを意識しましょう。
よく噛んで時間をかけると食べる量を減らせるため、自然とカロリーを抑えやすくなります。一口あたり30回を目安として噛むことを目標にしましょう。
間食を減らす
間食を毎日食べることが習慣になっている場合は、できる限り3食の食事のみにするよう意識しましょう。
間食を食べたい場合は、「間食は日々のご褒美」という位置付けで、回数・頻度を制限して取り入れると良いでしょう。
なお、間食の目安は1日あたり200kcal以下です。カルシウムが足りないならチーズを食べるなど、食事だけでは足りない栄養素を摂取できる内容にすると、栄養バランスが整います。
栄養バランスが整った献立を考えるなら「未来献立®」がおすすめ
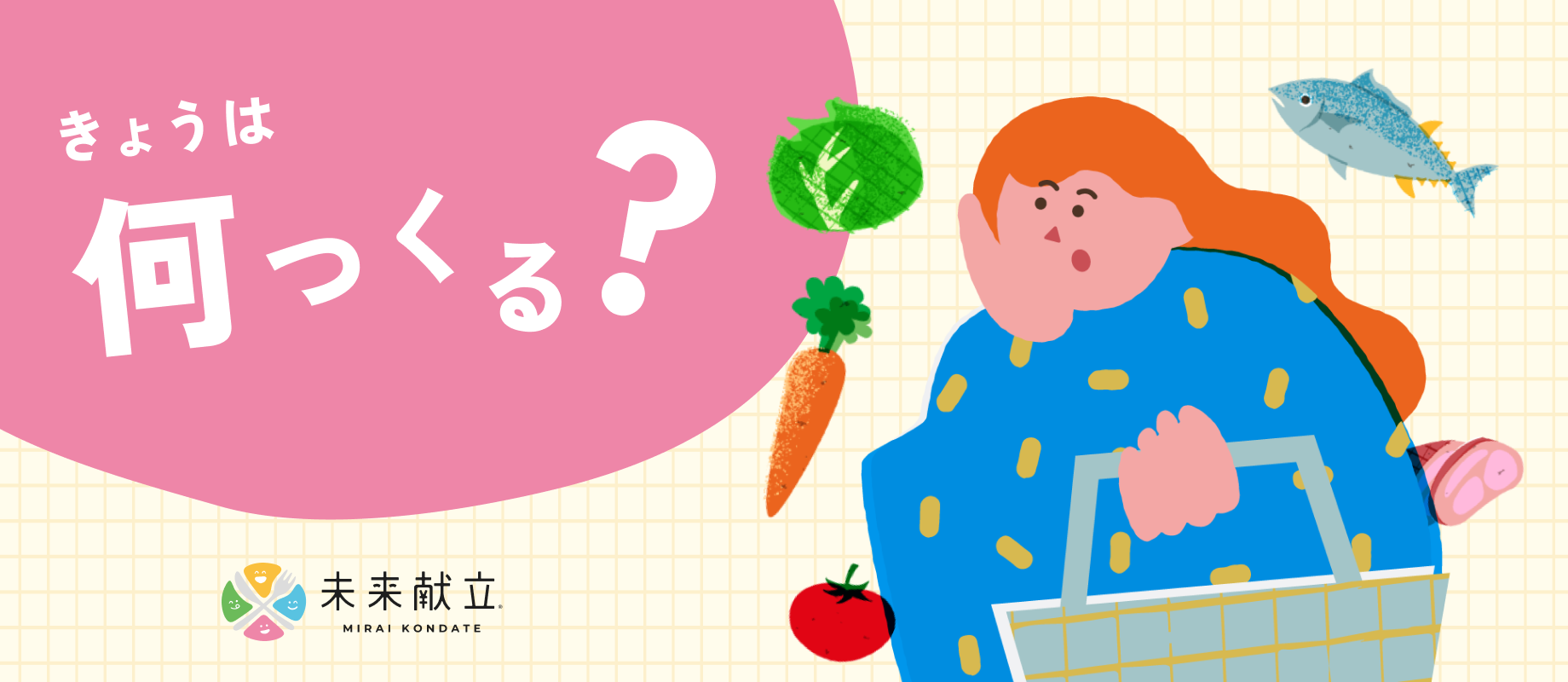
ここまで読んで、BMIを適正値に近づけたいと考え、食生活を改善したいと思ったものの、一食一食栄養バランスをちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
しかし、【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、具体的にどんな食事にすればいいの?」と悩む方は、献立提案サービス「未来献立®」を試してみてください。特徴は以下のとおりです。
「未来献立®」の特徴
- 自分の食生活に合わせて栄養バランスが整った「ゴールデン献立」ができる
- 簡単な操作で最大8日間分まとめて登録でき、登録・利用ともに無料
- 昨日偏った栄養バランスを整える、便利な「ツジツマ献立」機能あり
- 一部のメニューを差し替えて自分好みの献立にカスタマイズできる
- お気に入りの献立・苦手な食材を登録できる
- レシピのアレンジ・分量などもメモできる
「未来献立®」を使えば、プロ監修の栄養バランスが整った「ゴールデン献立」を楽しみながらつくることができます。まとめて30分前後で完成する献立は、簡単につくれるメニューが多く、時間がない日の食事づくりに役立ちます。
また、外食などで偏った栄養バランスとツジツマを合わせて次の献立をご提案する「ツジツマ献立」機能で、誰でも簡単に栄養バランスを整えることが可能です。
おいしさと栄養バランスを両立した食事でBMIをきちんと管理したい方は、ぜひ「未来献立®」を活用してみてください。
BMIを把握して健康的な食生活を意識しよう
BMIは体格を判定する指標であり、健康管理のひとつのバラメーターになります。身長と体重の数値があれば求められるため、まずはBMIを計算してご自身の体型を判定してみましょう。
BMIが高く肥満が気になる場合は、運動を取り入れたり食習慣を見直したりして、体重をコントロールすることをおすすめします。
食生活を改善したいと考えているものの、栄養バランスに配慮した献立を毎日考えるのは大変という場合は、「未来献立®」の利用を検討してみてください。栄養バランスのとれた献立を無料でご提案します。

監修者
伊藤 まゆ(いとう まゆ)
M’sクリニック南麻布 院長、日本抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医
本当の美とは、心と体の健康あってこそ、という観点から、2007年開院時より、内外美容医療を提唱、実践。栄養学、予防医学、エイジングケア、美容について、多様な経験と多角的視点で取り組み、幅広い世代のサポートを行っている。
 献立提案サービス
献立提案サービス