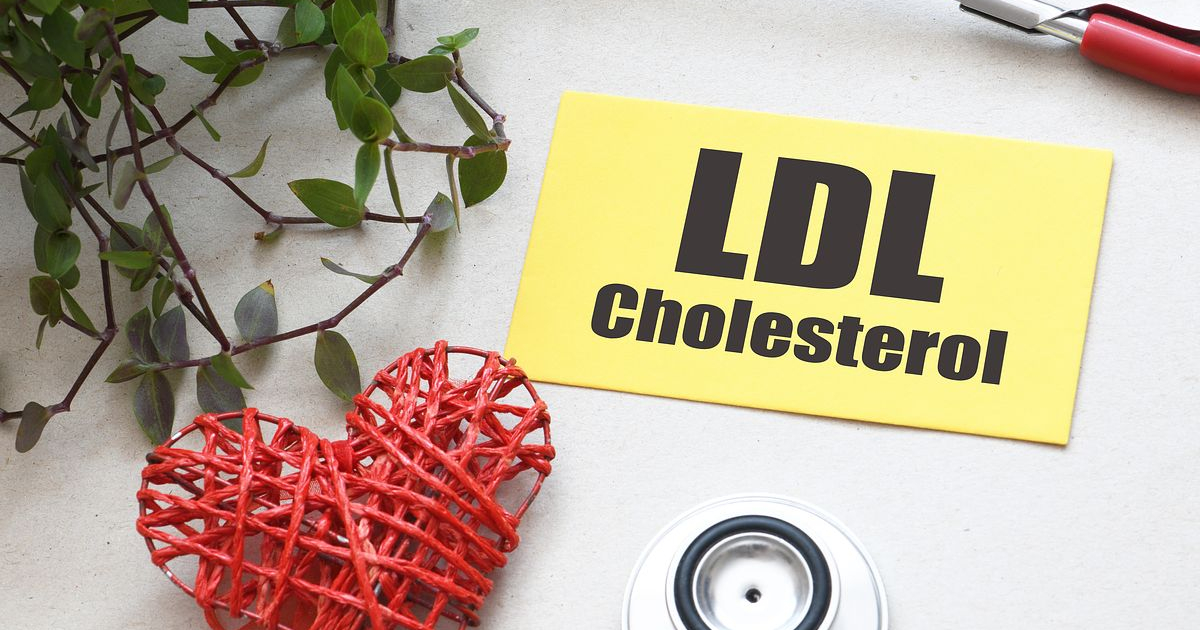ひな祭りの伝統的な食べ物・お菓子とは?由来や簡単レシピも紹介

3月3日のひな祭りには、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物、菱餅や桜餅など、古くから伝わる伝統的な食べ物を用意する風習があります。
これらの料理やお菓子には、女の子の健やかな成長と幸せを願う深い意味が込められており、地域によって独自の特徴や食べ方の違いも見られます。また、子ども向けの甘酒や大人向けの白酒など、祝いの席にふさわしい飲み物も欠かせません。
この記事では、ひな祭りの定番メニューに込められた由来や意味を紐解きながら、ご家庭で手軽につくれる具体的なレシピまでご紹介していきます。
ひな祭り定番の食べ物

毎年3月3日の桃の節句は、女の子の健やかな成長を願う日本の伝統行事として親しまれています。中国の「上巳の節句」を起源とし、平安時代の「雛遊び」の文化が江戸時代に広く定着したことで、現在のひな祭りの形となりました。この特別な日には、子どもたちの幸せを願う様々な伝統的な食べ物が食卓を彩ります。
特に代表的な料理として知られるちらし寿司は、「寿を司る」縁起物として、はまぐりのお吸い物は、「生涯の良き縁を願う象徴」としてなど、それぞれ大切な意味を持って親しまれてきました。
ちらし寿司
ひな祭りの定番の食べ物として、真っ先に挙げられるのはちらし寿司です。
「寿を司る」と書く寿司は、元来から祝いの席で好んで振る舞われてきました。なかでもちらし寿司は、華やかな見た目と豊富な具材で、女の子の健やかな成長を願う桃の節句にふさわしい料理として親しまれています。
江戸時代に祝いの席の定番となり、大正時代以降にひな祭りの代表的な料理として定着したとされています。色とりどりの具材が春の訪れを感じさせる、めでたい席にぴったりの一品です。
はまぐりのお吸い物
ひな祭りの定番料理として、はまぐりのお吸い物も欠かせません。
はまぐりの貝殻は、対になる貝殻同士が完璧にぴったりと合いますが、他の貝とは決して合わない特徴があります。この性質から「一生一人の伴侶と添い遂げる」という願いが込められた食材として親しまれ、縁結びのシンボルとしての歴史を刻んできました。
はまぐりは、平安時代「貝合わせ」遊びにも使われ、江戸時代には婚礼道具として重宝されるようになりました。お吸い物をつくる時には、より一層の幸せを願う意味が込めて、貝殻ひとつに二つの身を入れる風習があります。
ひな祭り定番のお菓子
ひな祭りの食卓を彩るお菓子には、菱餅、桜餅、ひなあられなど、長い歴史を持つ伝統的な和菓子が欠かせません。
これらの甘いお菓子は子どもたちに親しまれ、それぞれに込められた願いや地域ごとの独自の特徴を持ちながら、今日まで大切に受け継がれています。
菱餅
ひな祭りを彩る伝統的なお菓子のひとつが菱餅です。その起源は中国の上巳節にまで遡ります。当初は母子草を混ぜた餅として伝来しましたが、日本では「母と子をつく」ことを縁起担ぎから避け、代わりに春の薬草である蓬(よもぎ)を使用するようになったとされています。
江戸時代に現在のひし形の形が定着し、明治時代には緑・白・赤の3色が完成しました。緑は厄除け、白は子孫繁栄、赤は魔除けを表すとともに、この色合いには春の情景も表現されています。
桜餅
ひな祭りの定番和菓子として親しまれている桜餅には、実は特別な由来はありません。ピンク色の春らしい色合いや、菱餅の代替として食べやすいことから、ひな祭りの定番菓子として定着したとされています。
桜餅には、関東の「長命寺」と関西の「道明寺」という代表的な2種類があります。関東の長命寺は江戸時代に向島のお寺で生まれた薄皮タイプ、関西の道明寺は道明寺粉を使用したつぶつぶした食感が特徴的で、それぞれに異なる魅力があります。
どちらも塩漬けにした桜の葉で包まれ、春の訪れを感じさせる季節の和菓子として愛されています。
ひなあられ
ひなあられは、ひな祭りに欠かせない伝統的なお菓子のひとつです。ピンク・黄・緑・白の4色で春夏秋冬を表現し、一年を通じた子どもの健やかな成長を願う意味が込められています。
明治時代以降に広く普及したとされ、ひし餅を砕いて煎ったおかきが始まりとする説などがあります。地域によって特徴が異なり、関東では砂糖がけの甘い味わい、名古屋では円柱形という独特の形状、関西では塩味が特徴的です。
ひな祭りの食べ物と一緒に楽しむ飲み物
一般的にひな祭りの席には、ノンアルコールの甘酒と大人向けの白酒という、2つの伝統的な飲み物が用意されます。中国の桃花酒がルーツとされ、時代とともに日本独自の発展を遂げながら、祝いの席にふさわしい縁起物として親しまれています。
甘酒
ひな祭りの祝いの飲み物として親しまれている甘酒は、子どもも楽しめる飲み物として定着してきました。甘酒には、酒粕からつくるものと米麹からつくるものの2種類がありますが、ノンアルコールは米麹からつくる甘酒のみです。
もともとは桃の花びらを浸した桃花酒を飲む風習があり、それが江戸時代に白酒へと変化し、子どもたちも楽しめる甘酒が生まれたとされています。
白酒
白酒は、みりんと米麹を使用してつくられる白く濁った甘みのある酒です。アルコール度数9〜10%のリキュール類に分類され、とろみのある独特な口当たりが特徴です。
起源は中国の「上巳の節句」で飲まれていた桃花酒に遡り、桃の花を美しく引き立てる白酒が好まれるようになったことから、現在の形へと発展したとされています。無病息災と厄除けを願う飲み物として江戸時代から親しまれ、現代まで受け継がれてきました。
甘酒と混同されやすいですが、未成年者は飲むことができないので注意が必要です。
ひな祭りにおすすめのレシピ〜ちらし寿司〜
ひな祭りの定番メニューであるちらし寿司は、見た目の華やかさが特徴です。
「AJINOMOTO PARK」で紹介しているレシピの中から、基本の五目ちらし寿司から春らしい具材を使ったアレンジレシピまで3つのレシピをご紹介します。子どもから大人まで楽しめる味付けの、ひな祭りメニューです。
五目ちらしずし

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
ひな祭りの定番として人気の高いレシピです。れんこん、にんじん、しいたけ、油揚げなどの具材を和風だしの素で優しく味付けし、錦糸卵と絹さやで華やかに仕上げます。調理時間30分程度で、お祝いの席にふさわしい彩り豊かな一品です。
調理時間の目安:30分 ※時間外を除く
材料<4人分>
- 米:2・1/2(400g)
- 水:450ml
- 【A】酢:大さじ4
- 【A】砂糖:大さじ1
- 【A】塩:小さじ1/2
- 【A】和風だしの素:小さじ1
- 油揚げ:1/2枚(10g)
- れんこん:1/2節(125g)
- にんじん:1/2本(100g)
- しいたけ:6個(60g)
- 絹さや:12枚
- 【B】水:大さじ3
- 【B】みりん:大さじ2
- 【B】砂糖:大さじ1
- 【B】塩:小さじ1/4
- 【B】和風だしの素:小さじ1/2
- 卵:1個
- サラダ油:少々
- いり白ごま:小さじ1
春の彩りちらし寿司

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
春らしい華やかさが魅力の彩りちらし寿司のレシピです。むきえびと錦糸卵、しいたけ、にんじんなどの具材をバランスよく使用し、絹さやの緑と桜の花の飾りで春らしさを演出します。
調理時間はわずか20分と手軽で、見栄えの良い本格的なちらし寿司ができ上がります。
調理時間の目安:20分
材料<2人分>
- 米:1カップ(170g)
- 水:1カップ
- 【A】酢:大さじ2
- 【A】砂糖:大さじ1・1/2
- 【A】塩:小さじ1/4
- 【A】うま味調味料:少々
- 【B】溶き卵:1個分
- 【B】酒:小さじ1
- 【B】砂糖:小さじ1
- 【B】塩:少々
- 干ししいたけ:2枚
- にんじん:30g
- 【C】水:1/4カップ
- 【C】しょうゆ:小さじ1
- 【C】酒:小さじ1
- 【C】砂糖:小さじ1
- 【C】和風だしの素:小さじ1/4
- むきえび:6尾
- 【D】酒:小さじ1
- 【D】うま味調味料:5ふり
- 酢:適量
- 絹さや:4枚
- いり白ごま:大さじ1
- 刻みのり:適量
- 桜の花の塩漬け・好みで:4本
そぼろと卵のちらし寿司

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
鶏そぼろと甘い卵の味付け、酢を控えめにした酢飯で、小さなお子様でも食べやすく仕上がるちらし寿司です。絹さやとにんじんを花型にすれば、お祝いの席にふさわしい、彩りのある一品になります。
具材がシンプルなため、苦手な食材が多いお子様も無理なく食べられます。
調理時間の目安:20分
材料<4人分>
- 炊きたてご飯:700g
- 【A】酢:大さじ2
- 【A】砂糖:大さじ1
- 【A】塩:小さじ1/2
- 【B】鶏ひき肉:120g
- 【B】酒:大さじ1
- 【B】みりん:大さじ1
- 【B】しょうゆ:大さじ1
- 【B】砂糖:大さじ1/2
- 【B】和風だしの素:4g
- 卵:2個
- 【C】砂糖:大さじ1
- 【C】塩:少々
- 絹さや:8枚
- にんじん:1/2本
- サラダ油:小さじ1
ひな祭りにおすすめレシピ〜お吸い物〜
はまぐりのお吸い物は、ひな祭りの伝統的な一品ですが、他にも手軽につくれる上品なお吸い物があります。
「AJINOMOTO PARK」で紹介しているレシピの中から、鯛、まいたけ、たらなど、素材の味を活かしたお吸い物をご紹介します。いずれもちらし寿司との相性が良く、ひな祭りの食卓を優しく彩るメニューです。
鯛のお吸い物

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
鯛の上品な旨みとゆずの香りが広がる、ひな祭りにふさわしい贅沢なお吸い物です。調理時間はわずか15分で、見た目も美しい一品に。青ねぎの彩りとゆずの香りで春らしさを演出し、ちらし寿司との相性も抜群です。
調理時間の目安:15分
材料<4人分>
- たい(切り身):2切れ(125g)
- 【A】酒:大さじ1
- 【A】塩:小さじ1/3
- 【B】水:4カップ
- 【B】酒:小さじ2
- 【B】塩:小さじ1
- 【B】和風だしの素:小さじ1・1/2
- うす口しょうゆ:小さじ1
- 青ねぎ・または長ねぎ:適量
- ゆずの皮・好みで:適量
大根とまいたけのお吸い物

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
まいたけの豊かな旨みと和風だしの素で、深い味わいのお吸い物です。大根のやさしい甘みと、三つ葉の爽やかな香りが春らしさを演出します。調理時間わずか15分で完成する、ひな祭りの食事の締めくくりにちょうど良い一品です。
調理時間の目安:15分
材料<2人分>
- 大根:4cm(100g)
- まいたけ:1/2パック(50g)
- みつば:4本
- 【A】水:240ml
- 【A】酒:大さじ1
- 【A】和風だしの素:小さじ1/2
- 【A】塩:小さじ1/4
たらと葱のお吸い物

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
たらと青ねぎでつくる優しい味わいのお吸い物です。和風だしの素を使用し、たらの旨みを引き立てながら上品に仕上げます。青ねぎの爽やかな香りと彩りが春らしさを演出し、ちらし寿司以外にも幅広い和食にあう一品です。
調理時間の目安:15分
材料<4人分>
- たら:3切れ
- 【A】和風だしの素:小さじ山盛り1
- 【A】水:3カップ
- 【A】酒:大さじ1・1/2
- 【A】塩:小さじ2/3
- しょうゆ:小さじ1
- 青ねぎ・わけぎ・九条ねぎなど:2本
ひな祭りにおすすめレシピ〜デザート〜
ひな祭りのデザートは、伝統的な和菓子から現代風のケーキまで、ご家庭でも手づくりを楽しむことができます。
「AJINOMOTO PARK」で紹介しているレシピの中から、春らしい色合いと味わいを楽しめる3つのデザートレシピをご紹介します。
桜もち

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
ひな祭りの定番和菓子を、ご家庭で手づくりできるレシピです。薄力粉と白玉粉を使用し、本格的な食感でありながら手軽につくれます。ホットプレートで生地を薄く焼き、こしあんを包んで桜の葉で巻くだけの簡単な工程です。食紅で優しいピンク色に仕上げ、桜の葉の香りとともに春の訪れを感じられるデザートです。
調理時間の目安:20分
材料<8個分>
- 薄力粉:80g
- 白玉粉:大さじ1
- 砂糖:大さじ3
- 水:120ml
- 水溶き食紅:少々
- こしあん・市販品:250g
- 桜の葉の塩漬け:8枚
ひな祭りケーキ

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
ひな祭りのお祝いにぴったりの、華やかな手づくりケーキです。ふんわりとしたスポンジ生地にたっぷりのいちごとホイップクリームを挟み、ひし形に仕上げることで、ひな祭りらしい可愛らしい見た目に。お子様と一緒につくる思い出づくりにもおすすめです。
調理時間の目安:60分
材料<6人分>
- 卵:3個
- 砂糖:70g
- 薄力粉:40g
- バター:20g
- 生クリーム:1・1/2カップ
- 砂糖:大さじ3
- いちご・ひと粒13g位のもの:45個
つぶしいちごの白玉

出典:味の素株式会社「AJINOMOTO PARK」
つぶしいちごを練り込んだピンク色の白玉と、フレッシュないちごを組み合わせた和洋折衷のデザートです。いちごの果肉を白玉粉に練り込むことで、自然な甘みと春らしい色合いになります。
お子様と一緒に手づくりを楽しめる簡単さが魅力です。ミントの葉を添えれば、見た目も華やかに仕上がります。
調理時間の目安:10分
材料<3人分>
- いちご・4~5粒:40g
- 白玉粉:40g
- 砂糖:大さじ3
- いちご・9~10粒:90g
- 砂糖:大さじ1
- ミントの葉:適量
- 牛乳:1/4カップ
ひな祭りの食べ物で伝統を楽しみながら子どもの成長を願おう
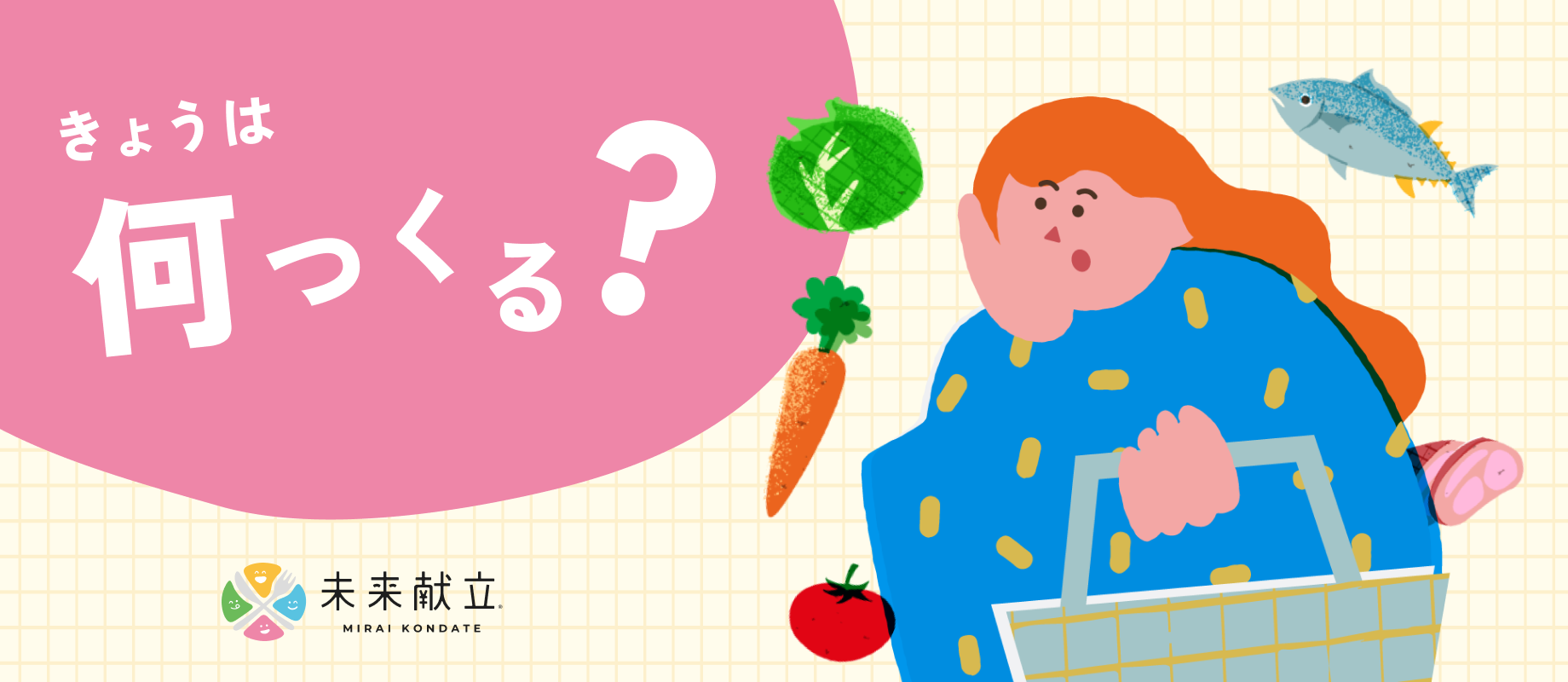
ひな祭りの食卓には、子どもたちの健やかな成長と幸せを願う意味が込められた様々な伝統的な料理が並びます。
ちらし寿司は「寿を司る」縁起物として、はまぐりのお吸い物は生涯の良き縁を願う象徴として、それぞれ大切に受け継がれてきました。菱餅には春の情景と厄除けの願いが、ひなあられには四季を通じた健康への祈りが込められています。
桜餅にみられるように、同じ食べ物でも関東と関西で異なる特徴を持つものも多く、それぞれの地域で独自の発展を遂げてきました。
現代では家庭でも手軽につくれるレシピが豊富にあるため、伝統を大切にしながらも、新しいアレンジを加えて楽しみましょう。
なお、行事ごとではつい食べ過ぎてしまうこともあるかもしれません。「未来献立®」は、前日の食事をもとに、栄養バランスを考えた「ツジツマ献立」をご提案するサービスです。食事メニューを考える手間が省けるだけでなく、より栄養バランスも整いやすくなります。詳細は以下からご確認ください。

監修者
金丸 利恵(かなまる りえ)
おうちごはん研究家、管理栄養士、分子栄養学カウンセラー
大手企業での栄養士業務、レシピ開発を担当。保健指導では2000名以上の食事指導を行う。その後独立し、料理教室を主宰し、食育やダイエットサポートなどあらゆる世代の食と健康に関わる。「食べることは、生きること」をモットーに、栄養指導やセミナーを通じて、食と栄養の大切さを伝えている。スーパーで買える身近な食材で、健康的に美味しく簡単に作れるレシピに定評がある。
 献立提案サービス
献立提案サービス