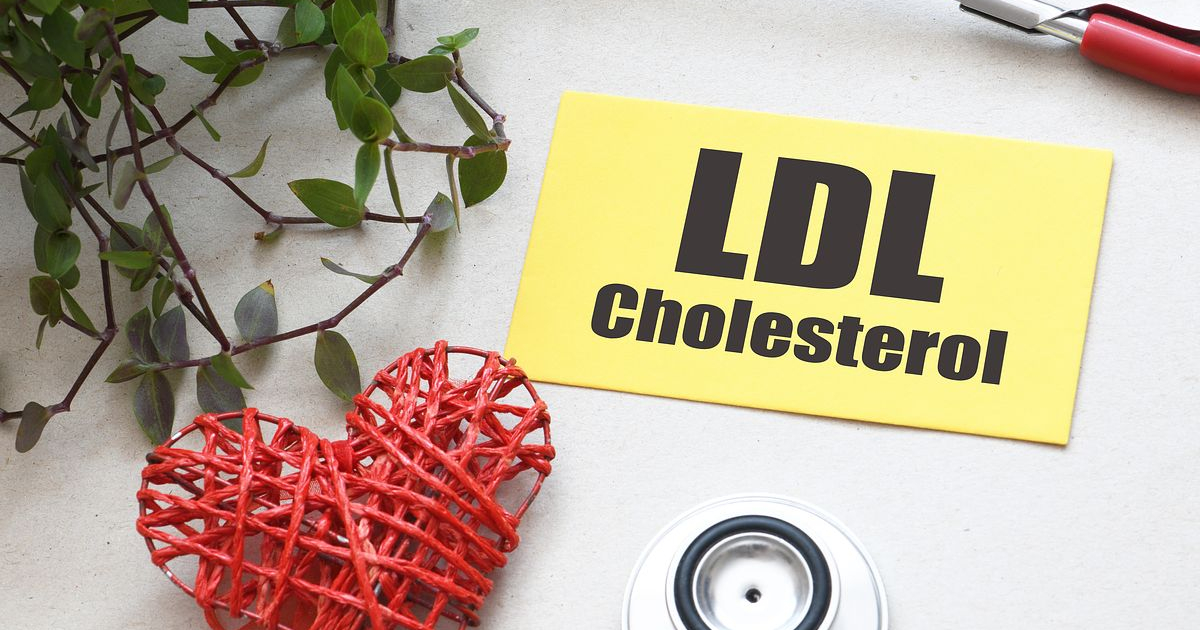体脂肪率の計算方法は?BMIとの違いや体脂肪を減らす方法を解説

ダイエットや健康管理をする際、体重だけでなく体脂肪率もあわせて管理したい方は多いと思います。
しかし、「体脂肪率の正しい計算方法がわからない…」という場合も多いのではないでしょうか。
この記事では、体脂肪率の計算方法とあわせて、体脂肪率を健康的に減らす方法を解説します。ダイエットや健康管理で体脂肪率を計算したい方は、ぜひ参考にしてください。
体脂肪率とは?
体の中に溜まっている脂肪のことを「体脂肪」といいます。「体脂肪率」は、体重のうちどのくらい体脂肪があるか、その比率をパーセントで表した割合のことです。
体脂肪は、主に皮下脂肪と内臓脂肪の2つに分けられ、それぞれ特徴が異なります。皮下脂肪は、名前のとおり皮膚の下につく脂肪のことで、一度溜まってしまうと簡単には減らせません。
一方で、内臓脂肪は胃や腸など内臓周辺につく脂肪のことで、体内のエネルギーが不足した際にエネルギーとして変換されます。この2つを合わせたものを「体脂肪」といいます。
BMIとの違い
体脂肪率とあわせてチェックしておきたい数値が「BMI」です。BMIは国際的に用いられている体格指数のことで、肥満や低体重などの判断に用いられます。BMIを求める計算式は以下のとおりです。
体重(kg)÷身長(m)の2乗
上記の計算方法は世界共通ですが、肥満の判定基準は国によって異なります。日本肥満学会は、BMI25以上が「肥満」、18.5未満は「低体重」、その間は「普通体重」と定めています。
BMIが18.5未満の場合は低体重(やせ過ぎ)なので、基本的にダイエットする必要はないでしょう。体脂肪率とあわせてBMIもチェックし、ぜひ健康的な体づくりに役立ててください。
体脂肪率の計算方法
ダイエットや健康維持のために把握しておきたい「体脂肪率」ですが、どのように計算すれば良いのでしょうか。体脂肪率は、以下の計算式で求められます。
体脂肪量(kg)÷体重(kg)×100=体脂肪率
この式を計算するには、「体脂肪量(kg)」が必要です。体脂肪量は、体組成計での測定の他、専用機器での測定が必要です。体脂肪量を正確に測定できる方法として、「水中体重秤量法」や「空気置換法」がありますが、個人で測ることは簡単ではありません。
体脂肪率を知りたい場合、計算して求めるのではなく、家庭で体脂肪率を測れる体脂肪計を用いることが手軽でおすすめです。主に使われているのは、「体脂肪計」です。
また、体脂肪率を計算できるサイトなどもありますが、体脂肪率を正確に計算することは難しいです。計算する場合も、あくまで目安として参考にしましょう。
体脂肪計を使った体脂肪率の計測
現在、家庭での体脂肪率計測として主流なのは、「生体電気インピーダンス法」とよばれるものです。
体に微弱な電流を流し、電流の流れやすさの程度を計測して体脂肪率を推定します。筋肉は電気を通しやすく、脂肪は電気を通さない性質を利用し、それぞれの電気抵抗量から体脂肪率を推定しています。
ただし、体脂肪計を使用する場合、実際の体脂肪量を測れているわけではありません。体脂肪計を使った計測は体内の水分量に影響を受けるため、測るタイミングによって変動します。あくまで目安として把握しましょう。
体脂肪率を正しく計測するコツ

体脂肪計を用いて体脂肪率を計測する際、できるだけ正確に測るためにはいくつかのコツがあります。
- 水分摂取後や運動・入浴後は避ける
- できるだけ同じ条件下で測る(時間や服装など)
上記のポイントに注意して計測しましょう。それぞれ詳しく解説します。
水分摂取後や運動・入浴後は避ける
体脂肪率を体脂肪計で計測する場合、水分摂取直後や運動後のタイミングは避けましょう。体内の水分量に影響を受ける計測方法なので、測るタイミングによって数値が変動してしまいます。
特に、体内の水分量が変わる水分補給後、運動や入浴で汗をかいた後は計測を避けることが望ましいです。
できるだけ同じ条件下で測る(時間や服装など)
体脂肪率は食事や体調の変化なども影響するため、継続的に測定する場合は、できるだけ1日の中で同じタイミングに同じ条件下で測定しましょう。
体脂肪計で測定する際は体に微弱な電流を流すため、洋服や靴下を身につけていると電流がスムーズに流れにくく、正確な数値が出ない場合があります。
そのため、できれば裸、裸足で測ることをおすすめします。洋服を着て測る場合は、できるだけいつも同じような服装にすると良いでしょう。
同じタイミングで測定するのを忘れてしまう場合は、「入浴前に裸で測る」など習慣化させると、継続して測りやすくなります。
体脂肪率の平均は?男女別に紹介
体脂肪率が高すぎたり、低すぎたりする状態は、それぞれリスクがあり、好ましくありません。
高すぎる場合、肥満による生活習慣病のリスクや心血管疾患、認知機能への悪影響が懸念されます。
一方で、低すぎると、脂肪の量が少ないことによる低体温や免疫力の低下をはじめ、髪や肌へも悪影響をおよぼします。女性の場合は、ホルモン代謝の働きにも影響し、月経異常や生理不順を引き起こすことも考えられます。
健康的な体脂肪率を保つには、基準値を把握する必要があります。性別によっても基準値は異なるため、健康とされる体脂肪率の平均値を確認しておきましょう。
体脂肪率の平均値
女性:20~29%
男性:10~19%
体脂肪率の数値は、平均して女性の方が高いです。女性は30%、男性は25%を超えると肥満とみなされます。基準を把握したうえで、健康的な体脂肪率を保つことが大切です。
体脂肪率を減らすために大切なこと
体脂肪率が低い場合、無理に減らす必要はありませんが、体脂肪率が高い場合は基準にあわせて減らすことで健康的な体つくりが叶います。
続いて、体脂肪率を減らすために心がけたいことを解説します。
- 栄養バランスの良い食事を心がける
- 摂取カロリーが消費カロリーを下回るように調整する
- よく噛んで食べる
なお、ダイエットについては以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
栄養バランスの良い食事を心がける
体脂肪率を減らすためには、朝昼晩、バランスの良い食事の摂取が基本です。炭水化物ばかり摂っていたり、栄養素が偏っていたりすると、健康に影響を与えてしまいます。栄養バランスを考え、偏りのないよう様々な食材を取り入れることが大切です。
バランスの良い食事とは、「一汁三菜」のように献立のバランスが取れており、栄養バランスの整った食事のことです。カロリー過多にならないよう気をつけながら、栄養満点の献立を心がけましょう。
バランスの良い献立についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
摂取カロリーが消費カロリーを下回るように調整する
「摂取カロリー<消費カロリー」になると、脂肪が燃焼されやすくなり体脂肪率も低下します。食べすぎていると感じる場合は摂取カロリーを見直して正常に戻し、消費カロリーを増やしましょう。
食事とあわせて、筋トレや有酸素運動をはじめとする適度な運動を行うことが大切です。無理のない範囲で取り組み、習慣化させましょう。
よく噛んで食べる
どんなに食事内容が優れていても、よく噛んで食べないと早食いになってしまい、体脂肪が増える原因になります。よく噛んで食べることで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎなくても十分満腹感を感じられるでしょう。
よく噛んで食べると肥満予防や消費カロリーの増加につながる他、噛む時間が長くなればなるほど、食事時間をゆっくり取れます。早食いによる食べ過ぎ防止にもなるため、普段からよく噛んでゆっくり食べることを心がけてください。
栄養バランスの整った食事なら「未来献立®」の活用がおすすめ
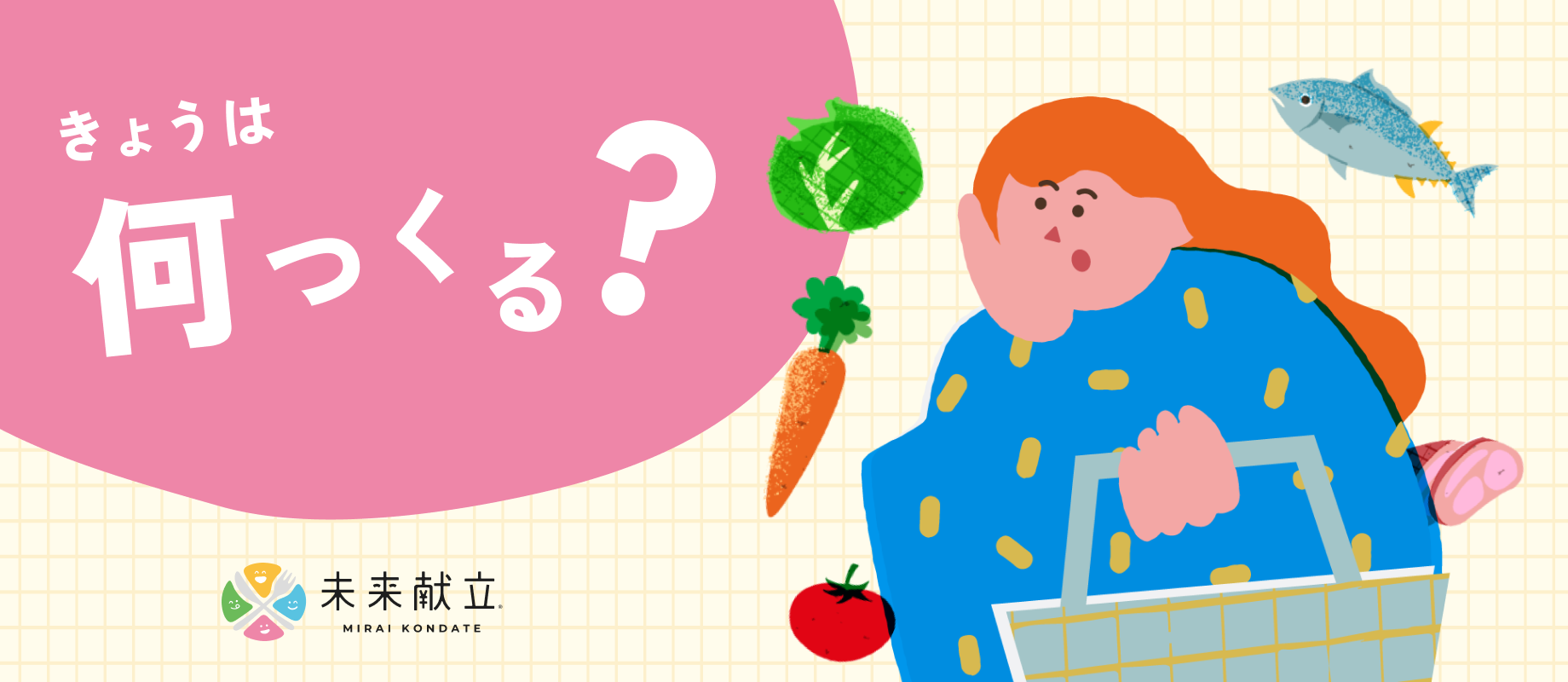
ここまで読んで、体脂肪率を健康的に減らすためにも栄養バランスの整った食事が大切なのはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
「未来献立®」は栄養バランスを考えた献立をまとめて提案するサービスです。活用することで、体脂肪率を健康的に減らすために大切な、バランスの良い献立を悩まず立てられます。
ダイエットや健康管理をしていて、「バランスの良い食事を考えるのが大変」「同じメニューばかりになってしまう」と悩んでいる方は、ぜひ一度チェックしてください。
体脂肪率を適正に保つにはバランスの良い食事も大切
体脂肪率とは、体重のうち体脂肪がどのくらい占めているかをパーセントで表したものです。体脂肪率を求める計算式も存在しますが、家庭での正確な計測はなかなか難しいです。
自身の体脂肪率を知りたいなら、計算して求めるのではなく、家庭で体脂肪率を測れる「体脂肪計」を用いると良いでしょう。目安として体脂肪率を把握し、ダイエットや健康維持に役立ててください。
適正な体脂肪率を保つためには、適度な運動とバランスの良い食事が大切です。特に、食事を見直すことで、健康的に体脂肪率を減らしやすいため、意識してバランスの良い食事を摂りましょう。
しかし、体脂肪率を適正に保つために、毎日バランスの良い食事を考えるのは大変です。手軽にバランスの良い食事を摂りたいなら、ぜひ「未来献立®」の利用を検討してください。

監修者
伊藤 まゆ(いとう まゆ)
M’sクリニック南麻布 院長、日本抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医
本当の美とは、心と体の健康あってこそ、という観点から、2007年開院時より、内外美容医療を提唱、実践。栄養学、予防医学、エイジングケア、美容について、多様な経験と多角的視点で取り組み、幅広い世代のサポートを行っている。
 献立提案サービス
献立提案サービス