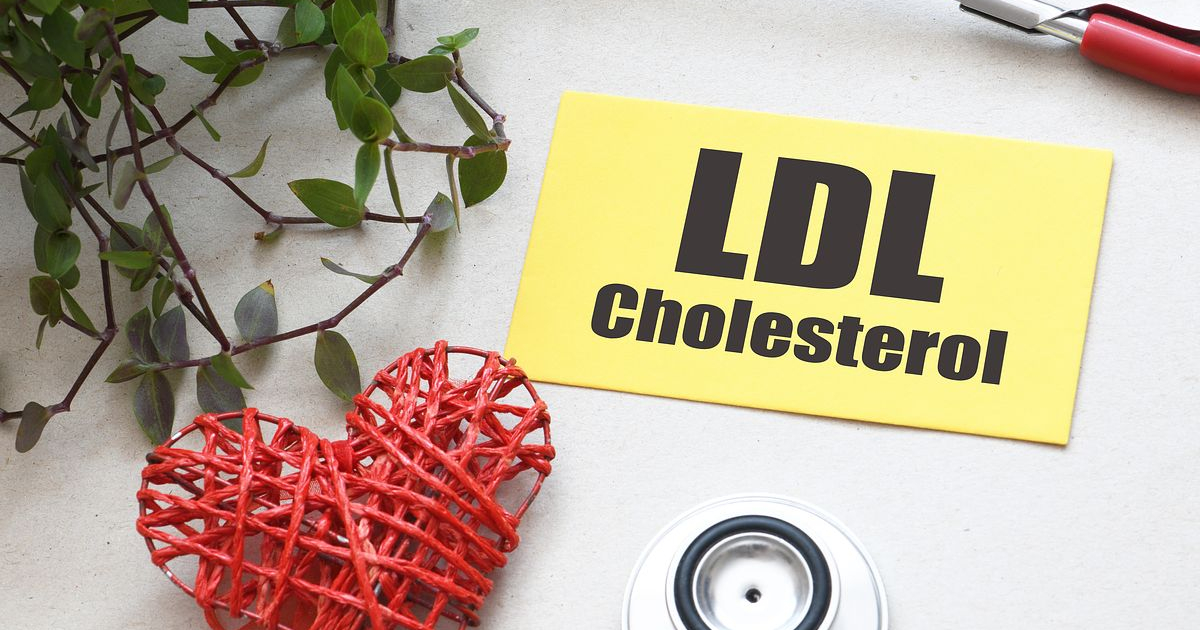偏頭痛に効く食べ物・避けるべき食べ物はある?日常生活のポイントも紹介

偏頭痛の原因は様々ですが、食べ物も頭痛と関連しています。「食べ物で偏頭痛を予防できるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
この記事では、偏頭痛の予防が期待できる食べ物と避けるべき食べ物を紹介します。偏頭痛を完全に予防できるわけではありませんが、人によっては辛い症状が和らぐ可能性があります。
食べ物で偏頭痛を予防するためには、バランスの取れた食生活が必要です。しかし、イベントや外食などで食生活が乱れる時もあるでしょう。
そんな時は、前日食べたものにあわせて献立を提案する「未来献立®」の活用をおすすめします。「未来献立®」の詳細は以下からご覧ください。
偏頭痛は食べ物で防げる?
偏頭痛は、特定の食べ物を摂取することで予防が期待できる場合があります。一方で、特定の食べ物が偏頭痛を引き起こす要因となる場合もあります。
ただし、偏頭痛に影響をおよぼすのは食べ物だけではありません。偏頭痛には、睡眠不足やストレス、環境要因など様々な事柄が影響します。そのため、食べ物だけで完全に予防することは難しいでしょう。
偏頭痛で悩んでいる方は、食事だけでの対策に頼るのではなく、まずは医療機関に相談することをおすすめします。そのうえで、偏頭痛を予防する手段のひとつとして、毎日の食事に注目すると良いでしょう。
偏頭痛の予防に良いとされる食べ物
偏頭痛の予防に良いとされる食べ物は以下のとおりです。
- マグネシウムを多く含む食べ物
- ビタミンB2を多く含む食べ物
それぞれの食べ物について詳しく解説します。
マグネシウムを多く含む食べ物

マグネシウムが多く含まれる食べ物を摂取すると、偏頭痛の予防が期待できるでしょう。代表的な食べ物を紹介します。
- えだまめ
- わらび
- きくらげ
- こんにゃく
- 落花生
- しいたけ
- まいたけ
- 切り干し大根
- ほうれん草
- ナッツ類
- 全粒穀物
- 大豆製品
マグネシウムは、体内に存在するミネラルのひとつで、細胞膜を安定させたり神経伝達物質の放出を調整したりする役割があります。
マグネシウム不足は脳の神経活動や神経伝達物質の異常につながります。血流の低下を招くため、偏頭痛が引き起こされやすくなるでしょう。
マグネシウムは、食生活の欧米化や加工食品の増加、ストレスなどの影響で不足しやすい傾向にあります。白米を玄米や雑穀米にしたり、おやつにナッツ類を取り入れたりして、意識的に摂取してください。
ビタミンB2を多く含む食べ物
ビタミンB2は血流を促すため、偏頭痛の予防が期待できるでしょう。
ビタミンB2が不足すると、集中力の低下やイライラ、睡眠の質の低下などが起きるため、偏頭痛の原因となるストレスが溜まりやすいです。
ビタミンB2を多く含む食べ物を紹介します。
- レバー
- 牛乳
- 卵
- 納豆
- アーモンド
- うなぎ
- 魚肉ソーセージ
- 青魚
- 魚卵
ビタミンB2は水溶性ビタミンなので、摂取してもすぐに尿として排出されます。体内に蓄えておけないため、できるだけ毎日摂取しましょう。
偏頭痛が起こりやすくなる食べ物はある?
偏頭痛が起こりやすくなるとされる食べ物は以下のとおりです。
- アルコール
- チラミンを多く含む食べ物
- 亜硝酸塩(亜硝酸ナトリウム)を多く含む食べ物
それぞれの食べ物を詳しく解説します。
アルコール
アルコールが持つ血管を拡張させる作用により、「血管性頭痛」を引き起こす可能性があります。血管性頭痛とは、頭部の血管が拡張することにより、周囲の神経が刺激されて起こる頭痛です。
特に赤ワインは、血管を拡張する「ヒスタミン」が多く含まれているため、酒類の中でも注意が必要です。
また、アルコールの飲み過ぎによる二日酔いで、頭痛が起こるケースも考えられます。二日酔いの頭痛は、アルコールに含まれる「アセトアルデヒド」が原因です。偏頭痛に悩んでいる方はアルコールの摂取を避けるか、少量に留めると良いでしょう。
チラミンを多く含む食べ物
チラミンを多く含む食べ物は、血管を収縮させることがあります。そして、チラミンの分解後に血管が拡張するタイミングで、頭痛が起きる可能性が高まります。
チラミンを多く含む食べ物は、以下のとおりです。
- チーズ
- 納豆
- 醤油
- レバー
- チョコレート
- ヨーグルト
発酵食品はチラミンを含む食材が多いです。しかし、全ての人がチラミンに反応するわけではありません。食後の体調を確認して、今後避けるべきかを判断すると良いでしょう。
亜硝酸塩(亜硝酸ナトリウム)を多く含む食べ物
亜硝酸塩(亜硝酸ナトリウム)を多く含む食べ物は、偏頭痛を誘発する可能性があります。亜硝酸塩の脳への血流を増やす作用は、偏頭痛が起きるリスクを高めるでしょう。
亜硝酸塩は、ハム・ソーセージ・サラミなどの加工肉を赤くするための添加物として使われます。
亜硝酸塩を通常量を摂取する程度なら人体に悪影響はないので、過剰に心配する必要はありません。しかし、偏頭痛に悩んでいる方は、頭痛との関係を意識しながら摂取しましょう。
偏頭痛予防のために日常生活で気をつけたいポイント

偏頭痛が起きないよう、日常生活で気をつけたいポイントは以下のとおりです。
- 栄養バランスの良い食事を摂る
- 十分な睡眠を確保する
- ストレスを溜めない
各ポイントを詳しく説明します。
栄養バランスの良い食事を摂る
偏頭痛を予防するためには、偏頭痛の予防が期待できる食べ物、避けるべき食べ物を考慮しつつ、栄養バランスの良い食事を摂りましょう。
低血糖が頭痛の原因となる場合もあるため、適度な糖質の摂取も必要です。一方で、過剰な糖の摂取は急激に血糖値が上がり、反動で低血糖になる場合もあるため注意してください。
偏頭痛の予防が期待できるマグネシウムやビタミンB2を適度にとりつつ、適度な糖質を摂るには、和食を中心とした献立がおすすめです。「未来献立®」を活用して、栄養バランスの良い食生活目指しましょう。
バランスの良い食事についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
十分な睡眠時間を確保する
偏頭痛予防のためには、適切な睡眠をとりましょう。睡眠の過不足はホルモンの分泌に影響し、頭痛を引き起こすといわれています。
寝不足は、反動による過眠につながるため、普段から十分な睡眠時間を確保し、生活リズムを整えなければなりません。
寝付きが悪い方は、スムーズに入眠できるよう、次の生活習慣を心がけましょう。
- 起床時間と就寝時間を決める
- 日の光を浴びる
- 夕方以降のカフェイン・アルコール摂取は避ける
- 寝室は暗く、静かにする
- 寝る前にテレビ・スマートフォンを見ない
生活リズムを整えるために、平日・休日ともに起床時間と就寝時間を一定にしましょう。また、昼間に日の光を十分に浴びるのもポイントです。
寝る前にテレビやスマートフォンなどから発する強い光を見ると、スムーズな入眠に支障をきたします。睡眠の質も悪くなるので、注意しましょう。
ストレスを溜めない
ストレスは頭痛の原因のひとつです。ストレスが溜まると、ストレスホルモンであるコルチゾールなどの自律神経が乱れます。ストレスホルモンには血圧を上昇させる作用があり、血管の収縮・拡張により頭痛が引き起こされます。
また、自律神経の乱れは筋肉を緊張させます。頭部の筋肉が緊張し収縮すると頭が締め付けられ、頭痛が起こるケースもあります。
普段からストレスを感じている方は、以下の方法を試しましょう。
- ストレスの原因を知る
- 可能ならストレス源から距離を置く
- 軽い運動を楽しむ
- 湯船に浸かってゆっくりする
- 好きな香りを楽しむ
- 自然に触れる機会をつくる
- 創作活動に挑戦する
- 誰かに悩みを相談する
ストレス解消には、リラックスすることがとても重要です。短時間でも構わないので、自分がリラックスできる環境で、ゆっくりする時間をつくりましょう。
くれぐれも、ストレス解消の方法として夜更かしや暴飲暴食を選んではいけません。食生活や生活習慣の乱れは、さらなるストレスにつながります。
栄養バランスの整った献立なら「未来献立®」の活用がおすすめ
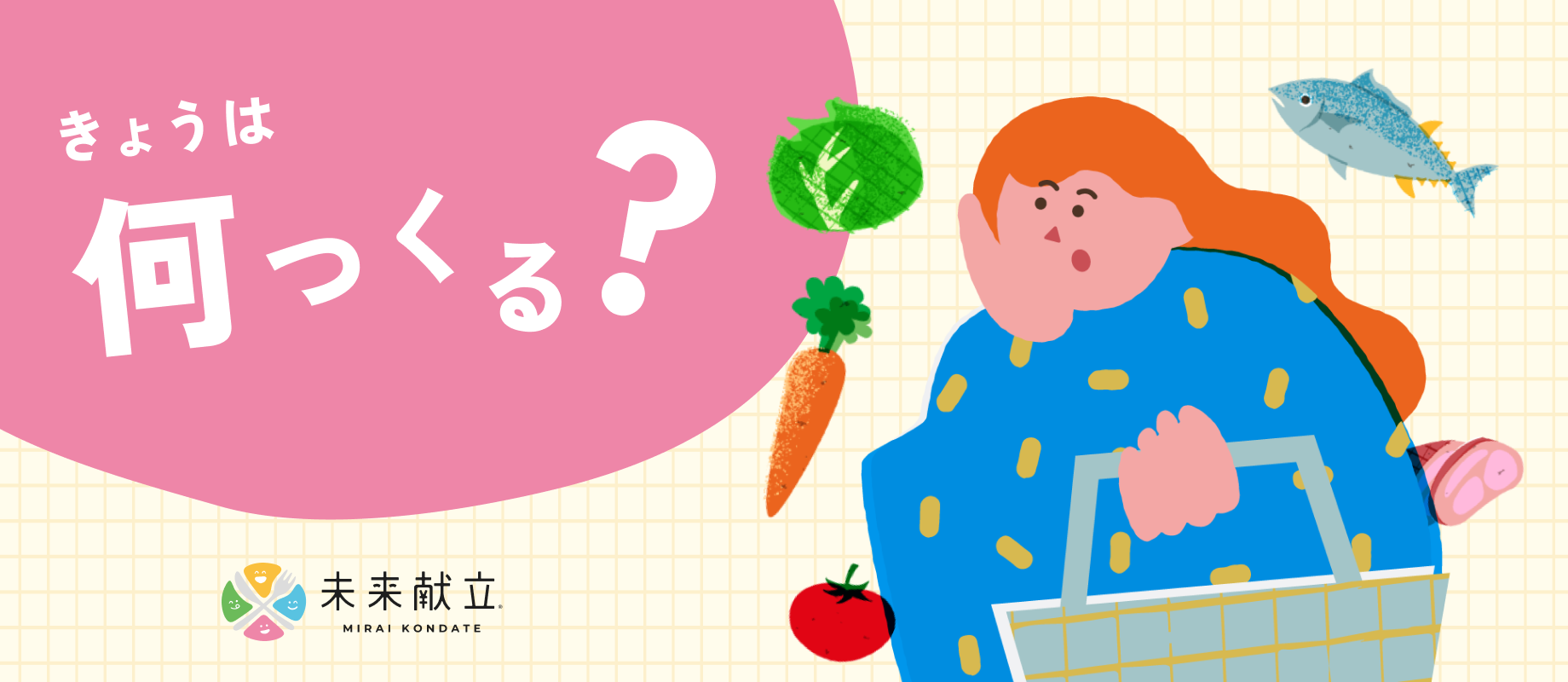
ここまで読んで、偏頭痛の予防に栄養バランスの整った食事が大切なのはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
「未来献立®」は、栄養バランスの取れた食事メニューを提案しています。一度で8日分のメニューを決められるので、毎日の献立に悩んでしまう方にぴったりです。
好みにあわせたカスタマイズもできるので、苦手な食べ物がある方も満足できるでしょう。偏頭痛の予防のために、バランスの良い食生活を目指す方は、ぜひ「未来献立®」を試してみてください。
食生活と日常生活の改善で偏頭痛を予防しよう
偏頭痛は、食べ物での予防が期待できます。ただし、偏頭痛の原因は様々なので、食事だけで完全に改善できるわけではありません。
食べ物による頭痛予防は、多くの予防法のひとつとして、日常生活に取り入れると良いでしょう。
偏頭痛を予防するためには、予防効果が期待できるマグネシウムやビタミンB2を取り入れた栄養バランスの良い食事を心がけてください。栄養バランスの良い献立を考えるならなら、「未来献立®」の活用をおすすめします。
その他にも、十分な睡眠時間の確保やストレスを溜めない生活を意識し、定着させましょう。

監修者
伊藤 まゆ(いとう まゆ)
M’sクリニック南麻布 院長、日本抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医
本当の美とは、心と体の健康あってこそ、という観点から、2007年開院時より、内外美容医療を提唱、実践。栄養学、予防医学、エイジングケア、美容について、多様な経験と多角的視点で取り組み、幅広い世代のサポートを行っている。
 献立提案サービス
献立提案サービス