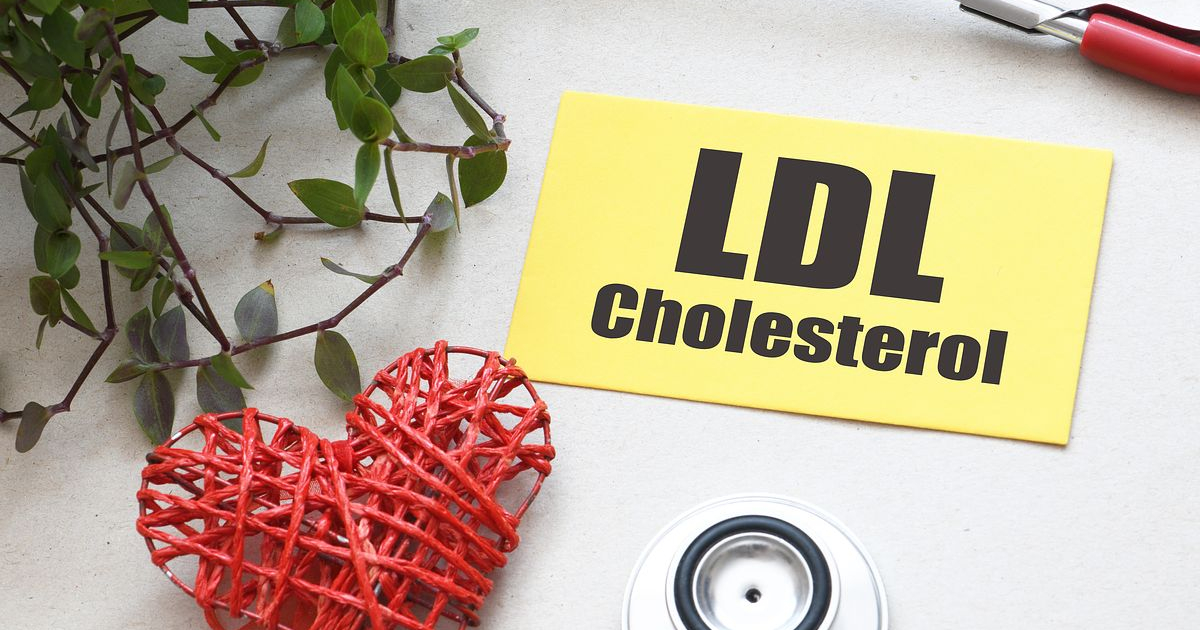貧血の原因とは?改善方法と予防方法・必要な栄養素を紹介

貧血になると、全身が酸素不足になり様々な身体の不調を引き起こします。何らかの疾患により貧血になっている可能性もあるため、放置するべきではありません。
この記事では、貧血の原因や改善方法、予防方法、貧血を予防するために必要な栄養素を紹介します。
貧血を予防するためには、栄養バランスの整った食生活を送る必要があります。しかし、毎日栄養バランスがとれた献立を考えるのは難しいでしょう。
そんな時は、最大8日分の献立をご提案する「未来献立®」がおすすめです。「未来献立®」の詳細は以下からご覧ください。
貧血とは?
貧血とは、何らかの理由で血液のなかに存在するヘモグロビンの濃度が低下し、血液が薄くなっている状態です。
ヘモグロビンは、鉄とたんぱく質が結合してつくられています。貧血のなかでも、鉄が欠乏して起きる貧血を「鉄欠乏性貧血」といいます。
貧血の診断の目安とヘモグロビンの正常値は以下のとおりです。
ヘモグロビン値における貧血の目安
| 性別 | 貧血と診断される値 | 正常値 |
|---|---|---|
| 男性 | 13g/dl以下 | 13.5~18g/dl |
| 女性 | 12g/dl以下 | 12~16.5g/dl |
ヘモグロビンは酸素を運ぶ役割があるので、不足すると全身が酸素不足になり、様々な症状が現れやすくなります。
貧血の主な症状は、以下のとおりです。
- 疲労感
- 息切れや動悸
- めまいや立ちくらみ
- 耳鳴り
- 慢性的な頭痛や肩こり
- 眠気
- 不眠
- 食欲不振
- 吐き気
- 性機能の低下
どんな症状が現れるかは、個人差があります。目立つ症状がなく、血液検査をしてはじめて貧血とわかる方も多いです。
貧血になる原因
貧血になる原因は以下のとおりです。
- 血液が十分につくられていない
- 血液を失っている
それぞれの原因を詳しく解説していきます。
血液が十分につくられていない
何らかの原因で血液が十分につくられないと、貧血になります。要因は以下のとおりです。
- 赤血球やヘモグロビンなどをつくるのに必要な栄養素が不足している
- 骨髄や腎臓の病気で血液がうまくつくれない
血液が十分につくられない理由の多くは、鉄分をはじめとした栄養素の不足です。特に妊娠中や授乳期は栄養不足になりやすく、貧血になるリスクが高まります。ダイエットをしている方や偏食の方も貧血になりやすいので注意が必要です。
血液を失っている
大量の出血をしたり、持続的に出血していたりすると、貧血になります。要因となるのは、ケガや手術、頻発月経、過多月経、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、がん、痔などです。
また、激しい運動や細菌感染、免疫の異常などで赤血球が破壊される場合もあります。赤血球が壊れる病気や、もろくなる病気も存在します。
貧血を改善するにはどうしたら良い?
貧血を改善するためには、まず医療機関を受診してください。貧血の改善には、専門家による原因の特定と、医学的な治療が必要です。まずは、貧血の原因を明確にするために受診しましょう。
仮に栄養不足が原因で貧血になっている場合には、医療機関で処方される薬の服用と併せて、食生活の改善が必要です。
何らかの疾患が貧血の原因となっている場合は、疾患に対する適切な治療を受けなければなりません。
なお、貧血の他に気になる症状がない場合には、一般内科を受診しましょう。もし月経異常がある場合には、婦人科の受診がおすすめです。
鉄欠乏性貧血を予防する方法

栄養不足による鉄欠乏性貧血を予防する方法は以下のとおりです。ひとつの方法を選ぶのではなく、予防方法を可能なかぎり取り入れられるよう、意識しましょう。
- 血液をつくるのに必要な栄養素を摂取する
- 十分な睡眠をとる
- 適度な運動を心がける
それぞれの方法を詳しく解説していきます。
血液をつくるのに必要な栄養素を摂取する
貧血を予防するためには、血液をつくるのに必要な栄養素を十分に摂取する必要があります。血液をつくるのに必要な栄養素は、主に「鉄」や「たんぱく質」です。鉄の吸収を良くする「ビタミンC」などの栄養素も積極的な摂取を心がけましょう。
また、血液をつくるための栄養素が足りていても、全体のエネルギーが不足しているとエネルギー代謝異常を起こし、正常に血が生産されません。十分なエネルギーを摂取できるよう、毎日3食欠かさず食べることが必要となるでしょう。
食による貧血予防は、長期間にわたって行う必要があります。一時的な取り組みと考えるのではなく、適切な食生活を定着させなければなりません。
バランスの良い献立や栄養素についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
- 関連記事:栄養バランスの良い献立の考え方は?朝昼晩の献立例・レシピも紹介
- 関連記事:たんぱく質が多い食材を一覧表で紹介!効果的な摂取方法やおすすめレシピも
- 関連記事:ビタミンCを多く含む食べ物ランキング!栄養素の働きや効率的に摂る方法も紹介
十分な睡眠をとる
貧血を予防するためには、十分な睡眠が必要です。睡眠不足による免疫機能の低下やホルモンバランスの乱れが、鉄の吸収を妨げるからです。また、睡眠時に分泌される成長ホルモンも、血液細胞の生成に関係しています。
睡眠と貧血には関連があり、貧血になると寝付きが悪くなったり、夜中に目覚めやすくなったりします。反対に、昼間は疲労により眠気を感じやすくなります。
貧血による眠気や不眠の症状に悩んでいる方は、貧血の治療を受けつつ、カフェインの摂取を控える、寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、良い睡眠をとるための習慣を身に付けると良いでしょう。
適度な運動を心がける
貧血を予防するためには、適度な運動も必要です。適度な運動は、赤血球の生産を活発にします。また、運動すると全身の血流が良くなり、鉄が効率的に利用されます。
加えて、運動により内臓機能の回復も期待できるでしょう。ただし、激しい運動は貧血を悪化させるため、軽く身体を動かす程度にとどめてください。
貧血を予防するために必要な栄養素と食べ物

貧血を予防するために必要な栄養素と食べ物の例を、以下の表にまとめました。献立を考える際の参考にしてください。
鉄分が多い食べ物の種類
| 栄養素 | 食べ物の種類 |
|---|---|
| 鉄(ヘム鉄) | レバー・牛肉・かつお・アサリ・砂肝 ※ヘム鉄は非ヘム鉄のおよそ10倍の吸収率があります。 |
| 鉄(非ヘム鉄) | 大豆製品・小松菜・ひじき |
鉄の吸収を助ける栄養素と食べ物の種類
| 栄養素 | 食べ物の種類 |
|---|---|
| ビタミンC | パプリカ・ゴーヤ・ブロッコリー・果物 |
| たんぱく質 | 牛肉・豚肉・鶏肉・魚・大豆製品・卵 |
| クエン酸 | 梅干し・レモン・酢 |
造血作用がある栄養素と食べ物の種類
| 栄養素 | 食べ物の種類 |
|---|---|
| ビタミンB12 | 魚介類・牛レバー・二枚貝・肉、鳥肉、卵、牛乳・乳製品 |
| 葉酸 | 枝豆・ブロッコリー・葉物野菜・アスパラガス |
貧血を予防するためには、鉄分の摂取の他に鉄の吸収を助ける栄養素や造血作用がある栄養素が必要です。
鉄分だけでなく、様々な栄養素に注目して食べるものを決めましょう。
貧血を予防する際に避けるべき栄養素と食べ物
鉄の吸収を阻害する食べ物の例は、以下のとおりです。
鉄の吸収を阻害する成分と食べ物の種類
| 成分 | 食べ物の種類 |
|---|---|
| タンニン | コーヒー・緑茶・烏龍茶・紅茶・赤ワイン |
| 不溶性食物繊維 | 玄米・ふすま・おから |
| 加工食品 | ハム・ソーセージ・その他加工食品・清涼飲料水・スナック菓子 |
| アルコール | ビール・日本酒・ウィスキー・焼酎・ワインなど |
コーヒーや緑茶に含まれる「タンニン」と鉄分を一緒に摂ると、鉄分の吸収が悪くなります。飲む場合は食事と時間をずらしましょう。
また、加工食品や不溶性食物繊維も鉄の吸収を阻害します。アルコール飲料も、代謝する際にビタミンが消費されてしまうため、鉄の吸収率を低くする要因です。摂りたい栄養素だけでなく、鉄の吸収を阻害する食べ物も、あわせて覚えておきましょう。
栄養バランスの整った献立を考えるなら「未来献立®」を活用しよう
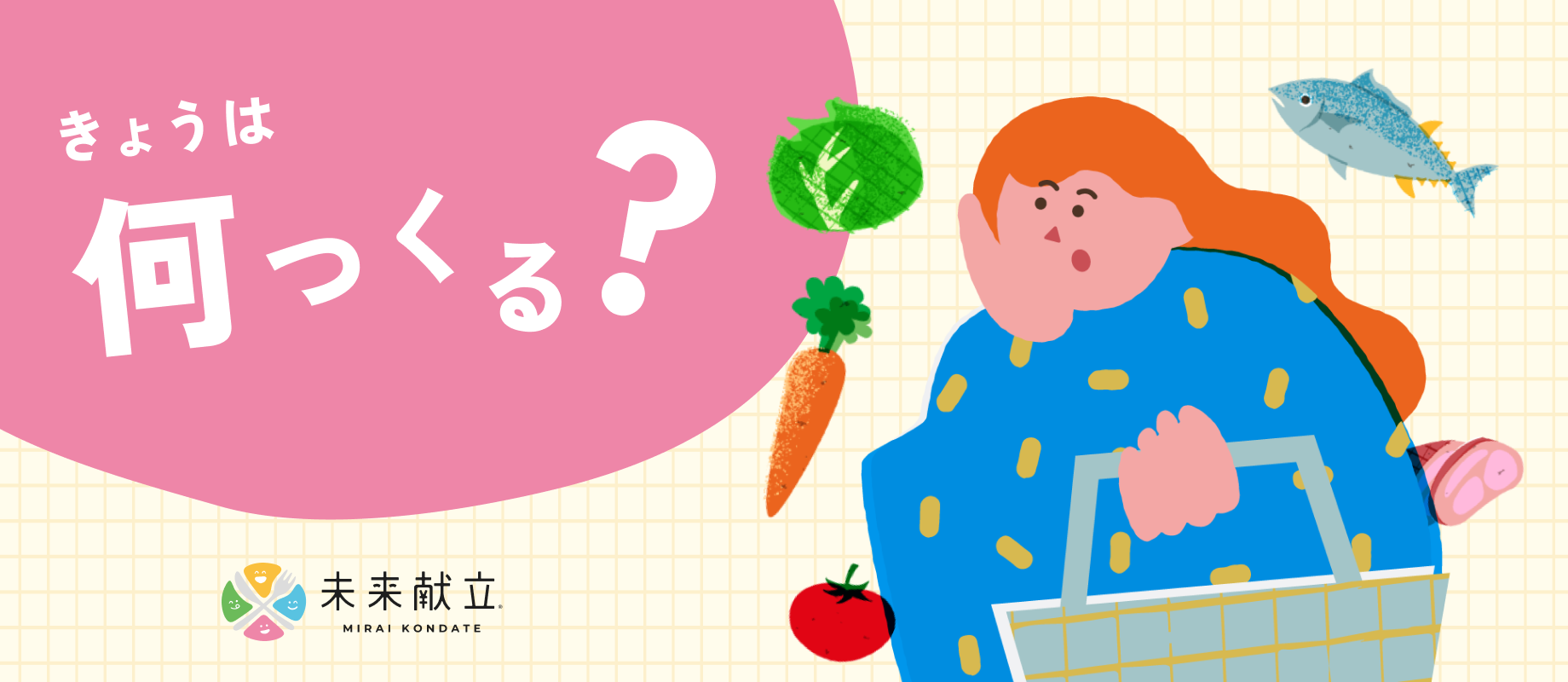
ここまで読んで、貧血予防のために栄養バランスの整った食事が大切なのはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
最大8日分のメニューを考えてくれるので、毎日の食事内容を考えるのが楽になるでしょう。前日に食べたものが脂っこかったり、野菜が少なめだったりした場合には、前後で栄養バランスを整えるツジツマ献立を提案しています。
「未来献立®」を活用すれば、外食やイベントなどがあっても、無理なく栄養バランスの整った食生活を送ることができます。
貧血の原因を特定して適切な対処をしよう
貧血は血液中のヘモグロビンが不足し、血液が薄くなっている状態です。疲れやすい、動悸・息切れなど様々な症状が現れる場合があります。
貧血の多くは、栄養不足による鉄欠乏性貧血です。しかし、何らかの疾患が原因となっている場合もあるので、貧血の疑いがある方は医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
鉄欠乏性貧血を予防するためには、血液をつくるのに必要な栄養素を摂り、十分な睡眠と適度な運動を心がける必要があります。食事の内容で悩んだ場合には、「未来献立®」をぜひ活用してください。

監修者
伊藤 まゆ(いとう まゆ)
M’sクリニック南麻布 院長、日本抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医
本当の美とは、心と体の健康あってこそ、という観点から、2007年開院時より、内外美容医療を提唱、実践。栄養学、予防医学、エイジングケア、美容について、多様な経験と多角的視点で取り組み、幅広い世代のサポートを行っている。
 献立提案サービス
献立提案サービス