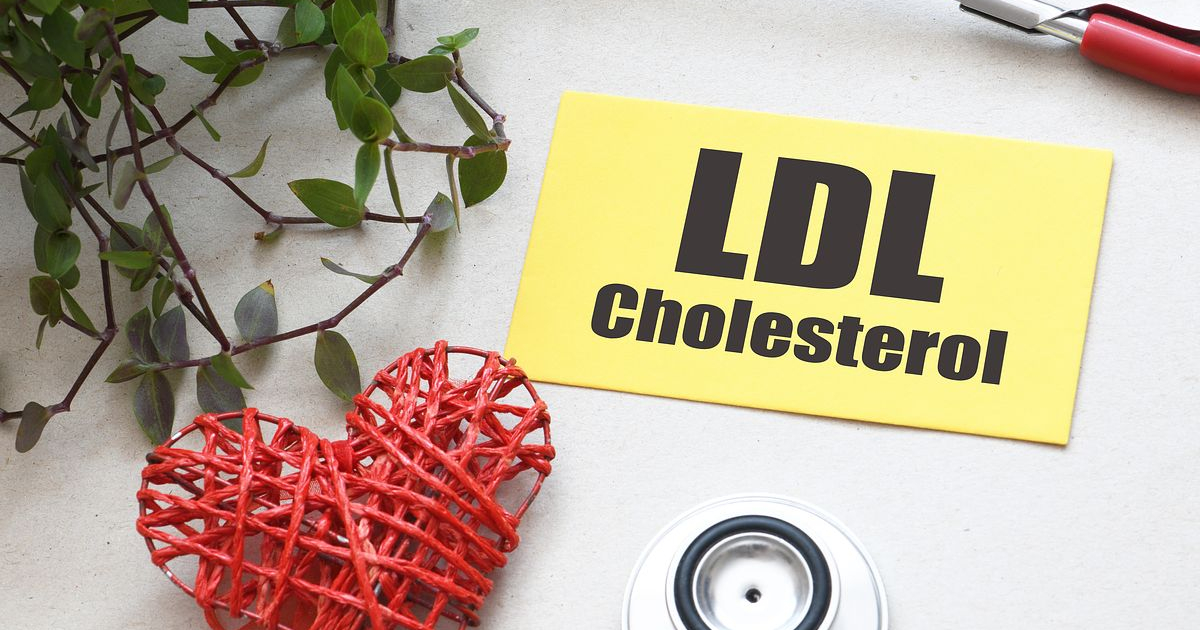ビタミンCを多く含む食べ物ランキング!栄養素の働きや効率的に摂る方法も紹介

風邪予防やお肌の健康維持などのために、ビタミンCを積極的に摂取しようと考える方は多いのではないでしょうか。まずは、栄養素の働きや役割を理解しましょう。
この記事では、ビタミンCの働きや役割とともに、ビタミンCを多く含む食品を「野菜」「果物」「飲み物」別にランキング形式で紹介します。
また、あわせて1日に必要な摂取量の目安や効率よく摂取する方法なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ビタミンCとは?
ビタミンCは、食品に含まれる水溶性ビタミンのひとつです。化学名では別名「アスコルビン酸」とも呼ばれ、果物(特に柑橘類)や野菜から多く摂取できます。
ほとんどの動物は、ブドウ糖をもとにしてビタミンCを体内で合成できるものの、ヒトはビタミンCを体内でつくり出すことができません。
そのため、ビタミンCは、野菜や果物などの食品から摂取しなければならない栄養素のひとつです。
ビタミンCが持つ働きや役割
ビタミンCが持つ働きや役割には、主に以下が挙げられます。
- 活性酸素を抑えて体の健康を維持する
- コラーゲンの生成を促進する
- 免疫力を高める
- 鉄の吸収を促進する
それぞれについて次章で詳しく解説します。
活性酸素を抑えて体の健康を維持する
ビタミンCは、ビタミンA、ビタミンEなどとともに、活性酸素の働きを抑える作用を持つ「抗酸化ビタミン」とも呼ばれます。
活性酸素とは、呼吸によって体内に取り込まれた酸素の一部が、通常よりも活性化された状態になることです。活性酸素は、神経伝達物質や免疫機能として重要な役割を持つものの、体内で過剰になると細胞障害を引き起こす恐れがあるため、過剰に蓄積させないことが重要です。
例えば、動脈硬化を起こしやすくする「過酸化脂質」をつくり出す他、がんや老化、免疫機能の低下などを引き起こします。
ヒトは、もともと酵素によって活性酸素を抑える働きを持ちますが、年齢などにより酵素の量は減少し、活性酸素を抑える能力も減少します。そのため、活性酸素の働きを抑える作用を持つ、抗酸化ビタミンの十分な摂取が重要です。
ビタミンCを摂取し抗酸化作用が発揮されることで、がんや動脈硬化の予防、老化防止が期待できます。
コラーゲンの生成を促進する
ビタミンCは、「コラーゲン」を生成するために必要な栄養素です。
コラーゲンとは、皮膚や腱、軟骨、血管などを構成するたんぱく質の一種で、体を構成する全てのたんぱく質のうち約30%を占めています。肌の弾力や関節の柔軟性に関して重要で、傷の治癒にも関わります。
免疫力を高める
ビタミンCは、ストレスや風邪などの病気に対する抵抗力を高め、免疫系の適切な働きを助ける効果があります。
そのため、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかると、より多くのビタミンCを摂取する必要があります。
鉄の吸収を促進する
ビタミンCは、植物性食品から鉄の吸収を促進する働きを持ちます。
人体に必要な栄養素である鉄は、赤血球のヘモグロビンに多く含まれ、不足すると鉄欠乏貧血を引き起こす他、頭痛や食欲不振、集中力の低下などの原因となる場合もあります。
月経のある女性や、妊娠・授乳期の女性には特に重要な栄養素のひとつでもあり、不足しないためには、鉄と一緒にビタミンCを摂取すると良いです。
ビタミンCが多く含まれる食材ランキング
ビタミンCは、主に野菜や果物に豊富に含まれており、動物性食品にはほとんど含まれていません。
文部科学省による「食品成分データベース2023年増補※」をもとに、ビタミンCが多く含まれる食材を、「野菜」、「果物」、「飲みもの」に分けてそれぞれランキング形式で紹介します。
※出典:文部科学省「食品成分データベース」
【野菜】
各「野菜」に含まれるビタミンC量のうち、可食部100gあたりの含有量が多い順※に紹介します。
ビタミンCは加熱に弱く水に溶けやすい特徴があるため、調理によって実際に摂取できるビタミンC量は減少します。ただし、加熱することでカサが減るため、摂取する野菜量を多くできたり、汁ごと食べたりすれば、水に溶け出したビタミンCを享受できます。
生野菜にこだわらず、煮たり、炒めたりして、いろいろなバリエーションで摂取できるよう心がけましょう。
【野菜】可食部100gあたりのビタミンC含有量ランキング(生食)
| 順位 | 食品名 | 成分量 (100gあたりmg) |
|---|---|---|
| 1 | トマピー | 200 |
| 2 | 赤ピーマン | 170 |
| 3 | めキャベツ | 160 |
| 4 | オレンジピーマン | 150 |
| 5 | 黄ピーマン | 150 |
| 6 | ブロッコリー | 140 |
| 7 | 和種なばな | 130 |
| 8 | とうがらし | 120 |
| 9 | パセリ | 120 |
| 10 | 洋種なばな | 110 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
ランキングを見ると、生の野菜の中では、カラーピーマンやブロッコリー、青菜類などに特に多く含まれていることがわかります。
パプリカ(赤ピーマンやオレンジピーマン、黄ピーマン)は、青ピーマンと比較すると約2倍のビタミンCを含み、さらに、欧米では「栄養素の宝庫」と呼ばれるほど栄養素が豊富なブロッコリーも、ビタミンCの含有量は野菜の中でもトップクラスです。
【果物】
各「果物」に含まれるビタミンC量のうち、可食部100gあたりの含有量が多い順※1※2に紹介します。なお、果物を生で食べる場合のみのランキングです。
【果物】可食部100gあたりのビタミンC含有量ランキング(生食)
| 順位 | 食品名 | 成分量 (100gあたりmg) |
|---|---|---|
| 1 | アセロラ/酸味種 | 1700 |
| 2 | アセロラ/甘味種 | 800 |
| 3 | グァバ/赤肉腫・グァバ/白肉腫 | 220・220 |
| 4 | キウイフルーツ/黄肉種 | 140 |
| 5 | レモン/全果 | 100 |
| 6 | キウイフルーツ/緑肉種 | 71 |
| 7 | かき/甘がき | 70 |
| 8 | あけび/果肉 | 65 |
| 9 | いちご | 62 |
| 10 | オレンジ/ネーブル/砂じょう | 60 |
-
※1 出典:文部科学省「食品成分データベース」
-
※2 食品成分データベースのランキング(対象食品:果実類)のうち、果皮や果実飲料を除いて記載しています。
【飲みもの】
各「飲みもの」に含まれるビタミンC量のうち、成分量100gあたりの含有量が多い順※に紹介します。
【飲みもの】成分量100gあたりのビタミンC含有量ランキング
| 順位 | 食品名 | 成分量 (100gあたりmg) |
|---|---|---|
| 1 | 青汁/ケール | 1100 |
| 2 | せん茶 | 260 |
| 3 | アセロラ/果汁飲料/10%果汁入り飲料 | 120 |
| 4 | 玉露 | 110 |
| 5 | 抹茶 | 60 |
| 6 | グレープフルーツ/果実飲料/濃縮還元ジュース | 53 |
| 7 | オレンジ/バレンシア/果実飲料/濃縮還元ジュース | 42 |
| 8 | グレープフルーツ/果実飲料/ストレートジュース | 38 |
※出典:文部科学省「食品成分データベース」
ビタミンCの1日の推奨摂取量目安
1日に必要なビタミンCの推奨量は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書※に記載があります。
| 年齢 | 男性(mg) | 女性(mg) |
|---|---|---|
| ~5(月) | ― | ― |
| 6~11(月) | ― | ― |
| 1~2歳 | 35 | 35 |
| 3~5歳 | 40 | 40 |
| 6~7歳 | 50 | 50 |
| 8~9歳 | 60 | 60 |
| 10~11歳 | 70 | 70 |
| 12~14歳 | 90 | 90 |
| 15~17歳 | 100 | 100 |
| 18~29歳 | 100 | 100 |
| 30~49歳 | 100 | 100 |
| 50~64歳 | 100 | 100 |
| 65~74歳 | 100 | 100 |
| 75歳以上 | 100 | 100 |
| 妊婦(付加量) | ― | +10 |
| 授乳婦(付加量) | ― | +45 |
※出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書」
ビタミンCが不足するとどうなる?
前述のとおり、ビタミンCは骨や腱などの結合たんぱく質であるコラーゲンの生成に欠かせない栄養素です。ビタミンCが不足すると、コラーゲンが生成されずに血管がもろくなり出血を引き起こします。この状態が壊血病(かいけつびょう)です。
壊血病の症状には、他にもイライラ、顔色が悪くなる、皮下や歯茎からの出血、貧血、筋肉が減る、心臓障害、呼吸困難などが挙げられます。
ビタミンC不足が起こりやすいのは、主に以下に当てはまる方です。
ビタミンC不足になりやすい方
- アルコール依存症者
- 野菜、果物の摂取が少ない方
- ビタミンCの必要性が高い高齢者
- 薬物依存症者
また、喫煙者や受動喫煙者は、非喫煙者と比較してよりビタミンCの必要性が高まります。
1日あたり10mg程度のビタミンCを摂取していれば欠乏症は発症しないものの、これらに該当する方は、より意識してビタミンCを摂る必要があります。
ビタミンCを過剰摂取するとどうなる?
健康な方がビタミンCを過剰に摂取しても、消化管からの吸収率が低下して尿中に排出される量が増えることから、耐容上限量が定められておらず広い摂取範囲で安全と考えられています。
ただし、通常の食事以外のサプリメントなどによる過剰摂取により、吐き気や腹痛、下痢をはじめ、胃腸に不調が生じる恐れがあります。
食品に含まれるビタミンCは、通常、過剰摂取になることはないため、むしろビタミンC不足にならないよう、積極的に野菜や果物を食べるようにしましょう。
ビタミンCの効率的な摂り方とポイント

前述のとおり、水溶性であるビタミンCは尿中から排出されやすく、体内消費量も多い栄養素です。食事からビタミンCを十分に摂取していると思っていても、気づかないうちにビタミンC不足に陥ってしまう可能性もあります。
ビタミンC不足を予防するためには、日頃から野菜や果物を積極的に摂取することが重要です。
次章では、加熱に弱いビタミンCをできる限り壊すことなく調理する方法を紹介します。生野菜や果物からの摂取を意識する他、調理方法も工夫して、より効率よくビタミンCを摂取しましょう。
調理方法を工夫する
ビタミンCは加熱調理によって約50%に減少するため、調理の際は加熱時間を短くすることが重要です。
そのため、非加熱調理や電子レンジ調理を活用すれば、ビタミンCをより効率的に摂取できます。「茹でる・煮る」よりも「炒める・揚げる」ほうが比較的ビタミンC量を保ちやすいため、ぜひ参考にしてください。
さらに、ビタミンCは水に溶けだす性質を持つため、汁物のように煮汁ごと食べる料理であれば、ビタミンCを逃さず摂取できます。
食材の中で効率的にビタミンCを摂取できる代表例は、「じゃがいも」です。通常、ビタミンCは熱に弱いですが、じゃがいもに多く含まれるでんぷんがビタミンCを保護し、分解を防ぐ働きをします。この働きによって、加熱時のビタミンC減少量が抑えられ、効率的な摂取が可能となります。
毎日摂取する
前述のとおり、ヒトはビタミンCを体内で合成できず、さらに食事から摂取した分も余剰分は尿と一緒に排出されます。
つまり、ビタミンCは体内に貯めておくことができないため、一度の食事から摂取しようとせず、日々栄養バランスの良い食生活を意識してビタミンCを摂取することが大切です。
栄養バランスの整った食事を意識する
ビタミンCは、バランスの良い食事を心がけていれば基本的に、不足の心配はありません。
なお、「バランスの良い食事」とは、主食・主菜・副菜がそろう食事です。
国立健康・栄養研究所によれば、「主食・主菜・副菜がそろう食事」の回数が増えると、ビタミンCをはじめ、ビタミンB1、ビタミンA、カルシウム、鉄の摂取が適正でない方が減る傾向があるようです※。
ビタミンCに限らず、様々な食材から栄養素を摂取しましょう。
※出典:国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所「バランスの良い食事をとるために」
栄養バランスの良い献立に悩んだら「未来献立®」の活用がおすすめ
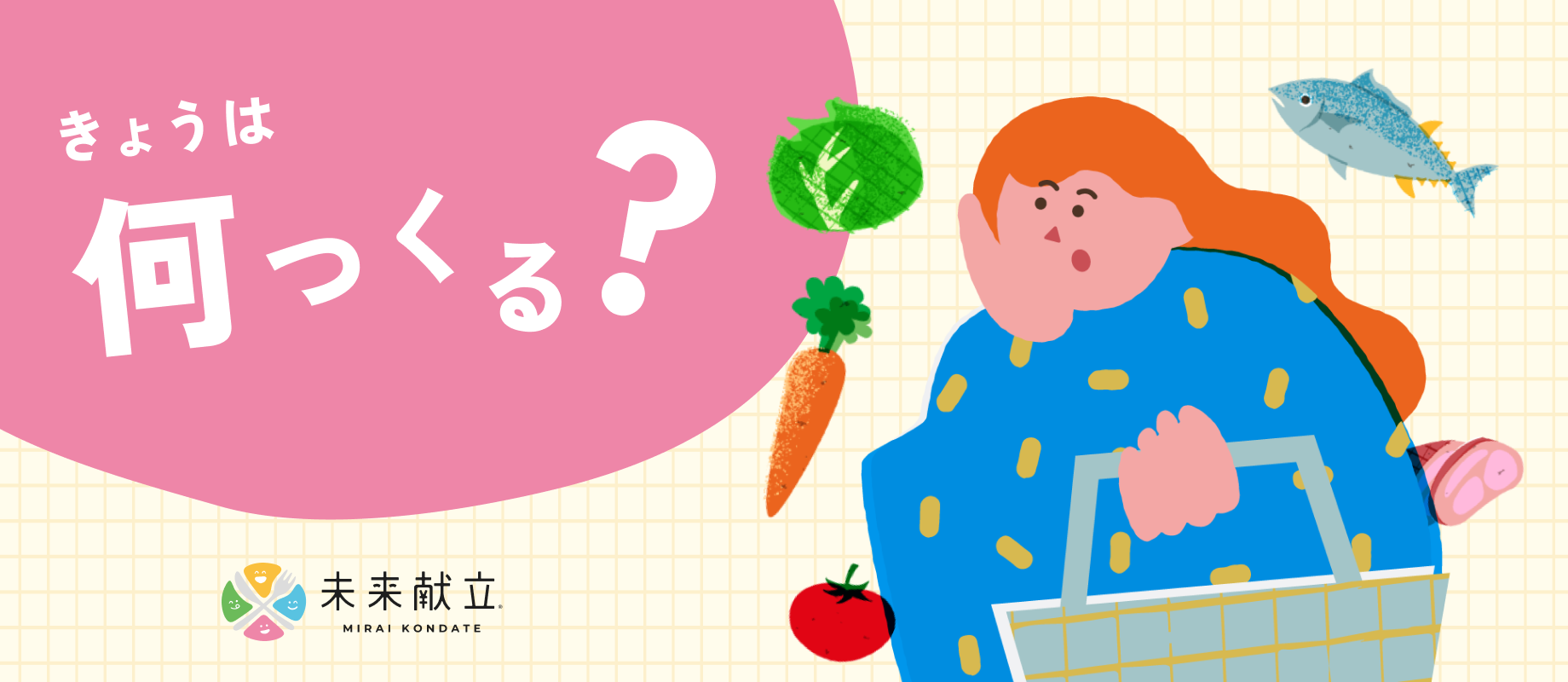
ビタミンCを十分に摂取するには、バランスの良い食事が基本です。主菜・主食・副菜のそろった献立を心がけていれば、基本的に、不足の心配はありません。
とはいえ、毎日主食・主菜・副菜がそろった栄養バランスの良い献立を考えるのは簡単ではなく、お悩みの方もいるでしょう。
そこでおすすめなのは 【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】考え方です。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、具体的にどんな食事にしたら良い?」と悩む場合は、献立提案サービス「未来献立®」をぜひお試しください。
「未来献立®」は、栄養バランスを考えた献立をまとめて提案するサービスです。苦手な食材を3つまで登録できる他、お気に入り登録機能などもあり、自分や家族の好みにあわせた活用が可能です。
また、「ツジツマ献立」では前日食べたものの傾向にあわせて、これからの食事でツジツマをあわせる献立をご提案します。栄養バランス計算済みの献立で、毎日の食事を無理なく整えましょう。
ビタミンCの摂取を意識して健康的な毎日を
ビタミンCは、免疫力の向上や体の調子を整えるために必要な栄養素です。体内で合成できないため、毎日の食事から意識して摂取しましょう。
ビタミンCを含め、栄養バランスの整った献立を立てるためには、ぜひ「未来献立®」の活用をご検討ください。

監修者
金丸 利恵(かなまる りえ)
おうちごはん研究家、管理栄養士、分子栄養学カウンセラー
大手企業での栄養士業務、レシピ開発を担当。保健指導では2000名以上の食事指導を行う。その後独立し、料理教室を主宰し、食育やダイエットサポートなどあらゆる世代の食と健康に関わる。「食べることは、生きること」をモットーに、栄養指導やセミナーを通じて、食と栄養の大切さを伝えている。スーパーで買える身近な食材で、健康的に美味しく簡単に作れるレシピに定評がある。
 献立提案サービス
献立提案サービス