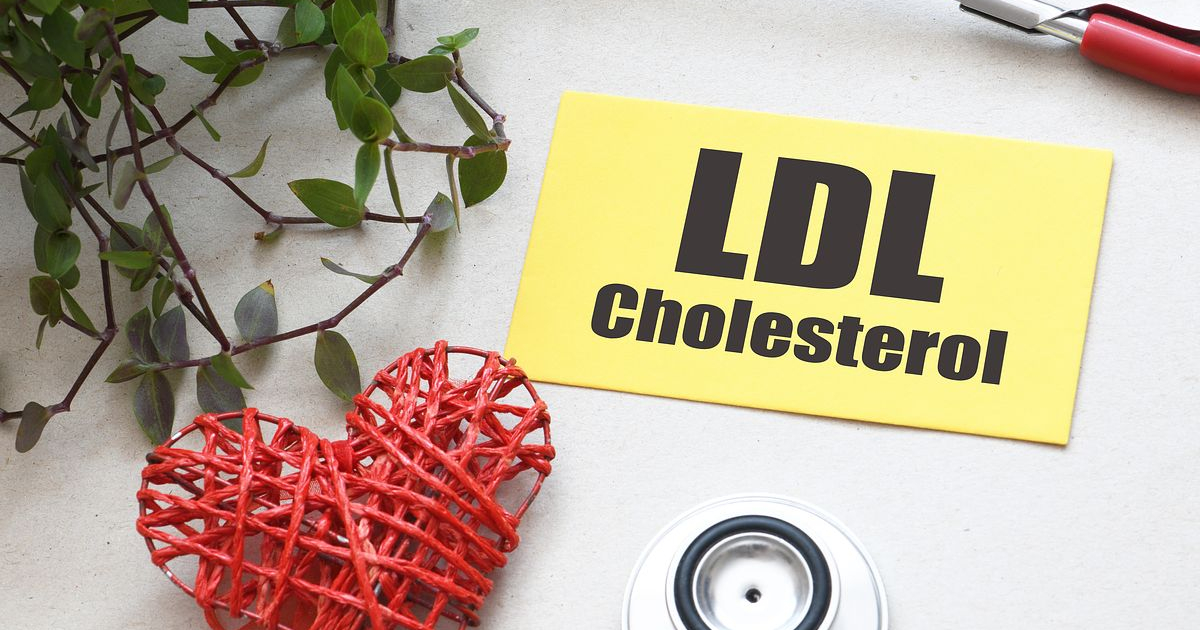炭水化物の制限は本当に正解?食べ物選びから1日の健康的な摂取目安量まで徹底解説

「炭水化物は太る」「糖質制限をした方が健康的」など、炭水化物に関する様々な情報が飛び交っています。
しかし、炭水化物は私たちの脳や体を動かすために欠かせない重要な栄養素です。極端な制限は疲労感や思考力の低下を招く可能性があるため、必要量の摂取が大切ですが、反対に過剰摂取すると肥満や生活習慣病のリスクを高める場合もあります。
健康的な生活を送るためには、どのくらいの量を、どのように摂取すれば良いのでしょうか。
この記事では、炭水化物の基礎知識から、年齢・性別に応じた適切な摂取量、効率的な摂り方まで、毎日の食生活に役立つ情報をご紹介します。炭水化物との上手な付き合い方を、チェックしましょう。
なお、炭水化物を含め、栄養バランスの整った食事を意識したい場合は、ぜひ無料の献立提案アプリ「未来献立®」を活用してみてください。
炭水化物とは
炭水化物は、私たちの体に必要不可欠な三大栄養素のひとつです。
三大栄養素とは、炭水化物・たんぱく質・脂質をさし、日々の生活に必要なエネルギーを生み出す重要な栄養素です。体を動かすために必要な燃料として働くため、バランスの良い食事を通じて適切に摂取する必要があります。
たんぱく質と脂質については、以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
炭水化物は脳や体を動かす働きをもつ
私たちの体にとって、炭水化物は重要なエネルギー源として機能しています。体内に取り込まれた炭水化物は、ブドウ糖として脳や赤血球、神経組織などの重要な組織に供給され、それぞれの組織が正常に機能するために使われます。
特に脳は、常にブドウ糖を必要とする組織として知られており、集中力や思考力を維持するためにも欠かせません。また、運動時の筋肉量維持にも炭水化物は重要な役割を果たしており、極端な制限は筋肉の分解を促進する可能性があるため注意が必要です。
炭水化物と糖質の違いは?
炭水化物と糖質の違いに疑問を持つ方は多いですが、「炭水化物=糖質+食物繊維」の関係性であり、炭水化物とは糖質と食物繊維の総称です。
炭水化物のうち、実際に体内でエネルギー源として利用されるのは糖質で、1グラムあたり約4キロカロリーのエネルギーを生み出します。
一方、食物繊維は消化されにくい性質を持ちますが、腸内環境を整えるなど別の重要な役割を果たします。
炭水化物の摂取量目安

炭水化物は、1日に摂取する総エネルギー量の50~65%を占めることが推奨されています。同じ三大栄養素であるたんぱく質(13~20%)や脂質(20~30%)と比較し、最も大きな割合です。
具体的な摂取量は、年齢や性別、身体活動レベルによって異なります。
| 年齢等 | 男性の目標量 | 女性の目標量 |
|---|---|---|
| 0〜5(月) | - | - |
| 6〜11(月) | - | - |
| 1~2(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 3~5(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 6~7(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 8~9(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 10〜11(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 12〜14(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 15〜17(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 18〜29(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 30〜49(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 50〜64(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 65〜74(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 75歳以上(歳) | 50〜65 | 50〜65 |
| 妊婦 | - | 50〜65 |
| 授乳婦 | 50〜65 |
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
例えば、身体活動レベルが「ふつう(座位中心の仕事だが、通勤や家事程度は行う)」の30代女性のケースを見てみましょう。
この場合、基礎代謝基準値は21.7kcal/kg、活動指数は1.75です。身長160cmと仮定し、適正体重(約56.3kg)で計算すると、1日の必要エネルギー量は約2,140kcalです。
- 適正体重=22×(1.60m)2 = 約56.3kg
- 基礎代謝量=約56.3kg×21.7kcal = 約1,222kcal
- 1日の必要エネルギー量=約1,222kcal×1.75 = 約2,139kcal
このうち炭水化物からは50~65%、つまり約1,070~1,390kcalを摂取することが望ましいとされています。
炭水化物を含む主な食品一覧
私たちの身近にある食品に含まれる主な炭水化物を、分類別にご紹介します。なお、以下の数値は食品100gあたりの炭水化物含有量を示しています。
●穀類
| 食品名 | 成分量100gあたり(g) |
|---|---|
| とうもろこし コーンフレーク | 83.6 |
| えんばく オートミール | 69.1 |
| とうもろこし ポップコーン | 59.6 |
| こむぎ パン類 フランスパン | 57.5 |
| こめ 水稲めし 精白米 うるち米 | 37.1 |
| こめ 水稲めし 発芽玄米 | 36.4 |
| こめ 水稲めし 玄米 | 35.6 |
●いもおよびでん粉類
| 食品名 | 成分量100gあたり(g) |
|---|---|
| じゃがいも 塊茎 皮なし フライドポテト(市販冷凍食品を揚げたもの) | 32.4 |
| じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 19.2 |
| タピオカパール ゆで | 15.4 |
| ごま豆腐 | 9.1 |
| こんにゃく しらたき | 3.0 |
●砂糖および甘味類
| 食品名 | 成分量100gあたり(g) |
|---|---|
| 車糖 上白糖 | 99.3 |
| 車糖 三温糖 | 99.0 |
| 黒砂糖 | 90.3 |
| はちみつ | 81.9 |
| メープルシロップ | 66.3 |
| 黒蜜 | 50.5 |
●豆類
| 食品名 | 成分量100gあたり(g) |
|---|---|
| あずき あん こし練りあん(もなかあん) | 68.6 |
| だいず 全粒・全粒製品 きな粉(砂糖入り) | 63.9 |
| えんどう 塩豆 | 61.5 |
| えんどう グリンピース(揚げ豆) | 58.8 |
| だいず 全粒・全粒製品 いり大豆 黄大豆 | 33.3 |
| だいず 納豆類 糸引き納豆 | 12.1 |
●果実類
| 食品名 | 成分量100gあたり(g) |
|---|---|
| パインアップル 砂糖漬 | 86.8 |
| マンゴー ドライマンゴー | 84.9 |
| ぶどう 干しぶどう | 80.3 |
| かき 干しがき | 71.3 |
| いちご ジャム 高糖度 | 63.3 |
| プルーン 乾 | 62.3 |
| バナナ 生 | 22.5 |
| りんご 皮つき 生 | 16.2 |
| かき 甘がき 生 | 15.9 |
| さくらんぼ 国産 生 | 15.2 |
出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
出典:文部科学省「食品成分データベース」
特に乾燥果実や精製された穀類、甘味料に炭水化物が多く含まれることがわかります。同じ食品群でも加工方法や状態によって含有量が大きく異なるため、食品選びの際は意識してみてください。
炭水化物を効率的に摂取するポイント
炭水化物をより効率的に体内で活用するためには、ビタミンB1との組み合わせを意識することがポイントです。ビタミンB1は糖質の代謝に重要な役割を果たし、不足すると代謝がうまく進まず、余分な糖質が脂肪として蓄積されやすくなります。
ビタミンB1を含むのは、豚肉、ナッツ類、大豆、ほうれん草やカリフラワーなどが代表的な食材です。普段の食事で、白米ではなく玄米や全粒粉パン、雑穀パンを選ぶと、自然とビタミンB1を摂取できるでしょう。
炭水化物の過不足は体へ悪影響をおよぼす可能性がある

炭水化物は、摂取量が多すぎても少なすぎても、体に様々な影響をおよぼす可能性があります。過剰摂取は肥満や生活習慣病のリスクを高め、極端な制限は体力や集中力の低下を招く可能性があることも懸念点です。
健康的な生活を維持するために、適切な摂取量を意識しましょう。
炭水化物が不足すると起こる症状
炭水化物が不足すると、体に様々な不調が現れる可能性があります。深刻な影響が出やすいのは、脳機能と身体エネルギー面です。
脳は1日に約120gのブドウ糖を消費しますが、このエネルギー源を唯一炭水化物に依存するため、不足すると重要な機能に支障をきたす可能性があります。
例えば、体内のグリコーゲン(エネルギー源)の不足で著しい疲労を感じやすくなります。また、脳へのブドウ糖供給の減少で思考力や判断力が低下し、集中力が続かなくなることがある他、夜間の脳の栄養不足により、睡眠の質に影響が出ることもあるでしょう。
加えて体内の糖質が不足すると、肝臓が代わりにたんぱく質から糖をつくり出そうとします。この過程で有害なアンモニアが生成され、これを処理する肝臓への負担が増大します。
炭水化物ダイエットによる過剰な糖質制限には注意
話題の炭水化物制限ダイエットですが、過度な制限は健康上のリスクを伴う可能性があります。
制限によって短期的には体重が減少したように見えても、体内の水分量が減少している場合が多く、本質的な体重減少とは異なります。
さらに、急激な減量は、体が飢餓状態だと認識してエネルギーを蓄えようとする働きが強まり、制限を緩めた途端に大きくリバウンドするリスクも高まるでしょう。
そのため、急激な糖質制限は避け、適切な糖質制限を心がけることが大切です。完全に糖質を絶つのではなく、質の良い炭水化物を適量摂取する方法の検討をおすすめします。
ダイエットを考える時に注意したいポイントは以下の記事でも紹介しているため、ぜひあわせてご覧ください。
炭水化物の過剰摂取にも注意が必要
炭水化物の摂りすぎは、体重管理の面だけでなく、健康面でもリスクになり得ます。
人が食事から摂取した炭水化物は消化されてブドウ糖となり、体内でエネルギーとして利用されます。
しかし、必要量以上に摂取すると、余分なブドウ糖は中性脂肪に変換され、皮下脂肪や内臓脂肪として体内に蓄積されるのです。
特に内臓脂肪の蓄積は要注意です。過剰な内臓脂肪は、血糖値の上昇や血中脂質の異常をもたらし、結果として糖尿病や動脈硬化などの深刻な生活習慣病を引き起こすリスクを高めます。
栄養バランスを意識したメニューが大切
炭水化物の適切な摂取には、バランスの取れた食事を意識することが重要です。
理想的な食事とは、「主食」「主菜」「副菜」をバランスよく組み合わせた日本型食生活です。具体的には、ご飯やパンなどの主食、肉や魚を中心とした主菜、野菜やきのこ類を使用した副菜を、ひとつの献立の中に揃えることを心がけましょう。
しかし、毎食完璧な献立を用意することはなかなか難しく、現実的ではありません。「1食1食を完璧にする」という考え方ではなく、「次の食事で調整する」という柔軟な発想が大切です。
例えば、朝食で主菜が不足していた場合は、昼食でたんぱく質を多めに摂取するなど、1日トータルでバランスを整えるよう意識しましょう。
1日の栄養バランスに悩んだら「未来献立®」の活用がおすすめ!
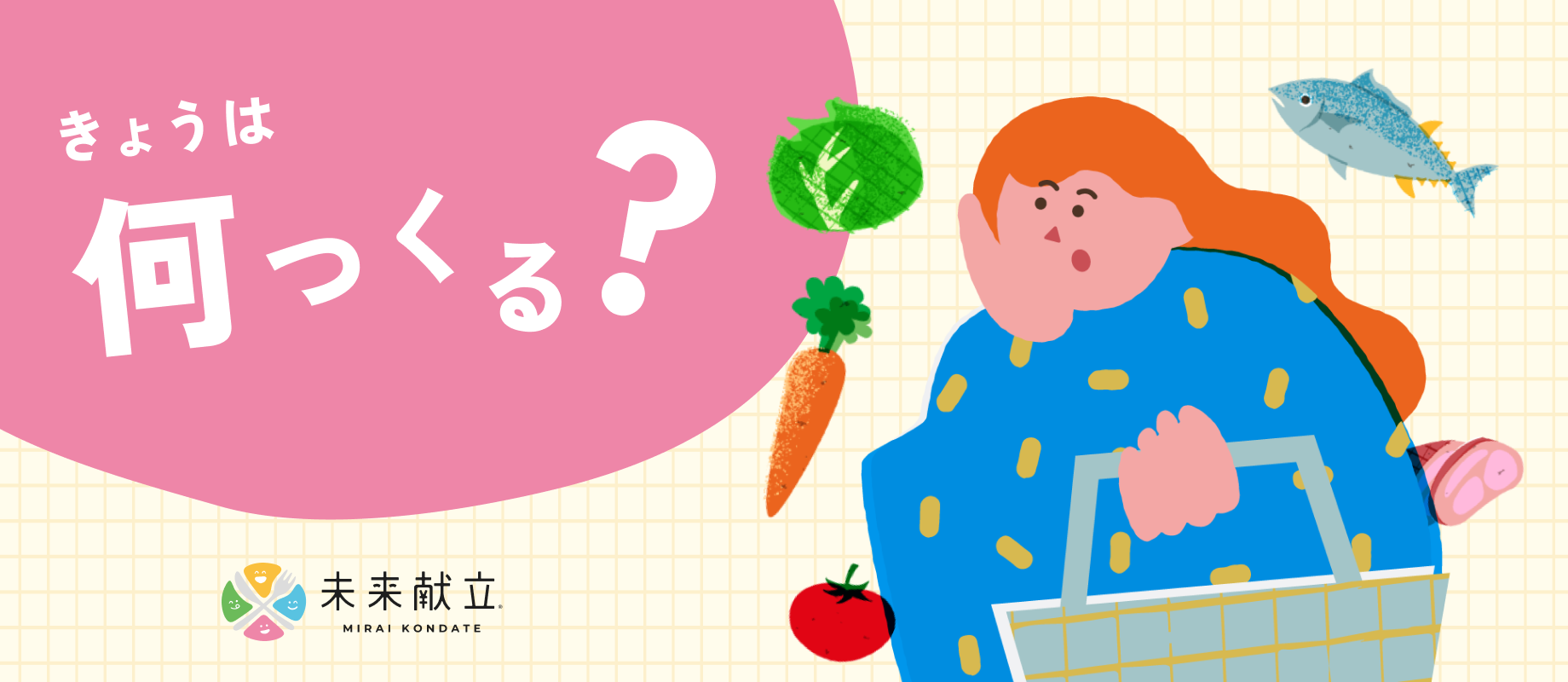
ここまで読んで、炭水化物を含めた献立の考え方や栄養バランスの整った食事の大切さはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせること】でも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
「未来献立®」は、栄養バランスが考えられた献立をまとめてご提案する献立提案サービスです。肉や魚など、バリエーション豊富なメニューをご用意しているので、「炭水化物を含めた栄養バランスを考えるのは大変」と感じる時に役立ちます。
また、「未来献立®」では食べたものに応じて、「ツジツマ献立」としてツジツマを合わせたメニューをご提案するので、つい好きなものを食べ過ぎた時でも安心です。
日々の献立を考えることが苦手に感じる方や、より栄養バランスの整った食事にしたい方は、ぜひ活用をご検討ください。「未来献立®」を活用すると、毎日の食事の栄養バランスにより気軽に向き合えるでしょう。
炭水化物は健康的な食生活に欠かせない栄養素
炭水化物は時として「太る原因」として敬遠されやすいですが、実は私たちの健康的な生活に欠かせない重要な栄養素のひとつです。
健康的な食生活のために心がけたいのは、1日の総エネルギー量の50~65%を炭水化物から摂取することです。また、より効率的な代謝のために、豚肉やナッツ類などビタミンB1を含む食品と組みあわせて摂取するのもおすすめです。
日々の食事では、主食・主菜・副菜を基本としたバランスの良い食事を心がけましょう。毎食完璧である必要はありません。1食で栄養バランスが偏っても、次の食事で調整する柔軟な考え方を持つことが長続きのコツです。
また、毎日の献立づくりに悩んだ時は、「未来献立®」を活用しましょう。栄養バランスを考慮した献立の提案で、より手軽に健康的な食生活を実現できます。

監修者
金丸 利恵(かなまる りえ)
おうちごはん研究家、管理栄養士、分子栄養学カウンセラー
大手企業での栄養士業務、レシピ開発を担当。保健指導では2000名以上の食事指導を行う。その後独立し、料理教室を主宰し、食育やダイエットサポートなどあらゆる世代の食と健康に関わる。「食べることは、生きること」をモットーに、栄養指導やセミナーを通じて、食と栄養の大切さを伝えている。スーパーで買える身近な食材で、健康的に美味しく簡単に作れるレシピに定評がある。
 献立提案サービス
献立提案サービス