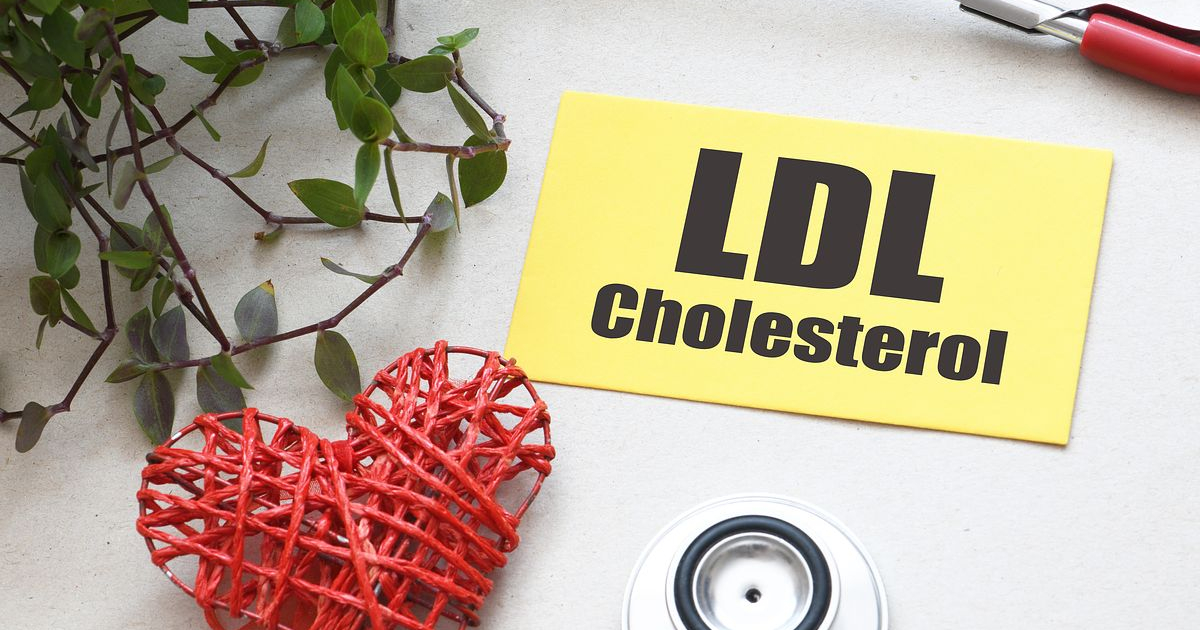鍋に入れる具材は?定番・変わり種の材料やそれぞれの栄養も解説

鍋は冬の定番として親しまれており、アレンジ次第で季節を問わず楽しめる手軽で魅力的な料理です。野菜、肉、魚介類など、多様な食材をひとつの鍋で楽しめるため、栄養バランスに優れた料理ができます。
この記事では、鍋料理に欠かせない定番の具材や、おすすめの食材をカテゴリー別に詳しく紹介します。それぞれの具材の特徴や栄養価、おいしい食べ方のコツなども紹介するため、ぜひ参考にしてください。
なお、栄養バランスを考えるのが苦手で、日々の献立づくりに悩む方には、「未来献立®」もおすすめです。「未来献立®」とは、おいしさと栄養バランスどちらも叶えた献立をまとめて(最大8日間分)ご提案するサービスです。気になる方は以下から詳細をご確認ください。
鍋に入れる具材や順番について
鍋料理の具材は、野菜、肉、魚介、その他に大別できます。
鍋をおいしく仕上げるコツは、火の通りにくい具材から順に入れていくことです。
とくに火が通りにくく、味をしっかり染み込ませたい具材の代表例は根菜類です。次に、だしの出る鶏肉や魚介類、しっかり中まで温めたい豆腐類を入れていきましょう。
火を通しすぎると固くなりやすい牛肉や牡蠣などは、つゆが沸騰し中火にしたタイミングで入れることをおすすめします。最後に軽く火を通すだけでおいしい葉野菜を加えて、完成です。
具体的に以下の順番で入れることで、それぞれの食材の特性を活かして鍋料理を楽しめるでしょう。
【鍋に入れる具材の順番一例】
- 大根・にんじん・白菜(白い部分)・ごぼう
- 鶏肉・えび・きのこ類・木綿豆腐
- 牛肉・豚肉・つみれ・牡蠣
- ねぎ・春菊・白菜(葉の部分)・水菜・もやし・絹ごし豆腐
【野菜編】鍋に入れる定番・おすすめの具材

鍋料理に欠かせない野菜の具材を紹介します。
【鍋に入れる定番・おすすめの野菜】
- 白菜
- 長ねぎ
- 玉ねぎ
- キャベツ
- 大根
- 人参
- ニラ
- 水菜
- 春菊
- もやし
これらの野菜は幅広い種類の鍋に合わせやすく、栄養バランスも整えやすいのが特徴です。
野菜が主役の鍋としては、寄せ鍋やちゃんこ鍋などがあります。具材の切り方も重要で、例えば白菜は食べやすい大きさに、ねぎは斜め切りにするなどの工夫で、食感や味の染み込み具合が変化します。
以下より、各野菜の特徴や栄養、おいしい食べ方を詳しく紹介します。鍋のレシピについては以下の記事で紹介しているため、気になる方はあわせてご覧ください。
白菜
白菜は鍋料理定番の具材として親しまれています。白菜にはビタミンC・K、カリウム、葉酸など、様々な栄養素がまんべんなく含まれているのが特徴です。
これらの栄養素は体の抵抗力を高めたり、骨を丈夫にしたり、血圧調整を助けたりと、健康維持に重要な役割を果たします。特に冬場の鍋料理で白菜を摂ることで、風邪予防にも役立つでしょう。
白菜は全体をざく切り、もしくは芯の部分のみ細切りがおすすめです。食感を残したい場合はざく切り、子どもの食べやすさを重視する場合は細切りにするなど、工夫しましょう。
長ねぎ
長ねぎは、白菜と並んで鍋料理では広く使われる定番の具材です。
長ねぎにはビタミンA・Cや硫化アリルが含まれています。体温を上昇させる作用や殺菌作用があり、風邪の予防に役立つことが期待されています。
長ねぎの白い部位は、とくに鍋との相性が良いです。甘みと辛味のバランスがほど良くなる斜め薄切りや、歯ごたえも残る筒切りなど、好みに合わせて切り方を調整しましょう。
玉ねぎ
玉ねぎは、多くの鍋料理に溶け込む万能な野菜のひとつです。玉ねぎの甘みと食感が様々な具材と相性が良く、鍋の味わいを豊かにします。
玉ねぎには、ビタミンB1の吸収を助ける硫化アリルという成分が含まれています。食欲増進や動脈硬化予防にも効果があり、血液をサラサラにする野菜としても有名です。ビタミンB1が豊富な豚肉との組み合わせると、疲労回復やストレス解消に役立ちます。
鍋に入れる際は、くし形切りにするのがおすすめです。加熱時間に応じて食感を調整しやすく、スープにもほどよく溶け込みます。
キャベツ
キャベツは鍋料理に使えば、大量消費に役立ちます。
キャベツに含まれる「ビタミン様作用物質」は、胃や腸の調子を整えるといわれています。煮ると水に溶け出てしまうため、汁ごといただくのがおすすめです。
部位によって異なる栄養素が含まれているのも特徴で、外葉と芯の周りにはビタミンCが、外葉の緑の濃い部分にはビタミンAが豊富です。免疫力の向上や肌の健康維持に貢献します。
鍋料理では、千切りにしてヘルシーなしゃぶしゃぶに加えるのもおすすめです。シャキシャキとした食感とさっぱりとした味わいが、肉や他の具材とよく合います。熱に弱く水に溶け出てしまう栄養素もあるため、鍋はしめまでいただいて、スープに溶け出した栄養を丸ごといただきましょう。
大根
大根は鍋料理に欠かせない具材のひとつで、鍋を囲む時間が経つにつれて、汁の味がしっかりと染み込み、より味わい深くなるのが魅力です。時間とともにうま味が増し、より味わい深くなるでしょう。
鍋に入れる際は、煮崩れを防ぐために面取りをすると良いでしょう。大きめに切る時は隠し包丁を入れると、火の通りを良くできます。
大根にはビタミンCや消化酵素のアミラーゼが含まれており、胸焼けや胃もたれの予防に効果的です。
大根の葉は固くて少しえぐみがあるため、鍋の具材には向かないかもしれません。しかし、カロテンやカルシウム、食物繊維が豊富に含まれているため、湯がいてからみじん切りにし、かつお節やしらすなどと甘辛く炒めてふりかけなどにするなど、捨てず活用することをおすすめします。
人参
人参は、味だけでなく見た目も引き立てる色合いが特徴的です。
人参に含まれるβカロテンは皮の近くに多く、体内で必要に応じてビタミンAに変換されます。免疫力を高める役割を果たすビタミンAは、油と調理すると吸収率が上がるので、肉や魚、油揚げなど脂質を含む具材と相性が良いです。
人参を調理する際は皮を薄めに剥くか、オーガニックのものなら、皮ごと食べると良いでしょう。薄めの半月切りや短冊切りにし、短時間で火が通るように考慮することも大切です。
ニラ
ニラは、鍋料理に彩りと香りを添える具材のひとつです。漢方薬としても知られており、冷え性の緩和や腸を整えるのに効果的な野菜です。硫化アリルが多く、血行を良くして胃腸の働きを良くします。
ビタミンAが豊富で体の抵抗力を高め、皮膚や粘膜を丈夫に保つため、体調を崩しやすい冬にぴったりの野菜です。
また、ビタミンB1、B2、E、K、Cに加えて、葉酸も豊富に含むため、まさに「マルチビタミン野菜」と呼ぶのにふさわしい具材です。ビタミンは、疲労回復や美肌効果、風邪予防、さらには認知機能の低下予防まで、幅広い健康効果が期待できます。
鍋料理にニラを加える際は、ざく切りにするのが一般的です。3〜4cm程度の幅に切ることで、食べやすくなるでしょう。
水菜
水菜はサラダの定番として知られていますが、実は鍋料理にも適した野菜です。火を通してもシャキシャキした歯ごたえがあり、細いのでスープの味が絡みやすく、おいしくいただけます。肉や魚の臭みを消す作用があり、鍋料理の具材としても人気があります。
水菜はβカロテンやビタミンC、Eを豊富に含みます。特に冬における風邪や肌荒れの防止、さらには疲労回復の効果も期待できるでしょう。
切るのが楽なところもポイントで、シャキシャキとした食感と鮮やかな緑色を保つためには、具材の中でも最後に鍋に入れるのがおすすめです。
春菊
春菊は、ビタミン類やカリウム、カルシウム、鉄などのミネラル、そして食物繊維が豊富に含まれています。ほうれん草や小松菜よりもβカロテンが多いのが特徴です。
カロテンには肌の抗酸化作用があるとされています。さらに春菊は、中国で「食べる風邪薬」と呼ばれています。春菊特有の香り成分が自律神経に作用し、胃腸の働きを促進したり、咳を鎮めたりする効果があるためです。
鍋に春菊を入れる際は、茎も一緒に使いましょう。茎にも栄養が豊富に含まれており、シャキシャキとした食感を楽しめます。
もやし
もやしは食物繊維が豊富で、整腸や便秘予防に役立ちます。他にも、ビタミンB群、ビタミンC、カリウム、アスパラギン酸など、様々な栄養素が含まれる野菜です。
低カロリーでありながら栄養価が高いもやしは、ダイエット中の方や健康志向の方にも嬉しい食材です。
もやしは、下処理の手間がかからずそのまま使えます。忙しい時の鍋料理に重宝するでしょう。シャキシャキとした食感とあっさりとした味わいが、他の具材とマッチします。
【肉編】鍋に入れる定番・おすすめの具材

鍋料理のメイン具材として欠かせない肉類は、種類や部位によって様々な味わいを楽しめます。ここでは、鍋に入れる定番・おすすめの肉類を紹介します。
【鍋に入れる定番・おすすめの肉類】
- 豚肉
- 鶏肉
- 牛肉
- つくね・つみれ・肉団子
肉が主役の鍋には、しゃぶしゃぶやすき焼き、もつ鍋などがあります。肉のうま味を存分に楽しめる上、野菜と組み合わせることで栄養バランスも整えやすいのが特徴です。
豚肉
鍋に入れる豚肉の部位の定番としては、肩ロース、もも、バラ、もつが挙げられます。それぞれに栄養や味わい、食感に特色があるため、鍋の味付けや自分の好みに合わせて選びましょう。
豚肉は主にビタミンB1が豊富です。疲労回復や脳の働きを助ける重要な栄養素で、寒さや疲れに負けない体づくりに役立ちます。
豚肉と相性の良い鍋料理としては、しゃぶしゃぶ、キムチ鍋、ミルフィーユ鍋などが挙げられます。
豚肉を鍋に入れる際は、薄切りにすると火の通りが良くなり、柔らかな食感を楽しめるでしょう。
鶏肉
鶏肉も部位によって栄養や味わい、食感にそれぞれ特色があるため、好みや鍋の種類に応じて選びましょう。
例えば、もも肉は加熱しすぎてもパサつきにくく、ぶつ切りや手羽先などは骨が付いているので、骨から出る濃厚な旨味が味わえます。
むね肉は、低カロリーでありながら、もも肉よりもたんぱく質が豊富です。また、イミダペプチドも豊富で、抗酸化作用や疲労回復に効果があるとされています。むね肉やささみは、長時間煮るとパサつくので気をつけましょう。
鶏肉は、寄せ鍋や水炊きと相性が良いです。鍋に入れる際は食べやすい大きさに切り分け、しっかり火を通しましょう。
牛肉
牛肉も、部位によって栄養や味わい、食感にそれぞれ特色があります。好みや鍋の種類に応じて選びましょう。
鍋料理では、リブロースとバラが特に人気です。リブロースは、きめの細かい肉質で柔らかく、しゃぶしゃぶやすき焼きに合います。バラは赤身と脂肪が層になった三枚肉で濃厚な風味が特徴であり、すき焼きや牛鍋などの煮込み系の鍋料理に適しています。
牛肉は、血液中の赤血球を作る鉄と亜鉛が豊富です。造血に必要なビタミンB12も含むので、貧血予防や疲労回復に効果が期待できるでしょう。
鍋に入れる際は薄切りにすると火の通りが良くなるため、柔らかな食感を楽しめます。
つくね・つみれ・肉団子
つくね・つみれ・肉団子は、鍋料理の中でも人気の高い具材です。単に肉や魚肉だけでなく、野菜やその他の食材が練り込まれています。
例えば、つくねは鶏ひき肉に軟骨や野菜などが加えられることが多く、つみれは白身魚のすり身にれんこんやごぼうが入ることがあります。食感や風味の良さを高める食材として楽しめるでしょう。
つくね・つみれ・肉団子の魅力は、だしが染み込みやすい点にもあります。もともとの食材のうま味と鍋の出汁が絶妙に絡み合い、おいしく食べられる一品となるのです。
【魚介編】鍋に入れる定番・おすすめの具材

鍋料理に彩りとうま味を加える魚介類は、多様な味わいと栄養価で人気の具材です。ここでは、鍋に入れる定番・おすすめの魚介類を紹介します。
【鍋に入れる定番・おすすめの魚介類】
- カニ
- エビ
- タラ
- 鮭
- ほたて
- 牡蠣
魚介が主役の鍋としては、寄せ鍋や石狩鍋、海鮮鍋などがあります。魚介の出汁が効いた鍋で身体を温めましょう。
カニ
カニは、鍋料理に豪華さと深いうま味をもたらす人気の具材です。加熱するとやわらかくほぐれやすくなり、味もより良くなるため、鍋料理に適した食材です。
カニは、高たんぱくで低脂質、かつ旨味が強くて満足感があるので、ダイエット中の方には特におすすめです。
赤い色の成分であるアスタキサンチンは抗酸化作用に優れています。肝臓の働きを助けるタウリンも豊富です。タウリンは水に溶けやすいので、カニの旨味を煮だした汁もしっかりいただいてください。
カニを鍋に入れる際は、他の具材と一緒に煮込みすぎないよう注意しましょう。
エビ
エビも、鍋料理に彩りと豊かな風味をもたらす人気の具材です。鍋に入れる際は、殻、しっぽ、足や背わたをあらかじめ取っておくと、より食べやすくなります。
エビは主にたんぱく質、ビタミンE、カルシウム、アスタキサンチン、タウリンが豊富です。たんぱく質は筋肉や臓器の構成に不可欠で、ビタミンEは抗酸化作用があり、血行促進に役立ちます。カルシウムは骨や歯の健康に重要です。
エビは比較的短時間で火が通るため、鍋に入れるタイミングに注意しましょう。他の具材がある程度煮えてから加えると、エビの食感と風味をほどよく楽しめます。
タラ
タラは鍋料理におすすめの魚介類のひとつで、特にたんぱく質とビタミンDが豊富です。たんぱく質は筋肉や臓器の形成に不可欠で、代謝の調節にも関わる重要な栄養素です。ビタミンDはカルシウムの吸収を促進し、骨の健康維持に役立ちます。
タラは身が崩れやすい特徴があるため、身崩れしないテクニックを覚えておきましょう。例えば、タラに薄く片栗粉をまぶしたり、90℃のお湯で短時間湯引きして氷水で締めたりする方法が効果的です。鍋に入れても身崩れせず、本来の食感を楽しめます。
タラはもともと淡白な味わいのため、様々な種類の鍋料理に適しています。寄せ鍋や味噌鍋など、幅広い味付けの鍋に合わせやすいのが特徴です。ただし、時に感じられる臭みが気になる場合は、塩を振って事前に取り除いておくことをおすすめします。
鮭
鮭は、アスタキサンチンやビタミンB6、ビタミンD、DHA、EPAなど、豊富な栄養素が含まれています。特にビタミンB6には、健康な皮膚や髪の維持、貧血予防、脂肪肝予防、さらにはPMS(月経前症候群)の症状緩和にも効果があるとされています。
鮭をよりおいしく鍋に入れるためには、あらかじめ臭みを取る下処理がおすすめです。塩を振る、牛乳に漬ける、流水で洗い流すなどの方法があります。いずれもキッチンペーパーなどで水気をしっかいりふき取りましょう。下処理を行うことで、鮭のおいしさをより楽しめるでしょう。
煮すぎると身が固くなる可能性があるため、鮭を鍋に入れる際は、他の具材がある程度煮えてから加えることをおすすめします。
ほたて
ほたては、肉厚の食感と豊かなうま味が魅力の具材です。貝類の中でもクセが少なく味わいがまろやかなため、他の魚介類との相性が良く、様々な種類の鍋料理に適しています。
ほたてはたんぱく質が豊富で脂質は少ないのが特徴です。疲労回復に効果があるとされるタウリンや、睡眠の質を向上させるグリシンも含まれているとされ、健康面でも優れた食材です。
牡蠣
牡蠣は鍋料理に深いうま味と豊かな栄養をもたらす人気の具材ですが、おいしさを引き出すには適切な下処理が欠かせません。
例えば、片栗粉をまぶしてしっかり洗う方法があります。牡蠣は火を通しすぎると硬くなってしまう傾向がありますが、事前に下処理を行うことで、ふっくらとした食感を保ちやすくなります。
栄養面では、牡蠣は特にビタミンB12、亜鉛、グリコーゲン、タウリンが豊富です。中でも身体を構成する成分として欠かせない亜鉛は、推奨量を上回る量を誇ります。グリコーゲンはエネルギー源として働き、タウリンは肝機能の向上や高血圧予防に効果があるなど、健康維持のためにも摂取したい食材です。
【その他】鍋に入れる定番・おすすめの具材
鍋料理には、野菜や肉、魚介類以外にも、様々な具材が使われます。ここでは、その他の定番・おすすめの具材を紹介します。
【鍋に入れる定番・おすすめのその他の具材】
- 豆腐
- きのこ類
- こんにゃく・糸こんにゃく・しらたき
- 餅・餅巾着
これらの具材は、主に寄せ鍋のような定番の鍋料理に使われます。寄せ鍋は、様々な具材をひとつの鍋に「寄せ集める」ことから名付けられた鍋料理です。幅広い具材が調和して独特の味わいを生み出します。
豆腐
豆腐は多くの鍋料理に欠かせない定番具材のひとつです。鍋に入れる際は、焼き豆腐や木綿豆腐のような崩れにくいタイプがよく使われます。特に焼き豆腐は、出汁や調味料が染み込みやすい特性があり、すき焼きのような味の濃い鍋料理にぴったりです。
栄養面ではたんぱく質、ビタミン、ミネラル、カルシウムが豊富で、特にカルシウムは焼き豆腐に多く含まれます。焼き豆腐は木綿豆腐を水切りして焼き目をつけたもので、しっかりとした食感が特徴です。
鍋に豆腐を入れる際は、他の具材がある程度煮えてから加えると良いでしょう。豆腐が崩れすぎることなく、適度に出汁を吸っておいしく仕上がります。
きのこ類
きのこ類は様々な種類があり、鍋料理にはしいたけ、しめじ、まいたけ、エリンギ、えのきが使われることが多く、それぞれが独特の食感と風味を持っています。
きのこ類を鍋に入れることで独特のうま味が染み出し、鍋全体の味わいがより豊かになるでしょう。
栄養面では特に食物繊維が豊富で、腸内環境を整えるのに役立ちます。また、ビタミンB群やビタミンD、カリウム、リンなどのミネラルも多く含まれているため、栄養バランスの良い鍋料理をつくるのにおすすめです。
こんにゃく・糸こんにゃく・しらたき
こんにゃく、糸こんにゃく、しらたきは、鍋料理に独特の食感と栄養を加える人気の具材です。こんにゃくをそのまま使うとえぐみや臭みがありますが、事前に茹でたり塩もみしたりすることで、不快な要素を取り除くことができます。
こんにゃくの味の染み込みをよくするコツとして、隠し包丁を入れるのがおすすめです。細かく切り込みを入れることで、鍋のスープがよく浸透し、よりおいしく仕上がります。
糸こんにゃくやしらたきは、結ぶことでよりスープが染み込みやすくなるでしょう。
こんにゃくはカルシウムと食物繊維の供給源です。日本人の食生活で不足しがちな栄養素を、低カロリーで効率的に摂取できる食材として注目されています。
餅・餅巾着
餅や餅巾着は、鍋料理に独特の食感と満足感をもたらす人気の具材です。食感がなくなるほどに溶けてしまわないよう、鍋の最後に入れましょう。
ほどよく溶けた餅に他の具材を絡めて食べるのも、鍋料理の醍醐味のひとつです。
一方、餅本来の食感を楽しみたい場合は、餅巾着を使うのも良いでしょう。餅巾着は周りの具材と絡まりにくいため、餅の食感を保ったまま鍋料理を楽しむことができます。
餅はご飯よりもカロリーと炭水化物が豊富です。エネルギー源として効果的であり、特に寒い季節の鍋料理では体を温める働きも期待できます。
栄養バランスの整った献立を考えたいなら「未来献立®」を活用しよう
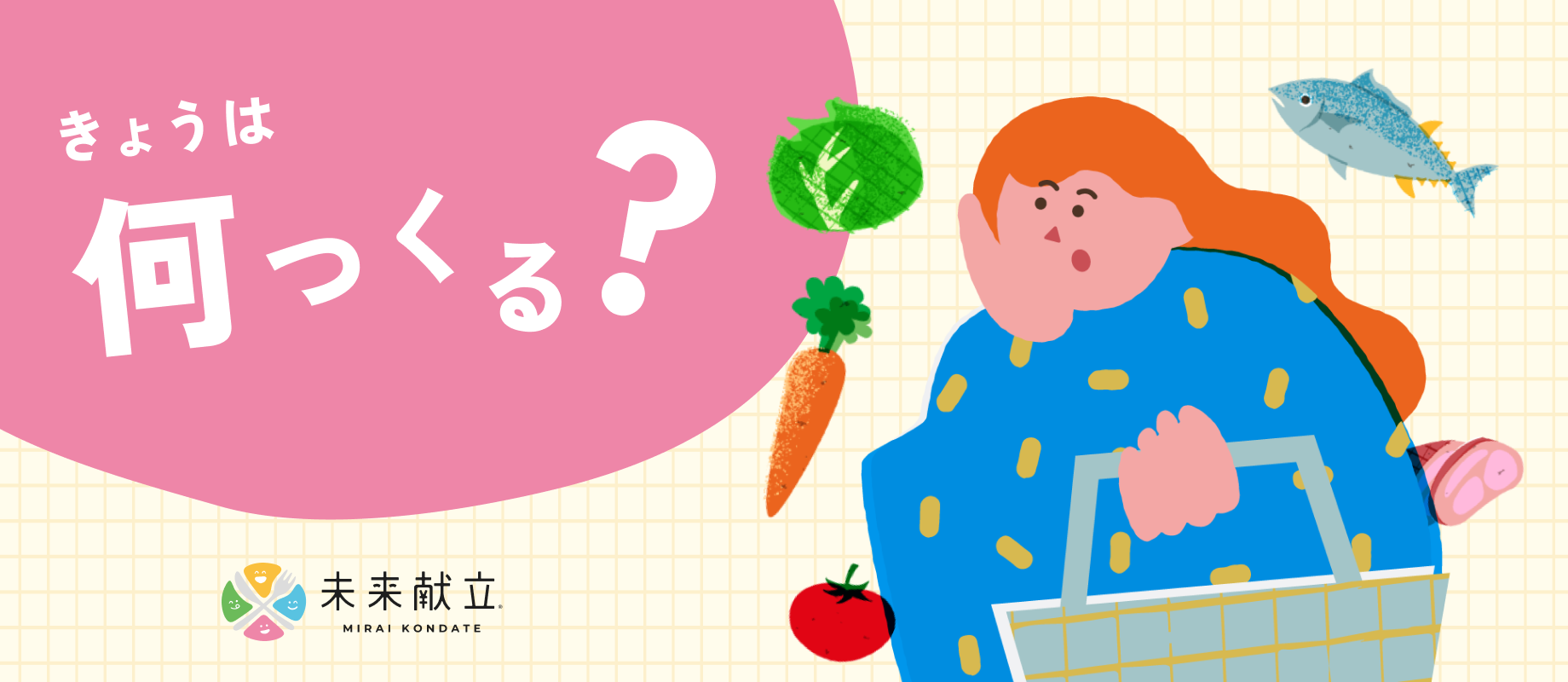
様々な栄養素を含む食材を一度に摂取しやすい鍋料理は、栄養バランスを考えたい人にもおすすめです。しかし、健康的な食生活を目指すには、鍋だけでなく毎食の栄養バランスを考える必要があります。
忙しい中、毎日栄養バランスの整った献立を考えるのは難しいかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧を目指さなくても良いと思えば、少し気が楽になりませんか?
「でも、具体的にどんな食事にすればいいの?」と悩んだら、献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
「未来献立®」は、栄養バランスが考えられた献立をまとめて最大8日間分ご提案する献立提案サービスです。バリエーション豊富なメニューをご用意しているため、「鍋以外の料理で栄養バランスを考えるのは大変」と感じる時にも役立ちます。
また、「未来献立®」では前日食べたものの傾向にあわせて、栄養バランスのツジツマを合わせた「ツジツマ献立」もご提案可能なため、つい好きなものを食べ過ぎた時でも安心です。
前日の食事をもとに必要な栄養素を把握して、鍋に入れる食材を決めるのもおすすめです。「未来献立®」があれば、食事の栄養バランスにより手軽に向き合えるでしょう。
鍋に入れる具材を工夫して栄養バランスの良い食事を
この記事では、鍋に入れる様々な具材の種類とその特徴、栄養価について紹介しました。
鍋料理の優れた点は、一度の食事で多様な食材を摂取できることです。様々な具材を組み合わせることで、比較的容易にバランスの取れた献立をつくることができます。
しかし、栄養バランスを考える上で重要なのは、鍋料理だけでなく日々の食事全体を見渡すことです。食事の栄養バランスを考えることは、健康的な生活を送る上で大切です。
毎日の献立を考えるのは大変だと感じる方は、ぜひ「未来献立®」を活用してください。

監修者
金丸 利恵(かなまる りえ)
おうちごはん研究家、管理栄養士、分子栄養学カウンセラー
大手企業での栄養士業務、レシピ開発を担当。保健指導では2000名以上の食事指導を行う。その後独立し、料理教室を主宰し、食育やダイエットサポートなどあらゆる世代の食と健康に関わる。「食べることは、生きること」をモットーに、栄養指導やセミナーを通じて、食と栄養の大切さを伝えている。スーパーで買える身近な食材で、健康的に美味しく簡単に作れるレシピに定評がある。
 献立提案サービス
献立提案サービス