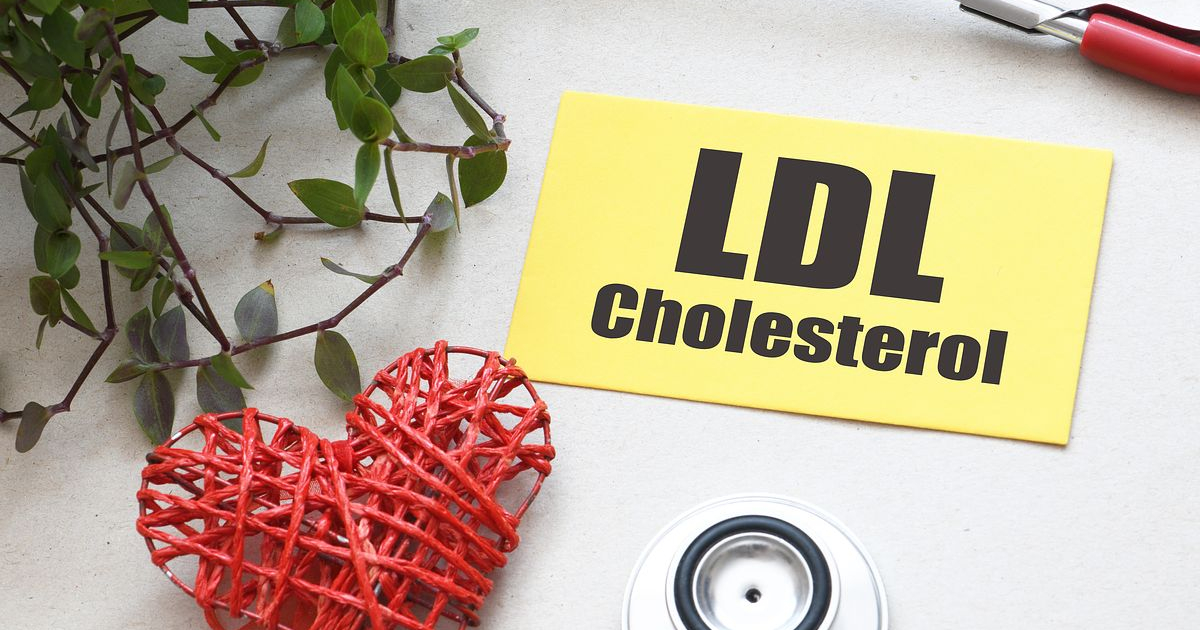腸内環境を改善する方法は?腸内フローラを整えるメリットやおすすめの食べ物を紹介

腸内環境の改善は、健康維持や病気予防に重要な役割を果たします。腸内フローラを整えると消化吸収がスムーズになり、免疫力の向上やメンタルヘルスの改善にもつながります。
一方、腸内環境が乱れるとお腹の調子をはじめとする健康面に悪影響が出るため注意が必要です。
この記事では、腸内環境を整えるための具体的な方法や、腸内環境改善に適したおすすめの食べ物を紹介します。腸内環境の乱れが体調不良の原因になっているのではないかと心配な方は、ぜひ参考にしてください。
腸内環境改善のために知っておきたい知識
腸内環境改善の具体的な方法を紹介する前に、腸内環境に関して知っておきたい前提知識を紹介します。
- 腸内環境や腸内フローラについて
- 善玉菌・悪玉菌・日和見菌の役割
それぞれ説明します。
腸内環境や腸内フローラについて
腸内環境は、100兆個〜1,000兆個(約1,000種類)の腸内細菌に影響を受けます。腸内細菌の種類は大きく分けて善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3つです。
腸内環境の良し悪しはこの3つのバランスで決まり、善玉菌が優勢な状態を「腸内環境が良い状態」と表現します。
腸内細菌は菌種ごとの塊で腸の壁に張り付いており、その様子がお花畑のように見えるため「腸内フローラ」と呼ばれています。腸内フローラの正式名称は「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」です。
善玉菌・悪玉菌・日和見菌の役割
前述のとおり、腸内フローラを構成するのは主に、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3タイプの菌です。それぞれ異なる役割を担い、腸内フローラのバランスが健康に大きく影響します。
腸内細菌ごとの役割と理想的な割合は、以下のとおりです。
| 腸内細菌の種類 | 役割 | 理想的な割合 |
|---|---|---|
| 善玉菌 | 乳酸・酢酸などをつくりだし、腸内を弱酸性に保つことにより、悪玉菌の繁殖を防ぐ。感染防止、免疫力アップなど健康が維持できる腸内環境を保つ。ビタミンをつくり、消化吸収を助ける役割もある。 | 2割 |
| 悪玉菌 | 毒性物質・有害物質をつくりだす。腸内を腐敗させ、便秘や下痢などお腹の調子が悪くなる。 | 1割 |
| 日和見菌 | 善玉菌と悪玉菌、優勢なほうと同じ働きをする。状況によって善玉菌と悪玉菌どちらの味方にもなる。 | 7割 |
悪玉菌はその名称から、悪いイメージを持つかもしれません。しかし、完全に不要なわけではなく、肉類をはじめとするたんぱく質を分解し、便にする働きがあります。
大切なのは、悪玉菌を完全になくすことではありません。善玉菌優勢の状態だと、数がもっとも多いとされる日和見菌が善玉菌と同じ働きを行い、腸内環境が整います。つまり、腸内環境改善のためには、善玉菌優勢の状態に保つことが重要です。
腸内環境が乱れると起こる症状

腸内環境が乱れると、主に以下の症状が起こる可能性があります。
- 便秘
- 下痢
- 肌荒れ
- 免疫力の低下
腸内環境が乱れた際の初期症状としてお腹の不調があらわれます。悪玉菌が優勢になると毒性物質の影響を受け、大腸の蠕動運動(排便を促す運動)が鈍化するためです。
また、腸内環境の乱れは、メタボリックシンドローム、糖尿病、動脈硬化症、大腸がん、認知症、うつ病などの疾患とも関係しています。疾患のある患者は健常者と比べて腸内環境が悪いことが知られています。
腸内環境の改善は疾患を予防し、健康維持につながる重要な要素のため、日頃から意識しましょう。
腸内環境の乱れとダイエットや肥満との関係
腸内環境はダイエットや肥満とも密接に関係しています。
腸内細菌でも多くの割合を占める日和見菌には「ファーミキューテス類」や「バクテロイデーテス類」と呼ばれるグループに属する菌があり、腸内環境が正常な時にはとくに害はありません。
しかし、腸内フローラのバランスが崩れると性質が変わり、健康に影響を与えます。
ファーミキューテス類は悪玉菌の味方になりやすい菌です。食べものから必要以上にエネルギーを取り込み体に脂肪として蓄える働きがあります。一方、バクテロイデーテス類は善玉菌の味方になりやすい菌です。短鎖脂肪酸と呼ばれる脂肪蓄積を抑制する物質をつくりだします。
ファーミキューテス類とバクテロイデーテス類の割合は4:6が理想とされています。ダイエットの成功や肥満防止のためには、ファーミキューテス類を活性化させないよう、善玉菌優位の状態に保つことが大切です。
腸内環境が乱れる主な原因
腸内環境が乱れる主な原因は以下のとおりです。
- 食生活の乱れ
- 不規則な生活
- 睡眠不足
- 運動不足
- ストレス
- 便秘
- 加齢 など
例えば、肉類や高脂質な食品、アルコール、甘いものの摂りすぎ、野菜不足などの食生活は悪玉菌を増やすため、偏った食生活や不規則な食生活には注意が必要です。
食べ物以外では、ストレスも消化器系の不調を起こす原因として知られています。腸内の働きは自律神経でコントロールされており、睡眠不足やストレスで自律神経が乱れると腸内環境も乱れるためです。ストレスで便秘や下痢が起こるのは「過敏性腸症候群」と呼ばれます。
なお、腸内細菌のバランスが乱れると、自律神経を介して脳にも悪影響を与えるため、「腸は第2の脳」と呼ばれます。健康的な生活を送るために、腸内環境改善は必要不可欠です。
腸内環境を改善するメリット・効果
腸内環境改善による主なメリット・効果は以下のとおりです。
- 便秘・下痢の改善
- 肥満防止
- 免疫機能の向上
- 睡眠の質向上
- ストレス軽減・気分の安定
腸内環境が整っている方は便秘や下痢になりにくく、スムーズに排便を行えるため太りにくい体質になる傾向にあります。腸内の免疫細胞も効果的に働き、ウイルスから体を守って免疫機能の向上も期待できます。
腸内環境が整っていると、質の高い睡眠に必要な物質も効率的に生成されるため、快適な睡眠が得られやすくなるでしょう。
また、前述のとおり、自律神経の乱れによって起こる症状のひとつが腸内環境の乱れです。腸内を良い状態に保てば自律神経の乱れを防げるため、ストレスの軽減や気分の安定にもつながります。
腸内環境の改善効果が期待できる食べ物・食事

腸内環境改善のためには、善玉菌を含む食品や善玉菌の餌となる食品の摂取が大切です。それぞれ「プロバイオティクス」「プレバイオティクス」と呼ばれます。
役割や摂取できる食品を紹介するので、腸内環境改善を目指している方は参考にして、食事に取り入れてください。
プロバイオティクスが摂取できる食品
プロバイオティクスとは、適正な量を摂取した時に健康へ良い効果をもたらす生きた微生物と定義されています。
プロバイオティクス食品と認められるのは、以下の条件を満たすもの※です。
- 安全であること
- ヒトの腸内フローラを構成する細菌であること
- 胃液や胆汁などに耐えて生きたまま腸に到達すること
- 腸内で増殖できること
- ヒトに対して明らかに有益であること
- 食品などの形で有効な菌数を維持できること
- 取り扱いやすく安価であること
※出典:公益財団法人 腸内細菌学会「プロバイオティクス(probiotics)」
プロバイオティクスに類する主な菌と、含まれる食品の例は以下のとおりです。
| 菌の種類 | 含まれる食品の例 |
|---|---|
| 乳酸菌 | 納豆、乳製品、キムチ |
| ビフィズス菌 | ヨーグルト(ビフィズス菌入り) |
| 酢酸菌 | ぬか漬け、臭豆腐 |
| 納豆菌 | 納豆 |
プレバイオティクスが摂取できる食品
プレバイオティクスとは、善玉菌の餌となり、善玉菌を増やす役割があるものをさし、「腸の特定の細菌を増殖させることなどにより、有益に働く食品成分」と定義されています。
プレバイオティクス食品と認められる条件は下記のとおりです。
- 消化管上部で加水分解、吸収されない
- 大腸に共生する一種または限定された数の有益な細菌(ビフィズス菌等)の選択的な基質であり、それらの細菌の増殖を促進し、または代謝を活性化する
- 大腸の腸内細菌叢(フローラ)を健康的な構成に都合の良いように改変できる
- 宿主の健康に有益な全身的な効果を誘導する
※出典:公益財団法人 腸内細菌学会「プレバイオティクス(prebiotics)」
プロバイオティクスに類する主な成分と、含まれる食品の例は以下のとおりです。
| 成分の種類 | 含まれる食品の例 |
|---|---|
| オリゴ糖 | りんご、バナナ、玉ねぎ、キャベツ、ごぼう、にんにく、大豆 |
| 水溶性食物繊維 | キウイ、ごぼう、ほうれん草、ブロッコリー、さつまいも、大豆、きのこ類、オートミール、ライ麦 |
| 不溶性食物繊維 | キウイ、かぼちゃ、ごぼう、さつまいも、大豆、おから、オートミール、ライ麦、アーモンド、くるみ |
腸内環境改善を目指すための食事以外の方法
腸内環境改善に効果がある食事以外の方法は以下のとおりです。
- 運動習慣を身につける
- 生活習慣を改善する
- ストレスを解消する
それぞれ簡潔に紹介します。
運動習慣を身につける
腸内環境の改善に取り組む際には、適度な運動習慣を身につけましょう。運動は蠕動運動を促進し、便秘を改善します。適度な運動は自律神経も整えるため、心身の健康にも効果的です。
仕事が忙しく時間がとれない方や運動する習慣がない方は、ラジオ体操やウォーキング、ストレッチなど簡単なものからはじめてみましょう。
生活習慣を改善する
生活習慣が乱れると腸内環境も乱れます。生活習慣を整えることは腸内環境を整えることにつながるため、十分かつ質の高い睡眠をしっかりとり、バランスの良い食事を心がけましょう。
例えば、成人の場合6〜9時間が理想的な睡眠時間とされますが、適切な睡眠時間は季節や年齢、個人差によって異なります。自分にとって休養感があり、昼間に強い眠気が生じない睡眠時間を知ることが大切です。自分にとって常に必要な睡眠時間を確保し、質の高い睡眠をとりましょう。
ストレスを解消する
腸内環境を整えるためには、自律神経が乱れないよう注意することも大切です。自律神経を乱す原因となるストレスは溜めないよう、日頃から意識しましょう。
ストレス解消の方法は様々です。ヨガやストレッチ、瞑想、アロマテラピー、散歩など、自分にとって適したストレス解消方法を日常に取り入れ、ストレスを溜めないよう工夫しましょう。
腸内環境改善のためにサプリメントは取り入れるべき?
腸内環境を改善するために、サプリメントを取り入れたいと考える方も多いと思います。腸内環境改善を目指してサプリメントを利用するなら、サプリメントは薬ではなく健康補助食品であることを前提として理解しましょう。
その上で、サプリメントには様々な種類があるため、その中から腸内環境改善に役立つと期待されるサプリメントを選ぶ必要があります。サプリメントは「健康食品」と呼ばれるものであり、特定の疾病を治療したり、予防したりする効果が得られるものではありません。
ただし、特定保健用食品の中には、腸内環境の改善効果が認められるとするもの、機能性表示食品においても、腸内環境の改善効果が販売事業者によって確認されているものなど、おなかの調子を整える効果を得ることを目的としたサプリメントがあるため、それらを選ぶと良いでしょう。
長期的かつ根本的に腸内環境改善を目指すなら、食生活をはじめとする生活習慣を見直すことが重要です。サプリメントを取り入れる場合でも、日頃の食生活を整えることを基本として、サプリメントは補助的な意味合いで利用すると捉えましょう。
サプリメントは食生活・生活習慣が乱れてしまう時のサポートとしてお役立てください。
栄養バランスを意識した献立を考えるなら「未来献立®」がおすすめ
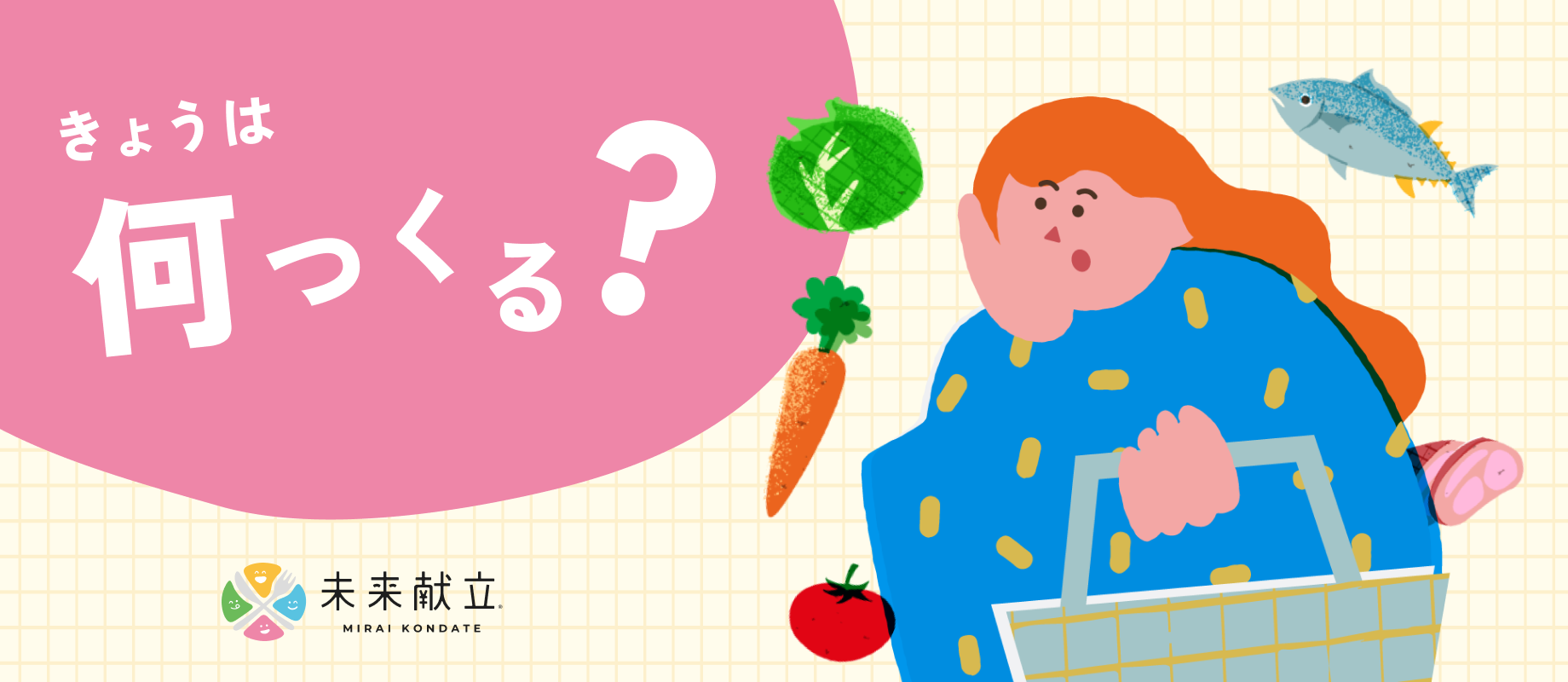
ここまで読んで、腸内環境改善のために栄養バランスの整った食事が大切なのはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
腸内環境改善を意識した食品を選びつつ、栄養バランスまで考えるのは難しいかもしれません。そんな時に「未来献立®」が役立ちます。
「未来献立®」は、栄養バランスが考えられた献立をまとめてご提案する献立提案サービスです。肉や魚など、バリエーション豊富なメニューをご用意しているので、「1週間の栄養バランスを考えるのは大変」と感じる時に便利です。
また、「未来献立®」では食べたものに応じて、「ツジツマ献立」としてツジツマを合わせたメニューをご提案するので、つい好きなものを食べ過ぎた時や栄養バランスが一時的に偏った時でも安心です。
「未来献立®」は、毎日栄養バランスも踏まえつつメニューを考えることが難しい方に便利なサービスです。1週間分の献立を考えることが苦手な方や、食生活に偏りを感じており、栄養バランスの整った食事にしたい方は、ぜひ活用をご検討ください。
腸内環境改善を意識して健康な毎日を目指そう
腸内環境は、消化吸収だけでなく免疫機能やメンタルヘルスにも影響を与えます。食生活の改善や発酵食品の摂取、適度な運動、ストレス管理を取り入れると腸内フローラのバランスを整えられ、腸内環境の改善が期待できます。
腸内環境を根本的に改善するなら、日々の食習慣の見直しが大切です。整った食生活を基本とし、サプリメントは必要に応じて補助的に取り入れると良いでしょう。
自分で栄養バランスの整ったメニューを考えることが大変なら、ぜひ「未来献立®」をご活用ください。「未来献立®」は栄養バランスが考えられた献立をまとめてご提案する献立提案サービスであり、栄養バランスのとれた献立が簡単に作成できます。

監修者
伊藤 まゆ(いとう まゆ)
M’sクリニック南麻布 院長、日本抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医
本当の美とは、心と体の健康あってこそ、という観点から、2007年開院時より、内外美容医療を提唱、実践。栄養学、予防医学、エイジングケア、美容について、多様な経験と多角的視点で取り組み、幅広い世代のサポートを行っている。
 献立提案サービス
献立提案サービス