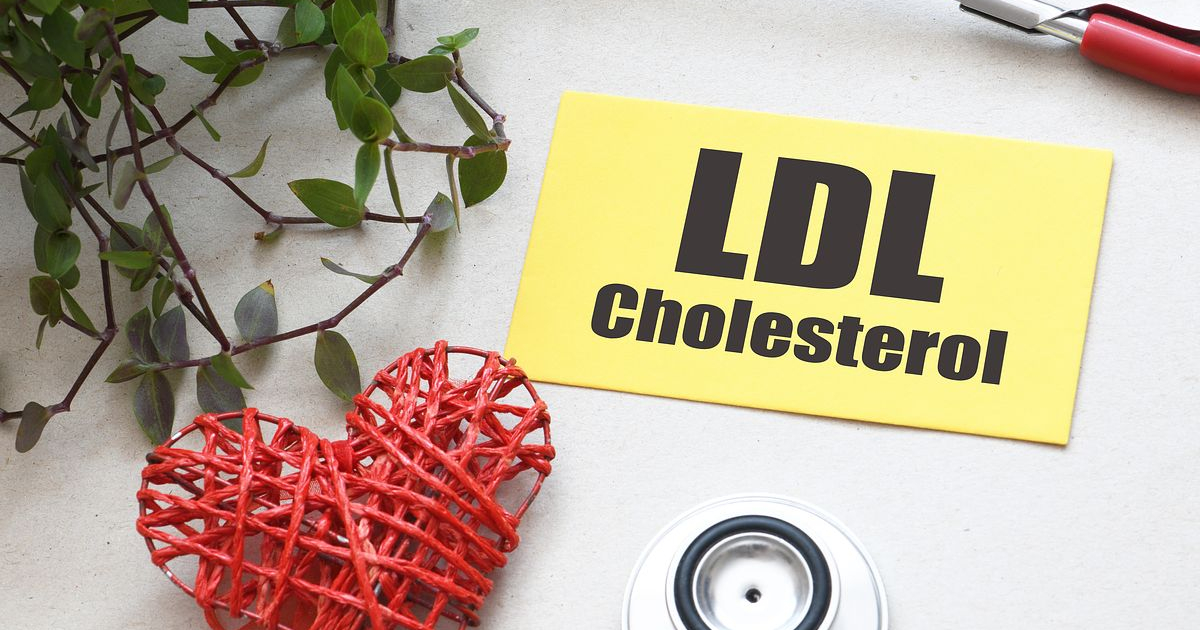冷え性の改善を目指す方法は?手足が冷たい原因からセルフケアのポイントまで紹介

季節を問わず体の冷えを感じて困っている方は多いです。とくに女性は手足の冷えや体のだるさなどを感じてお悩みの方が多いのではないでしょうか。
冷え性の改善を目指すためには、冷え性のタイプや症状の特徴を見極めることで原因を知り、対策を実践することが大切です。
この記事では、冷え性改善のために役立つ食事のポイントや、食事以外の改善方法などについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
冷え性には複数のタイプがある
一口に冷え性といっても様々なタイプがあり、それぞれ冷えを感じる部位や特徴が異なります。まずは、ご自身がどのタイプに該当するのか確認しましょう。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 下半身タイプ | 下半身の冷えを強く感じ、冷え性で悩んでいる方に多く見られる |
| 上半身タイプ | 上半身には汗をかき、下半身には冷えを感じる |
| 手足の末端タイプ | 手や足の先がとくに冷たく感じる |
| お腹タイプ | 内臓が冷え、お腹を壊しやすい |
| 全身タイプ | 全身が冷えており、体温も低くて体調を崩しやすい |
冷え性は人によって個人差があり、複数の症状が現れるケースもあります。
冷え性の症状とは?
冷え性の症状は、軽度から重度まで人によって異なります。
軽度の冷えであれば「なんだか手足が冷たい」と感じる程度です。一方、重度の場合は血行が悪くなり、手や足などの冷える部分にしびれを感じることがあり、何気ない動作や仕事などにも悪影響をおよぼすおそれがあるため注意が必要です。
他にも、体のあらゆる部分に不調が生じる可能性も考えられます。
| 部位 | 不調の一例 |
|---|---|
| 髪の毛 |
|
| 肌 |
|
| 歯 |
|
| 目 |
|
| その他 |
|
このように、様々な不調を引き起こす主な原因は、血の巡りが悪化して冷えが生じたからだと考えられます。
冷え性改善のためには、血の巡りが悪くなった原因の把握が大切です。
冷え性の主な原因
冷え性になる原因は、いくつか考えられます。
- 生活習慣の乱れ
- 筋肉量の低下
- 喫煙
- 鉄分不足 など
食事の栄養バランスが崩れる、ストレスを溜め込むなどの生活習慣の乱れによって冷え性を引き起こす原因は、自律神経の機能が乱れることです。
自律神経が血液の流れをコントロールして人間の体温は一定に保たれていますが、自律神経のバランスが乱れると体温調節が上手にできなくなり、冷え性を引き起こす場合があります。
また、運動習慣がない方は、筋肉量の低下により冷え性を引き起こすおそれがあるため注意が必要です。
筋肉の中に含まれるたんぱく質には熱をつくるはたらきがあり、筋肉量が増えると身体を効率良く温められる一方、筋肉量が減ると熱をつくるはたらきが弱くなって冷え性の原因につながります。
その他、喫煙習慣も血管収縮により血流を悪化させ、体温の低下を招きかねません。さらに、血液に含まれるヘモグロビンや、筋肉に含まれるミオグロビンに必要な鉄が不足するのも、血行不良や筋肉量の低下により冷え性を引き起こす原因になります。
女性は男性よりも冷え性の方が多い理由
男女問わず冷えを感じることはあります。しかし、とくに女性は男性よりも冷え性を実感している方が多いことが、厚生労働省の調査※でわかっています。
以下は、「手足が冷える」自覚症状があると答えた方の人数・割合です。
| 総数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 2,952人 | 888人(約30%) | 2,064人(約70%) |
出典:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
この結果から、冷え性の自覚がある女性は男性の2倍以上いることがわかります。
女性が冷えを感じやすいのは前項でも挙げたとおり、男性よりも筋肉が少ないことや、生理の経血により鉄分不足になりやすいことが主な原因です。
他にも肌を出して身体が冷えやすい服装をする機会が多いことも原因として考えられます。
セルフケアで冷え性を改善する方法

冷え性は日常生活でセルフケアを実践して改善を目指す方法があります。どなたでも簡単にはじめられる方法なので、ぜひ参考にしてください。
「三首(首・手首・足首)」を冷やさずに温める
人間の身体で「首」がつく部分の「三首」または「3つの首」と呼ばれる、首・手首・足首をしっかり温めることが大切です。
これらの部分に共通するのは太い血管や神経が通っていることで、気温が寒い時には影響を受けやすく、全身が冷えやすくなります。
外気が冷たく感じる季節や、エアコンが効いている室内で長時間過ごす時は、「三首」を冷やさないようにしっかり温める工夫をしましょう。
| 部位 | 温める方法の例 |
|---|---|
| 首 |
|
| 手首 |
|
| 足首 |
|
お風呂はシャワーで済ませず湯船に浸かる
お風呂はシャワーだけで済ませず、しっかり湯船に浸かることが望ましいです。入浴時には以下のポイントをおさえて、体を芯まで温めてください。
- お湯の温度は38~40℃
- 入浴時間は10~30分程度
- 時間帯は就寝の1時間30分程度前
入浴は睡眠にも影響を与える要素なので、睡眠時のことも考慮して入浴しましょう。
熱すぎるお湯で入浴すると、体が戦闘モードになって入眠しづらくなります。一方、「少しぬるいかな?」と感じる程度のお湯にゆっくり浸かると、心身をリラックスさせる副交感神経が優位になります。
また、人間は体の芯の温度が下がると眠くなる特性があります。体の芯まで温まってから1時間30分くらい経った頃に眠気がおとずれるため、寝る時間から逆算して入浴時間を調整してみてください。
なお、入浴時には好きな入浴剤を入れるのもおすすめです。入浴剤を入れたぬるめのお湯に浸かることで、リラックスして自律神経のバランスが整い、体が芯まで温まって冷え性の改善にも役立つでしょう。
筋トレやストレッチなどの運動に取り組む
筋肉量アップや血流改善を目指して、筋トレやストレッチなどの適度な運動習慣を心がけましょう。筋トレは腹筋やスクワットなどを実践して、体のなかでも大きな筋肉を鍛えるよう意識すると、基礎代謝アップにつながります。
いきなり筋トレに取り組むのは難しいと感じる場合は、簡単なストレッチからはじめてはいかがでしょうか。
20秒くらいの時間をかけて、ゆっくり呼吸をしながら筋肉を気持ちよく伸ばすよう意識することがコツです。肩の上げ下げ運動や、首回し、腰のひねり運動など、無理なく実践できるストレッチから取り組んでみてください。
また、筋トレやストレッチに取り組む時間を確保できない場合は、日常で体を動かすことを意識するのも有効です。例えば、いつも利用する駅のひとつ手前で降りて歩いて帰る、エレベーターではなく階段を使うなどの工夫もおすすめです。
良質な睡眠を心がける
不規則な睡眠は自律神経のバランスが乱れる原因になり、冷え性につながることもあるため注意しましょう。
自律神経のバランスは睡眠にも影響しており、交感神経が優位の緊張状態から、副交感神経が優位のリラックス状態になることでぐっすり眠れるようになります。
睡眠時間の目安は6時間以上ですが、人によって最適な時間が異なるため、ご自身にとって必要な睡眠時間を確保できるよう調整してみてください。
良質な睡眠を促すために入浴時間を工夫することに加えて、できることを実践しましょう。
- カフェインを多く含むコーヒーやお茶を寝る前に飲まない
- お酒やタバコの過剰摂取を控える
- 寝室の照明は暗くする
- 周囲の音が聞こえないよう対策する
- リラックスできる香りのアロマを楽しむ
食事で冷え性を改善する方法は?

冷え性改善を目指すためには、毎日の食事を見直すことも大切です。意外と見落としやすいので、ぜひ取り組んでみてください。
栄養バランスが整った食事を心がける
栄養バランスが整った食事を心がけることは、冷え性の改善に欠かせません。食事に含まれる様々な栄養素は、血行を促して体温を保つために役立つはたらきがあります。
以下のように、様々な栄養素をバランス良く補いましょう。
| 栄養素名 | 特徴 |
|---|---|
| 糖質 | 体内でブドウ糖になりエネルギー源になる |
| たんぱく質 | 筋肉に必要で、熱エネルギー源になって代謝を促す |
| ビタミンB群 | 糖質やたんぱく質をエネルギーに変えて体温を上げる |
| ビタミンC | 鉄分の吸収を促す |
| ビタミンE | 末梢血管の血流を促す |
朝食を抜かずに3食きちんと食べる
食事の見直しで忘れてはいけないのは、3食きちんと食べて、食べる時間帯が不規則にならないよう気をつけることです。
とくにダイエットや、忙しくて時間がとれないなどの理由で朝食を抜いている方は、明日からしっかり食べることを意識してみてください。
朝食は1日のエネルギー源として熱を生み出すためにも必要であり、筋肉量の低下を防ぐためにも大切なことです。
1日のはじまりには糖質とたんぱく質をしっかり摂取して、体温の上昇と代謝アップを目指しましょう。
冷たい飲み物や甘い食べ物はできる限り避ける
体温よりも温度が低い冷たい飲み物は内臓を冷やす原因のひとつです。そのため、冷たい飲み物を毎日飲んでいる方は要注意です。
暑い時期は冷たい飲み物がほしくなるかもしれませんが、できる限り常温や体温以上の飲み物を摂取しましょう。冷え性の方におすすめの飲み物の例として、以下のものがあります。
- 白湯
- 温かいウーロン茶・紅茶
- ハーブティー
- しょうが湯
- ホットはちみつレモン
また、飲み物の選び方に気を配るのに加えて、甘い食べ物を食べ過ぎないことも大切です。
砂糖が大量に入った甘い食べ物は、血流を悪化させる原因になります。甘いものを食べると血糖値が急上昇し、血流が悪くなって体が冷えやすくなるため、食べ過ぎないよう気をつけましょう。
体を温める食材を取り入れる
食材には、体を温めるものと冷やすものがあります。これらの違いを見極めて、毎日の食生活で使い分けましょう。
| 項目 | 食材の例 |
|---|---|
| 身体を温める |
|
| 身体を冷やす |
|
簡単な見分け方としては、冬に旬を迎える食材や土の中でできる根菜は体を温めるのに対し、夏に旬を迎える食材や地上にできる野菜は身体を冷やすとされています。
他にも未精製の食材や発酵食品も体を温める食材といわれているので、積極的に取り入れてみてください。
漢方で冷え性の改善が目指せる?
冷え性を改善する手段として、漢方を用いる方法も挙げられます。
基本的に、西洋医学では冷え性に対して効果的な薬が処方されるわけではなく、特別な治療法が存在しているわけでもありません。
一方、東洋医学では、冷えが様々な病気をもたらす「未病」として、重要な病態であると考えられており、漢方による冷え性対策が行われます。
漢方は冷え性の原因となる「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」のバランスを整えて改善を目指すところが特徴で、冷え性のタイプを見極めた上で個人に最適な方法を選びます。
症状が気になるなら医療機関の受診を
冷え性改善のために漢方薬を試したいと考える方は多いと思いますが、国で承認されている漢方薬は294処方あり、自分に適した漢方薬を探すのは難しいです。
症状が類似している方と同じ漢方薬を飲んでも、効果が得られないケースは珍しくありません。本当に合う漢方薬を見つけるためには、症状だけでなく、個人の体質や体力などの状況を見極める必要があります。
市販の漢方薬を自分で判断して飲むのは難しいため、冷え性改善のために漢方薬を飲みたいと考えているなら、まずは医師に相談しましょう。漢方内科を設けていたり、オンラインの相談に対応していたりする医療機関もあります。
冷えによる症状がつらい場合、他の病気が潜んでいる可能性もあるため、自己判断せずに医師の診察を受けることをおすすめします。
「未来献立®」で栄養バランスの整った食事を意識しよう
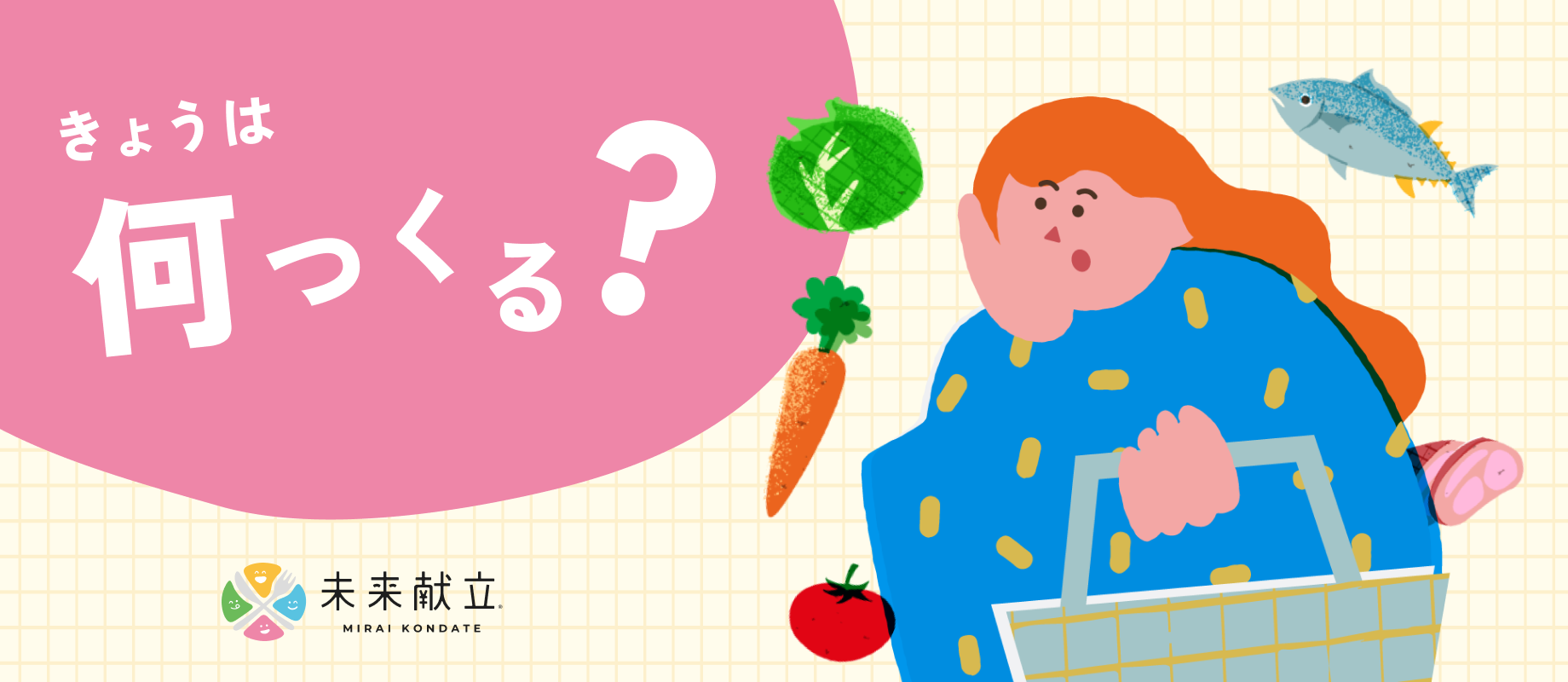
冷え性改善のためには食事や入浴、運動などに気を配ることが重要です。
なかでも食事に関しては、栄養バランスの整った食事が大切だと頭で理解していても、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少しだけ気が楽になるのではないでしょうか。
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」を試してみてください。
「未来献立®」は、おいしさと栄養バランスをどちらも叶えた献立をまとめてご提案するサービスです。
例えば、前日の食事内容で野菜が足りなかった場合には今日の献立で野菜を多く取り入れて、昨日と今日の栄養バランスのツジツマを合わせるようにご提案します。
「冷え性改善のために、栄養バランスのとれた献立を考えるのは大変」とお悩みの方にも、ぴったりのサービスです。
冷え性を改善するには生活習慣の見直しが大切
冷え性のタイプは人によって異なり、生活習慣の乱れやストレスなどが原因で生じることがあります。
冷え性を改善するためには、食生活や運動、睡眠などの生活習慣を見直すことが大切です。
「未来献立®」は、栄養バランスのとれた食事を楽しむために役立つ献立をご提案します。冷え性改善を目指して食生活を整えようと思っている方は、ぜひご活用ください。

監修者
伊藤 まゆ(いとう まゆ)
M’sクリニック南麻布 院長、日本抗加齢医学会専門医、日本医師会認定産業医
本当の美とは、心と体の健康あってこそ、という観点から、2007年開院時より、内外美容医療を提唱、実践。栄養学、予防医学、エイジングケア、美容について、多様な経験と多角的視点で取り組み、幅広い世代のサポートを行っている。
 献立提案サービス
献立提案サービス