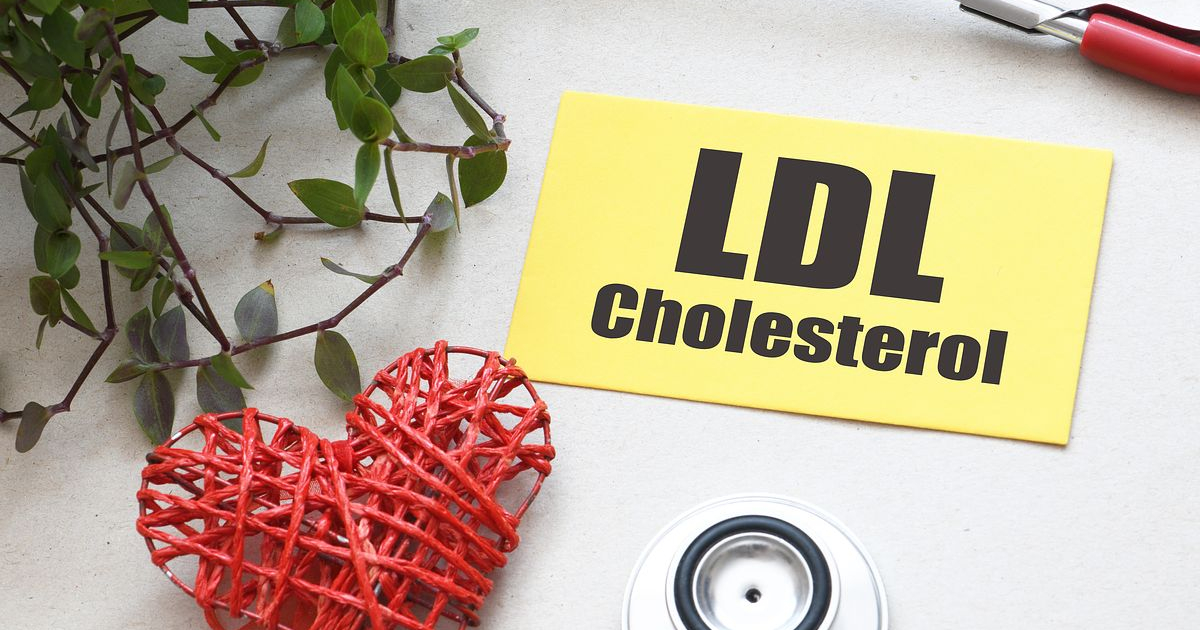夏バテに効く食べ物は?おすすめの食事方法や摂りたい栄養素も紹介

夏バテは、自律神経の乱れや発汗による栄養素の排出が原因で起きるとされています。日々取り入れられる予防法や対策としては、食事方法を変えることがおすすめです。
この記事では夏バテの原因や予防・対策方法、夏バテに効果的な栄養素を紹介します。夏バテ対策が知りたい方や、暑い夏も元気に過ごしたい方は、ぜひ参考にしてください。
夏バテとは?
夏バテとは、室内と室外の温度差がある時期に、以下のような症状が現れることです。
- だるさ(倦怠感)
- 疲れやすさ
- 食欲不振
- 胃もたれ
- 痩せる など
該当の症状がある場合には、原因を理解して改善を目指しましょう。
夏バテの原因
暑い時期には夏バテになりやすいため、原因を知ってバテにくい体に調整していくことが大切です。
夏バテの原因としては、主に以下が挙げられます。
- 温度差が激しい環境
- 冷たい食べ物の食べ過ぎ
- 運動不足
- 睡眠不足 など
温度差が激しい環境
体は、外の温度にあわせて体温を一定に保とうとエネルギーを使います。これは体温を調整する自律神経の働きです。
例えば、暑い日に室内を冷房で冷やしている場合、外では外気温に近づこうと体温を上げ、冷房の効いた室内では室温にあわせて体温を下げようとします。
そのため、室内外の温度差が激しい環境で体温調整が毎日続くと、自律神経に負荷がかかって働きが乱れ、体も疲れてしまいます。これが、夏バテの原因のひとつです。
冷たい食べ物の食べ過ぎ
夏は暑いため、冷たい物を食べたくなる季節でしょう。
しかし、冷たい食べ物を食べ過ぎると胃腸の働きを弱め、食欲低下につながります。食欲が低下してしまうと体力も低下して疲労がたまりやすくなり、夏バテにつながる可能性があります。
運動不足
運動不足や室内の寒さであまり汗をかかないと、体内に熱がこもり体温調節機能が低下することがあります。
また、運動不足は筋肉や体の各器官の機能低下、夏の暑さに対する防衛力の低下にもつながります。
睡眠不足
暑くて快適な睡眠ができない、寝つくまで時間がかかるなど、睡眠不足によって疲労回復が図れない場合も夏バテを起こしやすくなります。
疲労感が残っていると、自律神経が乱れて夏バテになる可能性があるため注意しましょう。
夏バテの予防・対策におすすめの食事方法・ポイント

夏バテ予防には、睡眠をしっかりとって疲労回復に努めたり、適度な運動を取り入れたりする方法があります。また、食事面で対策を講じることも大切です。
夏バテ予防や対策になるおすすめの食事方法を、以下で解説します。
- 1日3食の食事を摂る
- 体を冷やす冷たい食べ物を避ける
- 夏に不足しやすい栄養素を意識して摂る
- こまめに水分補給する
1日3食の食事を摂る
夏バテになると食欲がなくなることが多く、1日3食の食事が難しい場合もあるかもしれません。そのため、食欲がなくなる前に、毎日3食摂る習慣をつけておくと良いでしょう。
食事の基本は、主食と主菜、副菜で、炭水化物とたんぱく質、ビタミンやミネラルをまんべんなく摂ることです。ひとつの食材に偏るのではなく、様々な食材を組み合わせることで、体の不調につながりにくくなります。
体を冷やす冷たい食べ物を避ける
冷たい食べ物や飲み物は体を冷やし、胃腸の働きを弱める原因になります。そのため、夏の暑い時期でも「温かい食べ物」を意識して食べると良いでしょう。
冷房が効いた涼しい室内であれば、冷たいそうめんやアイスなどの冷たい食べ物より、温かいスープやうどんを食べ、飲み物は温めるまではいかなくても常温で飲むと体が冷えにくくなります。
夏に不足しやすい栄養素を意識して摂る
夏は冷たい麺類やアイスクリームなどを食べる機会が増え、炭水化物の摂取が増える傾向にあります。炭水化物は体のエネルギー源としては必要な栄養素ですが、炭水化物だけ摂っていても体は正常に働きません。
食事をする際は、不足しやすいたんぱく質やビタミン類を意識して摂ると良いでしょう。炭水化物がエネルギー源になるためには、ビタミンB1やビタミンB2が必要です。ビタミンB1やB2を含む食材は疲労回復にも役立つため、ぜひ取り入れてください。
なお、栄養バランスを考えた献立を考えるのが難しいと感じる方は、ぜひ「未来献立®」をご利用ください。
こまめに水分補給する
夏のだるさや疲れやすさは水分不足が原因の場合もあります。「のどが渇いた」と感じた時の水分補給も大切ですが、のどが渇く前から時間を決めてこまめに水分を摂りましょう。
特に夏は、自分でも気付かないうちに汗として水分が排泄されます。大人は2.5リットルの水分が1日に排出されるため、その分水分をしっかりと補給する必要があります。
飲むものは水やお茶にして、スポーツドリンクなどは適量に留めましょう。スポーツドリンクなどの清涼飲料水の摂り過ぎは、糖質の摂り過ぎにもつながるため注意が必要です。
夏バテに効く栄養素とおすすめの食べ物

夏バテに効く栄養素は以下のとおりです。
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンC
- クエン酸
- たんぱく質
- アリシン
以下で、それぞれの栄養素の働きと含まれる食材を紹介します。夏バテ予防として日々の食事に取り入れてみてください。
ビタミンB1
ビタミンB1は炭水化物をエネルギー源に変える役割を担っており、疲労回復効果につながります。そのため、不足するとだるさや疲れやすさが生じます。
ビタミンB1は豚肉やうなぎ、玄米、大豆、そら豆などに多く含まれています。
ビタミンB2
ビタミンB2はビタミンB1と同様に、炭水化物をエネルギー源に変える役割を担っています。さばやいわしなどの青魚、レバー、牛乳、卵などに多く含まれているため、意識的に摂取しましょう。
ビタミンC
ビタミンCは体内ではつくられないため、食事から摂らないと不足しやすい栄養素です。免疫力や日焼け予防のためには欠かせません。
特に夏は紫外線を浴びる季節であることから、よく使われる栄養素のため、しっかり摂取しましょう。ビタミンCはパプリカやゴーヤ、キウイ、ジャガイモなどに多く含まれています。
クエン酸
クエン酸は胃酸の働きをサポートして食欲を増し、たんぱく質の吸収をサポートする役割を担っています。
また、疲れやすさの原因になる「乳酸」と呼ばれる物質を体外に排出する働きもあるため、疲労回復効果もあるといわれています。
レモンなどの柑橘類やキウイ、酢に多く含まれているため、夏に食欲不振になる方は意識的に摂取すると良いでしょう。
たんぱく質
たんぱく質は筋肉や血液のもとになる栄養素です。たんぱく質不足だと筋肉の量が減り、基礎代謝も低下します。冷え性や体力低下につながる可能性もあるため、毎日きちんと摂取することが大切です。
食欲がなくても食べやすい冷奴やゆで卵など、意識して摂取しましょう。その他、肉や魚、乳製品、大豆製品にも多く含まれています。
たんぱく質が多く含まれる食材については、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
アリシン
アリシンはビタミンB1の働きを助けるために必要な栄養素です。疲れやすさやだるさなどに打ち勝って元気な体を保つためには、ビタミンB1が必要なため、そのサポートをするアリシンも意識して摂りたい栄養素のひとつです。
アリシンはねぎやにんにく、ニラなどに多く含まれています。特ににんにくを細かく刻むと、アリシンがより増えるので、ぜひお試しください。
「未来献立®」を活用して簡単に栄養バランスのよい食事を
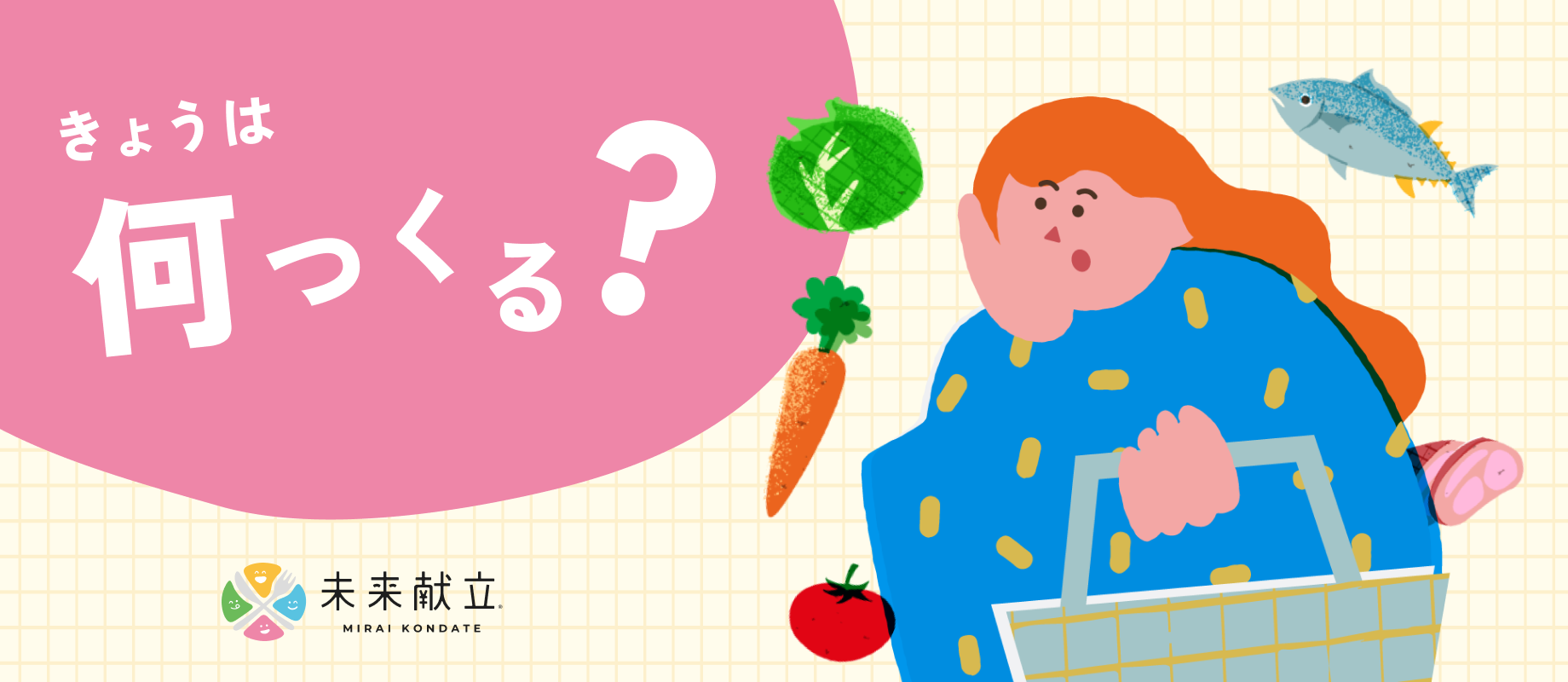
夏バテ対策には、睡眠不足の解消や温かい食べ物を食べるなどがあります。さらに、食事で様々な栄養素をバランス良く摂ることも大切です。夏だけでなく、日頃から栄養素を意識して摂ると良いでしょう。
栄養バランスの整った食事とは、主食と主菜、副菜で、炭水化物・たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維などをまんべんなく摂れる食事です。
しかし、栄養バランスの整った食事が大切なのはわかっても、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
「未来献立®」は、おいしさと栄養バランスの両方を考えた献立をまとめてご提案するサービスです。
今日不足していた栄養素があれば「明日多めに摂る」など、栄養素のつじつまをあわせる「ツジツマ献立」で、好きなメニューにあわせて栄養バランスの調整をサポートします。
食生活を見直したいものの、栄養素の取り入れ方がわからない方は、ぜひご利用ください。
栄養バランスの整った食事で夏バテ対策をしよう!
夏バテの原因は、温度差の激しい環境下で生活していることや冷たいものの食べ過ぎ、睡眠不足などがあります。
夏は冷房で冷えた室内から外出した際に、屋内外の気温差によって自律神経が乱れやすくなったり、多くの汗をかいてミネラルなどの栄養素が排泄されたりします。
夏バテ対策には、運動や十分な睡眠の他に、食事を見直すことも大切です。1日3食の食事で必要な栄養素を摂り、冷たい飲み物や食べ物は避けてこまめに水分補給をしてください。
夏バテに効果的な栄養素にはビタミンB1やB2、ビタミンC、クエン酸、たんぱく、アリシンがあります。これらの栄養素も意識した食事にしましょう。
献立にお悩みの方は、ぜひ「未来献立®」の利用をご検討ください。栄養バランスの整った食事で、暑い夏も夏バテせず乗り切りましょう。
 献立提案サービス
献立提案サービス