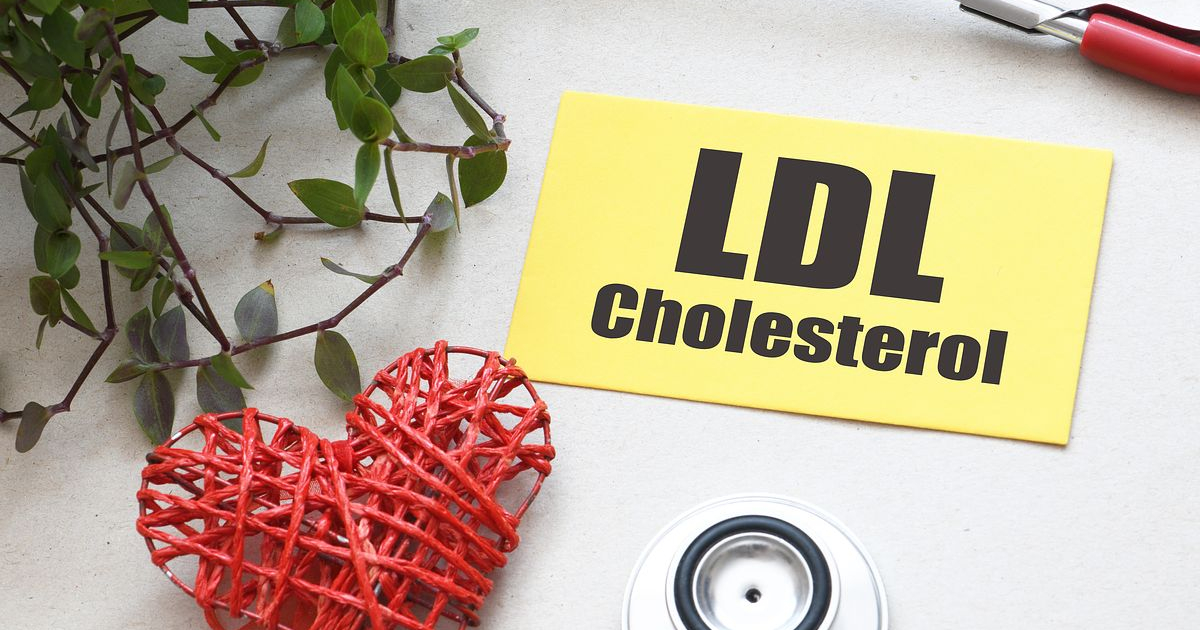食物繊維が豊富な食べ物はなに?摂取量の目安や摂り過ぎによる注意点を紹介

毎日の食生活を思い返して、「食物繊維が足りないのでは」と疑問に思ったことはありませんか。
食物繊維は、腸内環境を整えるなど、健康な体づくりに欠かせない栄養素として知られています。様々な食べ物に含まれますが、どんな食べ物からたくさん摂取できるのか、具体的に知らない方も多いかもしれません。
この記事では、食物繊維が豊富な食べ物や食物繊維の役割、摂取する時の注意点など、食物繊維をバランス良く摂取するために知っておきたい知識をわかりやすく紹介します。
食物繊維が手軽に摂れる食べ物
食物繊維は種や皮ごと口にできる食べ物や歯ごたえの強い食べ物、ぬめぬめした食感の食べ物などに豊富に含まれます。
以下の食品群ごとに、食物繊維の含有量や代表的な食べ物を紹介します。
- 野菜類
- 果物類
- 海藻類
- きのこ類
- 豆類
- 穀物類
野菜類
野菜類は皮ごと食べられるものが多く、栄養をもれなく摂取しやすい食べ物です。
また、食物繊維だけではなく、ビタミンやミネラルなどの栄養も豊富に摂取できるため、様々な種類の野菜をバランス良く摂取するとよいでしょう。
| 食品名 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維 総量 |
|---|---|---|---|
| 切り干し大根(乾) | 5.2g | 16.1g | 21.3g |
| パセリ | 0.6g | 6.2g | 6.8g |
| にんじん(生・皮なし) | 0.6g | 6.2g | 6.8g |
| モロヘイヤ(生) | 1.3g | 4.6g | 5.9g |
| ごぼう(生) | 2.3g | 3.4g | 5.7g |
| ほうれんそう(生) | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
| かぼちゃ(生) | 0.7g | 2.1g | 2.8g |
| キャベツ(生) | 0.4g | 1.4g | 1.8g |
| 大根(生・皮なし) | 0.5g | 0.8g | 1.3g |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
同じ大根でも、生の大根より切り干し大根のほうが食物繊維は豊富です。乾燥させると水分が抜けて栄養が凝縮されるため、食物繊維以外の栄養の成分量もアップします。
果物類
果物類は、野菜類と同じく、食物繊維に加えてビタミンやミネラルも多く含まれる食べ物です。ただし、果物には果糖などの糖質も多いため、食べ過ぎには注意しましょう。
| 食品名 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維 総量 |
|---|---|---|---|
| 干し柿 | 1.3g | 12.7g | 14.0g |
| いちじく(乾) | 3.4g | 7.3g | 10.7g |
| プルーン(乾) | 3.4g | 3.8g | 7.1g |
| アボカド | 1.7g | 3.9g | 5.6g |
| バナナ | 0.1g | 1.0g | 1.1g |
| りんご(皮つき) | 0.5g | 1.4g | 1.9g |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
果物に多い食物繊維がペクチンで、ジャムのとろみのある食感はペクチンの作用によるものです。
海藻類
海藻類も食物繊維が多い食べ物で、ひじきはその代表的な存在です。また、昆布やわかめなどのぬめり成分には、フコイダンと呼ばれる食物繊維の一種がたっぷり含まれます。
| 食品名 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維 総量 |
|---|---|---|---|
| ひじき(乾) | - | - | 51.8g |
| カットわかめ(乾) | - | - | 35.4g |
| 刻み昆布 | - | - | 39.1g |
| 焼きのり(あまのり) | - | - | 36.0g |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
さらに、ミネラルたっぷりの海中で育つ海藻類には、ナトリウムやマグネシウム、カリウム、カルシウム、亜鉛などのミネラルも凝縮されています。日々の食事に採り入れれば、不足しやすい栄養を摂取できるでしょう。
きのこ類
きのこ類はほぼ水分で、脂質や糖質もほとんどないため、低カロリーでヘルシーな食べ物として知られています。また、野菜類を上回る食物繊維を含んでいる食材も多く、少しの量でも満腹感を得やすいでしょう。
| 食品名 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維 総量 |
|---|---|---|---|
| きくらげ(乾) | 0g | 57.4g | 57.4g |
| 干ししいたけ | 2.7g | 44.0g | 46.7g |
| しいたけ(生) | 0.4g | 4.1g | 4.6g |
| しめじ(生)(ほんしめじ) | 0.3g | 1.6g | 1.9g |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
きのこ類には他にもビタミンB群やビタミンD、アミノ酸などが多く含まれ、代謝アップや疲労回復、健やかな体づくりにも役立ちます。
豆類
豆類は、ひとつひとつの小さな粒のなかにたくさんの栄養を詰め込んだ、万能な食べ物です。食物繊維だけではなく、ビタミンやミネラル、ポリフェノールなどの機能性成分が多く含まれます。
| 食品名 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維 総量 |
|---|---|---|---|
| あずき(乾・全粒) | 1.0g | 14.2g | 15.3g |
| 大豆(乾・国産豆) | 1.5g | 16.4g | 17.9g |
| いんげん豆(乾) | 3.3g | 16.2g | 19.6g |
| ささげ(乾) | 1.3g | 17.1g | 18.4g |
| きなこ | 2.7g | 15.4g | 18.1g |
| えんどう豆(乾) | 1.2g | 16.2g | 17.4g |
| あずき(こし生あん) | 0.3g | 6.5g | 6.8g |
| 挽きわり納豆 | 2.0g | 3.9g | 5.9g |
| えだ豆(生) | 0.4g | 4.6g | 5.0g |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
「畑の野菜」と呼ばれる大豆をはじめ、豆類は植物性たんぱく質も豊富です。
穀物類
穀物類は体を動かすエネルギー源となる炭水化物で知られますが、炭水化物は糖質と食物繊維で構成されているため、実は食物繊維も多く含まれています。
| 食品名 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 食物繊維 総量 |
|---|---|---|---|
| オートミール | 3.2g | 6.2g | 9.4g |
| ライ麦パン | 2.0g | 3.6g | 5.6g |
| そば(乾) | 1.6g | 2.1g | 3.7g |
| ぶどうパン | 0.9g | 1.3g | 2.2g |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
メニューの主食となる穀物類は、食物繊維の摂取量をむりなく増やしやすい食べ物です。とくに皮や粒ごと挽いたライ麦や小麦粉を使ったパンなどがおすすめです。
食べ物に含まれる食物繊維とは?

文部科学省「日本食品標準成分表」では、食べ物に含まれる食物繊維は「人の消化酵素で消化できない成分」と定義されています。多くの栄養が消化される小腸をとおり、大腸にまで達する栄養素です。
食物繊維の主な働きは、以下のとおりです。
- 噛み応えがあるため、満腹感を得やすく食べ過ぎを防ぐ
- 噛む回数の増加が唾液の分泌を促し、食べ物の消化・吸収を助け、虫歯を予防する
- 糖質の吸収をゆるやかにして、血糖値の上昇を抑える
- 脂質を吸着し、血液中のコレステロール値を抑える
- 腸内の善玉菌が増えて、便秘解消に役立つ
健康の維持に役立つ食物繊維は、たんぱく質や炭水化物などに次ぐ「第6の栄養素」とも呼ばれます。
食物繊維の種類と特徴
食物繊維にはいくつか種類がありますが、水に溶けにくい不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維、大きく2種類に分かれます。
不溶性食物繊維
不溶性食物繊維は、水に溶けない性質から、体内に取り込むと水分を吸収して膨らみます。便の量を増やして大腸を刺激し、腸のぜん動運動をサポートするとともに、腸内の有害物質を吸着して体外に出す役割を果たします。
例えば、野菜の皮などに含まれるセルロース、エビやカニなどの外殻に多いキチンやキトサンなどが不溶性食物繊維です。
水溶性食物繊維
水に溶ける性質がある一方、消化・吸収されにくい水溶性食物繊維は、糖質の吸収をゆるやかにして血糖値の上昇を防ぐ、血液中のコレステロールやナトリウムを吸着して体外に出すなどの働きをします。
例えば、果物に多く含まれるペクチン、海藻類によく見られるフコイダンやアルギン酸、こんにゃくに代表されるグルコマンナンなどが水溶性食物繊維で、粘り気があって水分をたくわえる性質を持ちます。
1日あたりの食物繊維の摂取目安量
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日あたりの食物繊維の摂取量の目安は、18~64歳で男性21g以上、女性18g以上です。
<1日あたりの食物繊維の摂取目安量>
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 3~5歳 | 8g以上 | 8g以上 |
| 6~7歳 | 10g以上 | 10g以上 |
| 8~9歳 | 11g以上 | 11g以上 |
| 10~11歳 | 13g以上 | 13g以上 |
| 12~14歳 | 17g以上 | 17g以上 |
| 15~17歳 | 19g以上 | 18g以上 |
| 18~64歳 | 21g以上 | 18g以上 |
| 65歳以上 | 20g以上 | 17g以上 |
| 妊娠・授乳中 | - | 18g以上 |
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
1950年頃は1日あたりの食物繊維の平均摂取量20g以上でしたが、穀物類や豆類を食べる機会が減るのにともなって、食物繊維の摂取量も減っています。
近年は食物繊維の大切さが注目されて改善の兆しも見えますが、厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」では1日あたりの食物繊維の平均摂取量は18.4gで、目標にはまだ届いていません。特に20代は男性が平均17.5g、女性が平均14.6gで、食物繊維不足が顕著です。
毎日のメニューに様々な食べ物を取り入れて、食物繊維の摂取を1日あたり3~4g増やせるように意識しましょう。
食物繊維を摂取する際の注意点
健康な体づくりのために、食物繊維は毎日の食べ物からの意識的な摂取が大切です。
しかし、食物繊維を摂取する際には以下のようにいくつか注意点があります。
- 食物繊維不足は腸内環境を悪化させる
- 過剰摂取は悪影響を及ぼす恐れがある
- 妊娠中の女性はとくに積極的な摂取が必要
食物繊維不足は腸内環境を悪化させる
食物繊維は腸内の善玉菌を増やすエサになり、便通を良好に保ちます。そのため、摂取量が減ると、悪玉菌の増殖を招き、腸内環境を悪化させる恐れがあります。
腸は食べ物の消化・吸収や排出を行う大切な器官であり、腸内環境の悪化は健康にも悪影響です。腸の免疫力が下がり、生活習慣病などを引き起こすことも考えられます。
過剰摂取は悪影響を及ぼす恐れがある
食物繊維を摂取すると、糖質やコレステロールの吸収を穏やかにしてくれます。しかし、過剰な摂取は、鉄分やカルシウム、マグネシウム、亜鉛など、ミネラルの吸収まで妨げる場合があります。
また、水溶性食物繊維の摂りすぎは便をやわらかくしすぎて下痢を招き、不溶性食物繊維の摂りすぎは便のカサを増やして便秘を悪化させることもあるため、腸内環境を改善させたいならとくに注意しましょう。
妊娠中の女性はとくに積極的な摂取が必要
妊娠中の女性は、黄体ホルモンの働きにより腸の働きが弱くなる他、大きくなった子宮が腸を圧迫するため、便秘になりやすい傾向があります。便秘を防ぐために、普段よりも積極的に食物繊維の摂取を心がけましょう。
2020年には、妊娠中に食物繊維をしっかり摂ると、生まれてくる子どもの肥満を防ぐとの研究結果も発表されています。
「未来献立®」を活用して食物繊維を意識した食事を
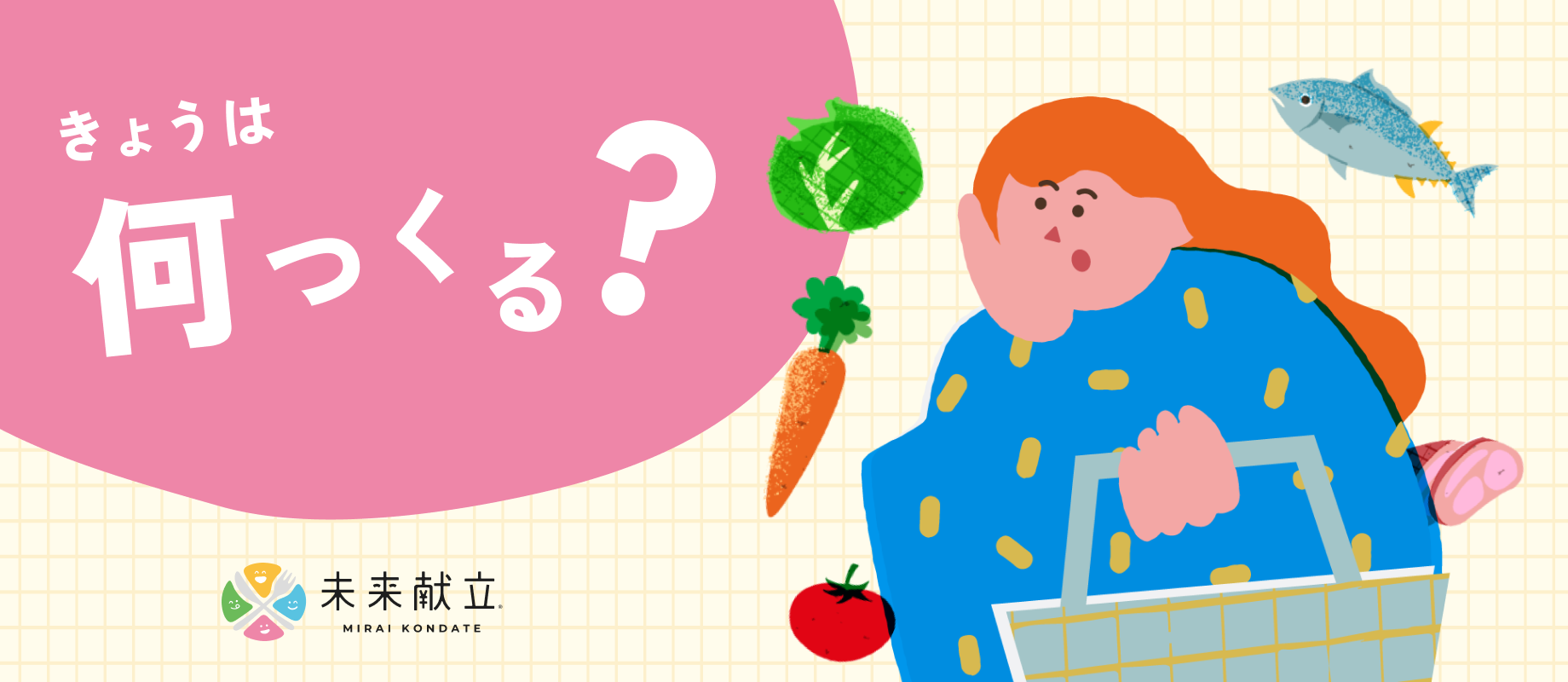
食物繊維は、摂り過ぎても不足しすぎても体によくない影響があるため、いろいろな食べ物からバランスのよい摂取が大切です。
食物繊維を含む栄養バランスの整った食事が大切なのはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
「未来献立®」は、おいしさと栄養バランスの両方を考えた献立をまとめてご提案する献立提案サービスです。朝ごはんと夜ごはん、昨日と今日など、複数の食事で栄養バランスをとる「ツジツマ献立」なので、無理なく続けられます。
バリエーション豊かなメニューで、楽しみながら栄養バランスをコントロールできるでしょう。
毎日の食事からバランス良く栄養を摂取して食物繊維を補おう
食物繊維は、野菜や果物、穀物など、様々な食べ物に含まれる栄養で、腸内環境の改善などに役立ちます。
食生活の変化から日本人は食物繊維不足が続いているため、1日あたり3~4gほど摂取量を増やすと良いでしょう。ただし、摂りすぎも体に良くないため、適量を心がけることが大切です。
栄養バランスの考えられた献立をご提案するサービス「未来献立®」は、食物繊維の摂取と健やかな食生活の実現をサポートします。おいしいメニューを楽しみながら、栄養バランスのツジツマあわせができるでしょう。
 献立提案サービス
献立提案サービス