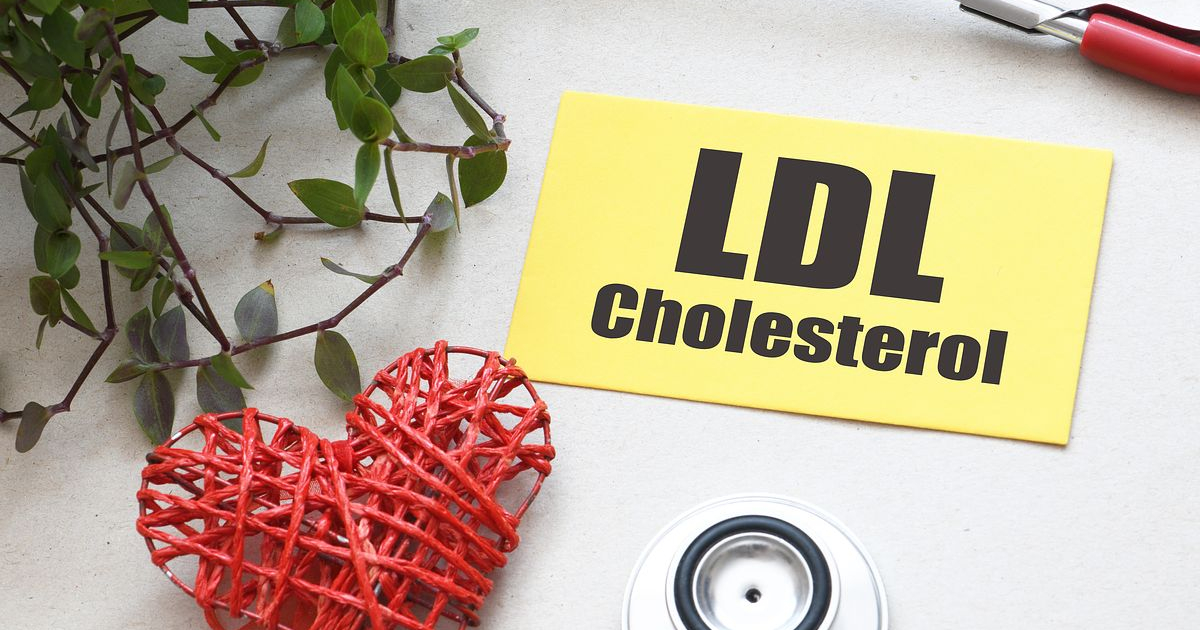血圧の正常値を年代別に解説!数値を正常に保つ方法も詳しく紹介
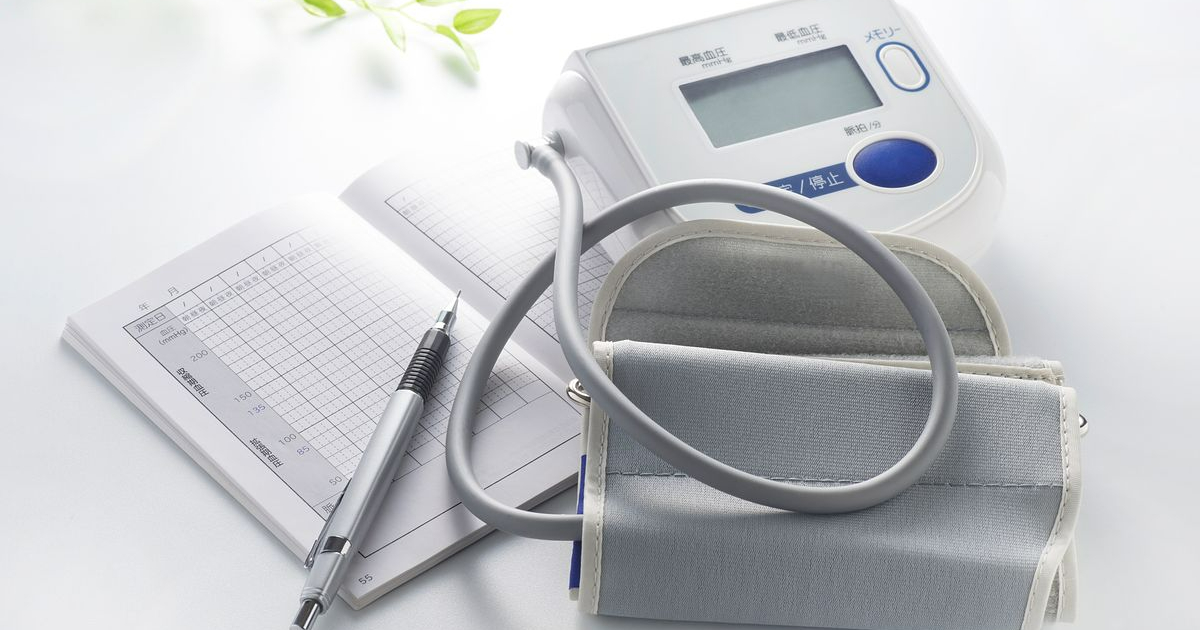
健康診断の結果で血圧の数値を指摘されると、健康状態が気になる方もいるのではないでしょうか。高血圧や低血圧の状態が続くと、病気を引き起こす可能性が高まります。
この記事では、血圧の正常値や低血圧と高血圧の基準、血圧を正常値に近づけるための方法を解説します。
血圧の数値を改善して、毎日を健康に過ごしましょう。
血圧とは
血圧とは、血液が動脈を流れる時に血管にかかる圧力をいいます。心臓が収縮し、血液が血管に送り出される時の血圧が収縮期血圧(最高血圧)です。
一方、全身に送り出した血液が心臓に戻り、拡張した時の血圧を拡張期血圧(最低血圧)と呼びます。
なお、血圧値は「収縮期血圧(最高血圧)/拡張期血圧(最低血圧)」と示され、単位は「mmHg(ミリメートル・エイチ・ジー)」です。
血圧の測定方法は、病院やクリニックで測る診察室血圧と、自宅で測る家庭血圧の2種類があります。血圧は様々な条件で変動するため、病院で計測するだけでなく、日頃から自宅でも計測して記録すると良いでしょう。
血圧の正常値と低血圧・高血圧の基準値
血圧には、正常値と低血圧、高血圧の基準となる数値が決められています。
以下で、正常値、低血圧、高血圧の基準値を紹介するため、ご自身の数値と比較してみてください。
| 診察室血圧 | 家庭血圧 | |
|---|---|---|
| 正常値 | 130/90mmHg以下 | 125/75mmHg以下 |
| 低血圧の基準値 | 収縮期血圧(最高血圧)が100mmHg未満 | |
| 高血圧の基準値 | 140/90mmHg以上 | 135/85mmHg以上 |
出典:日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」
正常値
血圧の正常値は、診察室血圧と家庭血圧で数値が変わります。診察室血圧の場合130/90mmHg以下、家庭血圧の場合は125/75mmHg以下が正常値です※。
※出典:日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」
低血圧の基準値
低血圧の明確な基準値は示されていません。一般的に、収縮期血圧(最高血圧)が100mmHg未満の場合に低血圧と診断されます。
高血圧の基準値
高血圧の基準値は正常値と同じく、診察室血圧と家庭血圧で数値が変わります。診察室血圧の場合140/90mmHg以上、家庭血圧の場合は135/85mmHg以上で高血圧です※。
高血圧の基準値を超えると、高値血圧、Ⅰ度高血圧、Ⅱ度高血圧、Ⅲ度高血圧とさらに細かく分類されます。
| 高値血圧 | Ⅰ度高血圧 | Ⅱ度高血圧 | Ⅲ度高血圧 |
|---|---|---|---|
| 130-139/80-89 | 140-159/90-99 | 160-179/100-109 | ≧180/≧110 |
高血圧の数値が上がるごとに危険度が増すため、注意が必要です。
※出典:日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」
年代別の血圧の平均値
血圧の正常値は前述のとおり、診察室血圧で130/90mmHg以下、家庭血圧で125/75mmHgとされています。
以下で、年代別の血圧の平均値を一覧で紹介します。なお、平均値のデータは血圧を下げる薬の使用者を除外した数値です。
年代別の血圧平均値
| 性別 | 血圧(mmHg) | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代・80代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 収縮期(最高)血圧 | 115.9 | 117.2 | 125.4 | 129.7 | 134.1 | 133.9 |
| 拡張期(最低)血圧 | 68.1 | 73.8 | 80.6 | 81.0 | 78.3 | 74.5 | |
| 女性 | 収縮期(最高)血圧 | 105.7 | 108.0 | 113.7 | 121.8 | 130.6 | 133.1 |
| 拡張期(最低)血圧 | 63.8 | 66.4 | 70.9 | 74.5 | 76.7 | 73.9 |
出典:厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査報告」
表を見ると、年齢とともに血圧の平均値が上がっていることがわかります。理由は、加齢にともなって動脈や細静脈の弾力が失われ、血液を素早く送り出せなくなるためです。
低血圧と高血圧で引き起こされる病気

低血圧や高血圧が原因で、病気を引き起こす場合があります。
以下で、低血圧と高血圧によって引き起こされる病気を詳しく解説します。
低血圧で引き起こされる病気
低血圧の状態が続くと、全身に十分な血液が送られなくなり、栄養や酸素が行き渡らない状態になります。
低血圧の主な症状は、めまいや立ちくらみ、全身の倦怠感などです。
低血圧は「本態性低血圧(一次性低血圧)」「起立性低血圧」「症候性低血圧(二次性低血圧)」の3つに分類されます。なかでも、症候性低血圧は何かしらの病気によって引き起こされます。
以下で、3つの低血圧の状態を詳しく解説します。
- 本態性低血圧(一次性低血圧)
原因がわからないまま、常に血圧が低い状態です。めまいや頭痛などの症状を引き起こします。 - 起立性低血圧
寝ころんだ状態から急に立ち上がったり、長時間立ち続けたりすると血圧が低くなる状態です。立ちくらみなどの症状が挙げられます。 - 症候性低血圧(二次性低血圧)
低血圧を引き起こす疾患がある状態です。心筋梗塞などの心臓疾患や、出血など血液量の低下が挙げられます。症候性低血圧は、病気を突き止める必要のある低血圧です。
高血圧で引き起こされる病気
高血圧の状態が続くと、血管が硬くなり動脈硬化が進みます。
血管が狭く硬くなると、さらに血圧が上昇し、脳卒中や心臓病、肝臓病などを引き起こす危険性が上がります。
血圧を正常値に保つ方法

低血圧や高血圧によって、様々な病気が引き起こされる可能性が高まります。
健康に生活するためには、血圧を正常値に保つことが大切です。血圧を正常値に保つためには、適正体重を維持する、適度に運動する、規則正しい生活を送ることなどを意識しましょう。
以下で、血圧を正常値に保つ方法を詳しく解説します。
- 適正体重を維持する
- 適度に運動する
- 規則正しい生活を送る
適正体重を維持する
適正体重を知るために、まずはBMIを算出する計算式に当てはめて、現在の状態を知りましょう。BMIとは肥満や低体重の判定などに用いられる値です。
[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で計算した数値が、25未満になると良いとされています。もし数値が25以上だった場合は、25を目標にしましょう。
肥満は高血圧だけでなく、糖尿病などの病気を引き起こす可能性が高まります。個人差はありますが、3kg~4kg減量すると血圧の低下が期待できるため意識すると良いです。
ただし、減量を意識するあまり、急激に体重を落とすと体調不良やリバウンドの恐れもあります。時間をかけてゆっくり減量するよう心がけましょう。
適度に運動する
適正体重を維持するためにも、適度な運動を取り入れましょう。有酸素運動を定期的に行うと、血圧を下げる作用が期待できます。
運動の時間は一日30分以上、週180分以上が目安です。体を慣らしながら、少しずつ取り組むことをおすすめします。
もし運動する時間が取れない場合は、可能な限り階段を使ったり歩いたりするなど、運動を生活の中に組み込むと続けやすいです。
規則正しい生活を送る
運動の他に、規則正しい生活も血圧を正常値に保つために大切です。
血圧は日中に高くなり、睡眠中は低くなります。睡眠中に低くなるのは、血管の修復が行われるためです。そのため、十分な睡眠時間を確保するよう心がけましょう。
また、生活リズムを正し、体重を維持するためには食生活の見直しも重要です。
例えば、血圧を正常値に保つためには、塩分の取りすぎに注意が必要です。日本高血圧協会では、1日の食塩摂取量が6g未満になるよう推奨しています。
塩分の他にも、お酒や煙草も血圧に悪影響を与えるため、控えましょう。
「未来献立®」で栄養バランスのとれた食事を意識してみよう
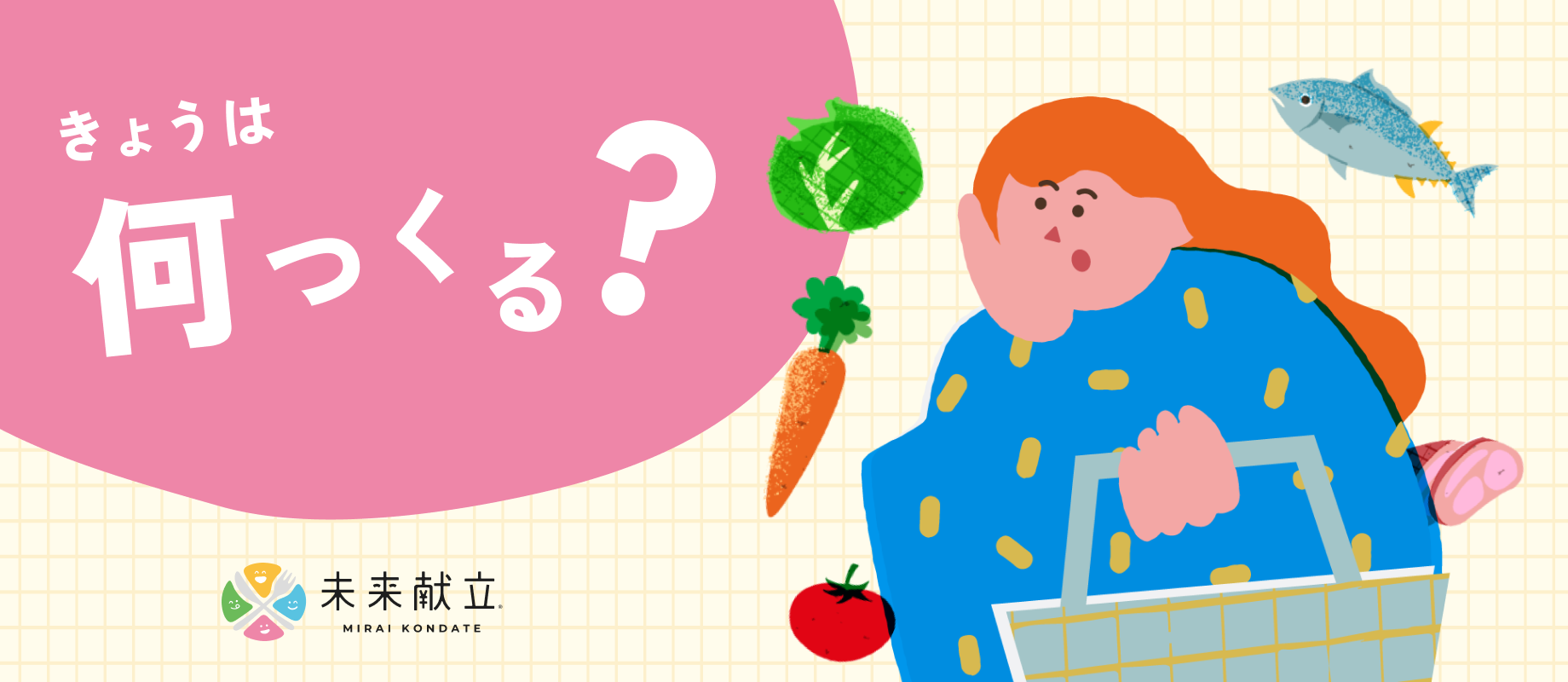
食事内容を改善したい方は、栄養バランスを意識してみてください。塩分の取りすぎは、病気を引き起こす可能性が高まります。日本高血圧協会が推奨する、1日の食塩摂取量6g未満を意識しましょう。
しかし、栄養バランスの整った食事が大切なのはわかったものの、一食一食ちゃんと考えるのは難しいと感じた方もいるかもしれません。
【栄養バランスは数日間でツジツマを合わせる】ことでも良いのです。
1日で完璧にしなくていいなら、少し気が楽になりませんか?
「でも、どんな食事にすればいいの?」と思ったら、ぜひ献立提案サービス「未来献立®」をお試しください。
「未来献立®」はおいしさと栄養バランスの両方を考えた献立をまとめて(最大8日間)ご提案するサービスです。
「ツジツマ献立」で好きなメニューにあわせて栄養バランスの調整をサポートします。「未来献立®」の献立提案サービスを利用して、栄養バランスの取れた食事を手軽にお楽しみください。
血圧を正常値に保つために生活習慣を見直そう
血圧は、正常値よりも高すぎたり低すぎたりすると、病気を引き起こす可能性が考えられます。食生活や生活習慣を見直し、血圧を正常値に保つよう意識すると良いでしょう。
特に、食生活は無理なく続けられるかがポイントです。ぜひ「未来献立®」を取り入れて、栄養バランスの取れた食事を楽しみましょう。

監修者
藤堂 紗織(とうどう さおり)
日本医科大学医学部卒業。日本医科大学武蔵小杉病院で研修後、腎臓内科学教室に入局。その後、善仁会丸子クリニックにて10年院長勤務。透析治療に携わる。令和元年に、街のかかりつけ医となれるよう、Alohaさおり自由が丘クリニックを内科、皮膚科、美容皮膚科を標榜して開業。
 献立提案サービス
献立提案サービス